論理的な関係をつかんで問題を解く
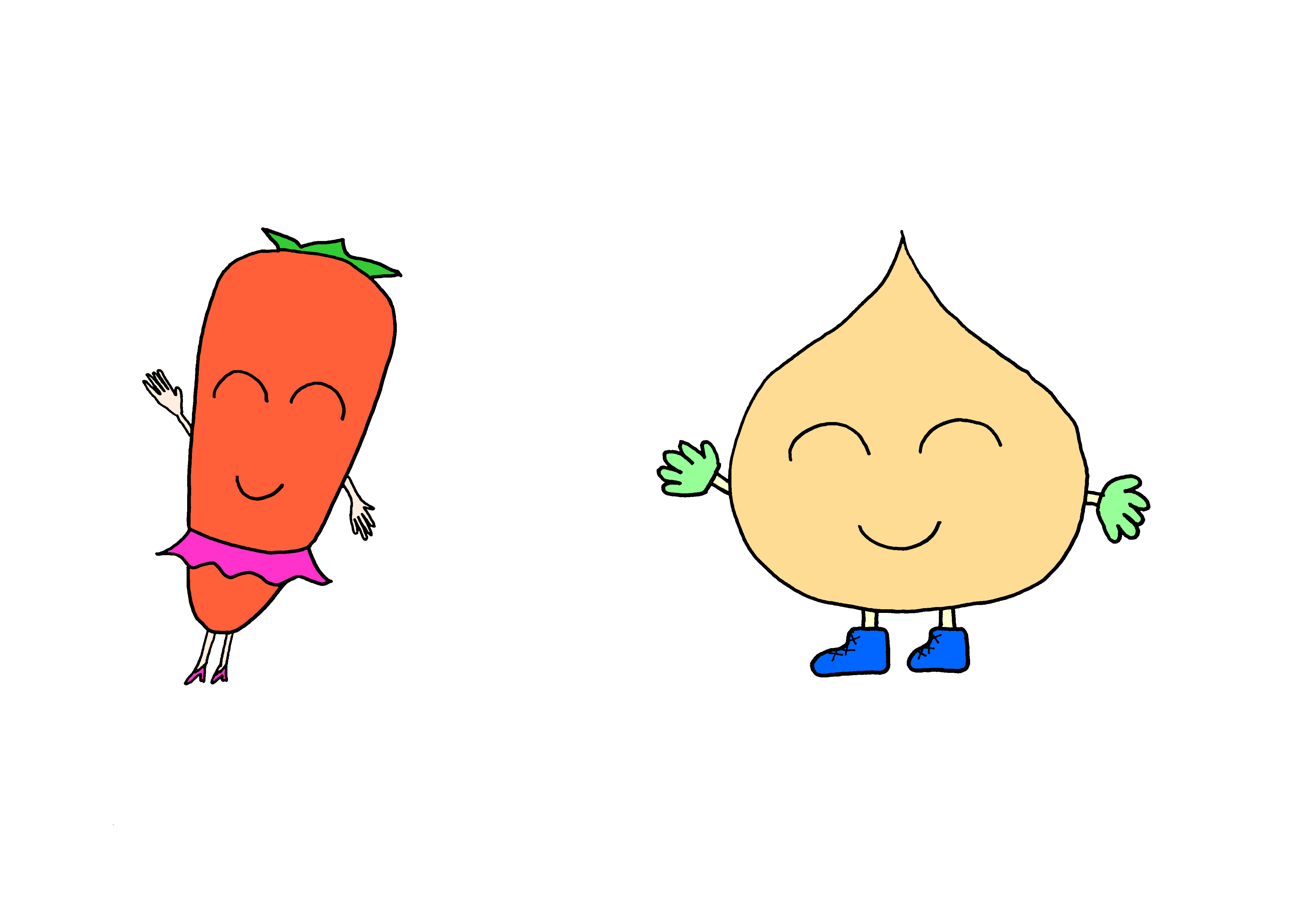
情報処理技術者試験の試験問題は,論理的な文章でできています。
論理的な文章というのは,言葉が次の3つの関係でつながっていて,文章の意味が1つに決まる文章のことです。
・イコールの関係(等価関係)
・対立関係
・因果関係
そのため,この論理関係をちゃんと把握できれば,試験問題を解くのはとても楽になります。
一番わかりやすいのが,アルゴリズム(プログラミング)問題です。
プログラミングというのは,作りたいものがあって,それをプログラミング言語で書き下ろしていくことです。
ですので,そのプログラムの説明と,プログラムは,イコールで結ぶことができます。
基本情報技術者試験の午後問8(アルゴリズム)や応用情報技術者試験の午後問2(プログラミング)の問題では,だいたい次の2つの段落があります。
〔プログラムの説明〕
〔プログラム〕
この2つは,使用する言語が〔プログラムの説明〕の方は日本語,〔プログラム〕の方がアルゴリズム特有のプログラム言語,というだけで,イコールの関係です。
そのため,どの文章がどのプログラムと対応するかを考えていくことが,問題を解くときの第一歩になります。
プログラムだけ眺めていても,何をするのかはわかってきません。
もちろん,そこで対応させた後は,プログラム特有のテクニック(定番のアルゴリズムを利用する,変数に値を入力するなど)を使って変換する必要はあります。
この部分に関しては,プログラミングの勉強過程で身につけていく知識です。
ただ,その前提として,論理的に文章を整理して,正確に読んで対応させることが大切なのです。
ストラテジ系やマネジメント系の問題では,問題文をイコールの関係を中心に対応させていくと,それだけで答えが導けるものも多くあります。
問題文から,設問で聞いていることとイコールの内容の文章を探してくるだけで,答えになることもあります。
もちろん,知識が必要になることも多いですが,その知識も,問題文と結びつけて考える必要があることが多いです。
テクノロジ系の問題だと,対立関係や因果関係も結構出てきます。
ネットワークやセキュリティの問題などでは,原因と結果の関係が大切で,その結果になった理由,というのをよく聞かれます。
例えば,基幹スイッチの1つのポートが故障したため,基幹サーバ1のみが使用できなくなった,というのを,問題文の記述から考察して読み取る,という形です。
なんとなく問題文を解いていると,思い込みで問題文に書いてあることとは別のことを考えてしまいがちです。
きちんと問題文を論理的に読んでいくことで,問題の意図を正確にとり,正解を導いていくことができます。
論理的な関係をつかんで読む読み方は,一朝一夕にできるものではありませんが,何度かやっていると慣れてきて早くできるようになります。
問題演習を行うときに,丁寧に論理を考えながら問題を読んでいきましょう。
