なるべく直近の過去問を解く
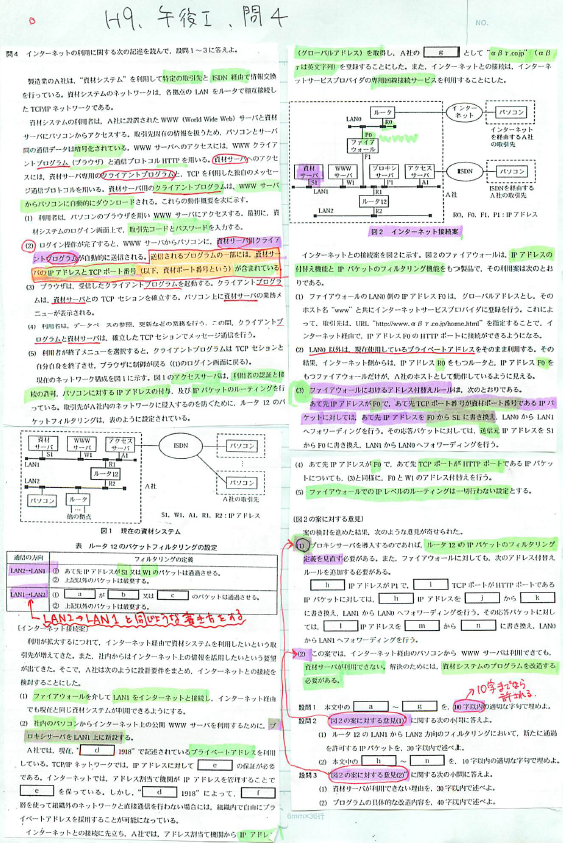
最近,試験問題の出題傾向を整理していて,改めて感じたのですが,昔と今とでは出題の傾向が,結構変わってるのです。
例えば,応用情報技術者試験のデータ構造では,ソフトウェア開発技術者時代には定番だった,二分木やB木など,「木」に関することは出てきていません。
多分,難易度が高いからだとは思いますが,その代わり,「リスト」問題が頻出です。
平成21年度の改訂以前の問題からは,大分傾向が変わってきていますので,旧試験の過去問だと,今とは違う可能性が高いのです。
普通に過去問集を解いている時には,年1回の試験区分でも過去4期分の過去問があるので,そんなに大量にやる人は少ないとは思います。ただ,問題集などでは,たまに平気で10年ぐらい前の過去問を載せていることがあるので,そういった場合には注意が必要です。
単に「今は出ない」というだけではなく,時代の流れで答えが変わってきている問題もあります。
以前も取り上げましたが,今の問題では,「更新可能なビューの条件」に,「単一の表を参照していること」は解答ではなくなっています。
これは,標準SQLの改訂が原因です。
あと,今の情報セキュリティ分野での解答で,SQLインジェクション対策にサニタイジングを書くと正解にはならないと思います。
バインド機構など,より確実なものの利用が求められているはずですので,そのあたりの技術の進化についても頭に入れておくといいです。
情報セキュリティスペシャリスト試験はここ1〜2年で,かなり技術寄りになってきましたので,新しい問題が解けるようになるのはとても大切です。
また,今年の秋だと,シラバス改訂も入りましたし,プロジェクトマネジメント(PMBOK),ITサービスマネジメント(ITIL),システム開発技術(共通フレーム2013)あたりは,問題が変わってくる可能性が高いです。
試験問題は,時代の流れを受け入れつつ,徐々に進化していっていますので,昔のものにこだわりすぎると,間違った解答をしてしまうおそれがあります。
それは,試験対策だけでなく,業務にも言えることだとは思います。
昔の技術にこだわりすぎていると,いつのまにか仕事でも取り残されてしまいます。
新しい技術をキャッチアップしていくことは,技術者にとってとても大切なことです。
直近の過去問を解いてみて,分からない言葉があったら調べて理解しておきましょう。
まったく同じ過去問は出てこないとは思いますが,同じようなことは出題される可能性が高いです。
特に,午前ではじめてみるような言葉は,次は午後で出てくることが多いです。
試験制度が変わって,「すごく昔の問題の使い回し」というのは減ってきています。
システムアーキテクトの午前2などは,過去問の再出題自体が少なかったりもします。
「過去問を答えごと覚えておけば午前は大丈夫」というのは段々通用しなくなっているような気がします。
最近の傾向を知るためにも,なるべく新しい年度の問題で演習を行いましょう。
そして,その問題をしっかり理解して,似たような問題が出たら解ける,というレベルまで学習できれば,合格は近いです。
試験まであと少しですが,できることを確実に,一歩一歩進んでいきましょう。
