試験問題のストーリーを記憶に残す
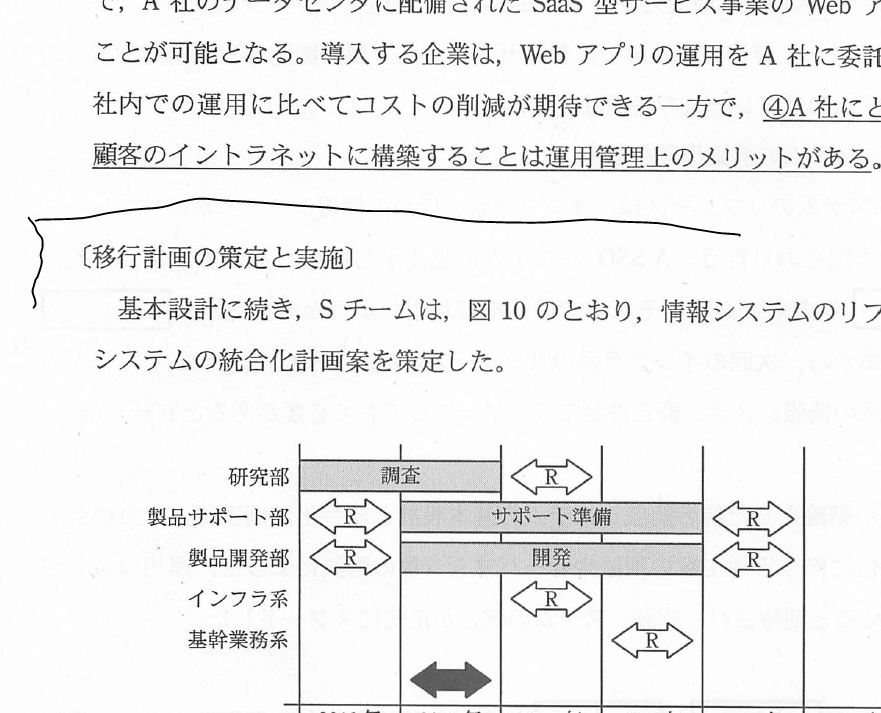
今日,原稿書きのために調べていて知ったのですが,ドラえもんに出てくるのび太の先生って,「先生(せんじょう)英一郎」って名前なんですね。(出典:Wikipedia「先生(ドラえもん)」より)
先生って姓の先生だったとは。。。生まれながらの先生ですね。
多分これで,のび太の先生の名前は,一生忘れないと思います。\(^^;ヲイ
というのは冗談として,こんな感じで意味づけがあって,ストーリーになるものは,記憶に残りやすいのです。
試験に受かる人って,「試験問題のストーリー」が頭に入っている人が多いです。
「DB24年春午後1問2では,またJ君はダメダメでK部長に指摘されてるね。」とか,「NW22年秋午後1問2のO主任とU君は,なんかU君が主導権を握ってるね」とか,問題をストーリーとして語れる人は,たいがい受かります。
過去問演習で,設問で問われていること以外の,全体像について見えるようになれば合格は近いと思います。
そして,この「ストーリーが頭に入る」ことは,高度区分では実はとても大切です。
わかりやすいのは論述系の区分ですが,午後2の論述式の試験は,設問ア,イ,ウで,一連のストーリーである必要があります。
このストーリーがつながっているかどうかというのは,「論旨の一貫性」という,大事な論述のチェックポイントです。
どのようなストーリーを作ればいいのかは,午後1のストーリーを見ると,だいたいイメージできます。
その試験区分の職業で大切なこと,行うべきことは,状況が違っても大体同じです。
論文ではその,「経験から来る具体例」をもとに,「その試験区分で典型的なストーリー」を求めているのです。
例えばPM24年春午後1問1では,外部設計の状況確認がテーマですが,次から次へと問題が起きてきます。
営業部のレビューが多忙で,毎回異なる代役が来てしまって,その場で意思決定できないとか。。。
設計の遅れを請負先であるX社に押しつけて,「要員はひっ迫しているが,何とか対応できる」と言わせたり。。。
こういった問題を,営業部に申し入れをして解決を図ったり,スコープを変動させて現実的な落としどころを見つけたりしていきます。
これは,ステークホルダマネジメントやスコープマネジメントが問われる午後2問題には,とても参考になる事例だと思います。
読んでいても,つい「あるある」と感じますし,日本ではそこら中で起こっていそうな事例です。
問題演習をするときには,単に設問の解き方を身につけるのではなく,こういった「問題そのもの」のストーリーを意識して頭に入れることが大切です。
論述系では,午後1問題でこれができると,午後2の論述式の質向上につながります。
その試験で求められているストーリーが,徐々に頭に出来上がってくるからです。
そして,論述系以外でも,高度区分ならこの方法は効果があります。
特にやった方がいいのは,情報セキュリティスペシャリスト試験です。
情報セキュリティスペシャリスト試験の問題は,一見あいまいに見えるのですが,いろいろな問題を見ていると共通の思想が見えてきます。
それが「情報セキュリティの考え方」でもあるのですが,考え方を身につけるにはストーリーの理解が大切です。
問題演習で典型的なセキュリティ問題のストーリーが頭に入っていると,新しい問題でも,何が問われているかイメージしやすくなります。
データベーススペシャリストもエンベデッドシステムスペシャリストも,ストーリーは役立つと思います。
ただこの2つは,比較的問題が素直なので,問題演習をちゃんとやっていれば,自然に頭に入ってくるようにも感じています。
過去の問題は,実際の現場で起こった事例の宝庫です。
うまく実力アップに活用しながら,最後の仕上げをしていきましょう。
