「正しい」と「適切な」を使い分ける
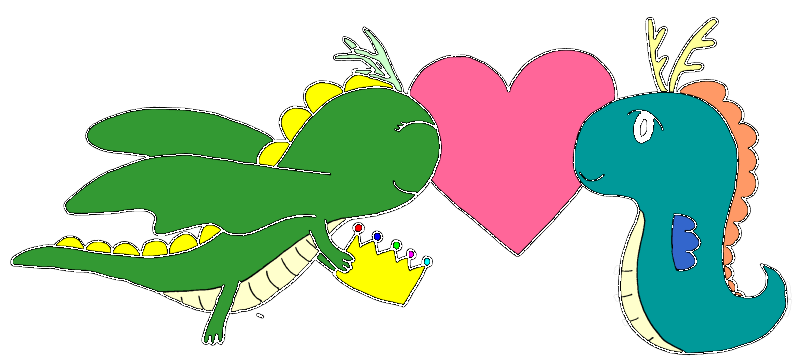
情報処理技術者試験の英訳にあたって,IPAでは,「情報処理技術者試験のアジア展開関連文書の英訳」に係る一般競争入札」という入札公告を出しています。
これを見ると,ITパスポートや基本情報技術者などの基礎資格だけでなく,応用情報技術者やネットワークスペシャリスト,エンベデッドシステムスペシャリスト,データベーススペシャリスト,情報セキュリティスペシャリストも含まれています。
高度区分も,英語でアジア展開する予定のようですね。
この件に関して,英語とはまったく関係ないのですが,少し気になった部分があります。
入札の仕様書(PDF)で,13ページに書いてある,「正しい」と「適切な」の違いについてです。
この文書の「5.6 形容詞・副詞の使い分け」に,次のような記述があります。
数学的に正解が証明できるもの、または正解に一意性があるものについてだけ、「正しい(correct)」という表現を用いる。日本語の試験問題では、「正しい」と「適切な」を厳密に使い分けているので、英訳の際にも同じく、厳密に使い分ける必要がある。
これは,試験問題を見ていてなんとなく気づいてはいましたが,その通りだと思います。
「正しい」という言葉は,実は簡単には使えない言葉です。
正しいことを証明するというのはとても大変ですし,1つだけ正解で他が違うというのは,厳密に言い切れないことがほとんどです。
ですので,試験問題では,「正しい」という記述は,あまり出てきません。
例えば,平成24年秋応用情報技術者午前の問題では,「正しい」という問い方をしているのは,1問(問3)のみです。
ちなみに,問3はハミング符号の問題で,「正しい情報ビットはどれか」と問われています。
これは,数学的に正解は1つですので,「正しい」という表現が使えます。
それ以外の問題は,だいたい[適切な」という表現を使っています。
同じ平成24年秋応用情報技術者午前の問題だと,「適切な」は,次の21問で使われています。
問6,問11,問14,問15,問17,問23,問24,問27,問30,問33,問36,問39,問41,問45,問46,問51,問52,問58,問60,問66,問70
見落としもあるかもしれませんが,「適切な」が多用されているのはわかるかと思います。
情報処理技術者試験で問われる内容は,厳密な正解がないものの方が多いです。
一般的にこう言われている,経験則からこれが今のところ妥当,というところで出題しているものも,実は結構多いのです。
ですので,選択問題では,「確実な正解」ではなく,最も妥当な,「適切なもの」を選ばせるのです。
このあたりは,進化途中の技術だとある程度仕方のないところなので,ある程度割り切る必要があります。
よく,研修の質問などで,「厳密にそんなことは言えない。この答えだって間違いとはいえないのではないか。」ということを言われる方がいます。
これはもちろん,その通りなことが多いです。
そういったいろいろな解釈も含めた上で,より妥当な,適切な解答を選ぶ必要があるのです。
特にあいまいな問題だと,さらに「最も適切なものはどれか」という聞き方で,「他も間違いじゃないんだけどね」ということを匂わせているものもあります。
完璧な正解がない中で,より妥当な考え方を選ぶ,そんな態度も大切です。
これは,問題文を読むときだけではなく,文章を書くときにも言えます。
論述式の答案で,「正しい」をむやみに使うと,知性がない感じになってしまうのです。
「~するのが適切だと考えられる・・・」など,適切という言葉を使った方が適切です。^^;
情報セキュリティスペシャリストの午後の記述式でも,「正しい」と「適切な」は区別して書くといいと思います。
というより,セキュリティは特に,「一意に決められる正解」はありませんので,「正しい」は基本的に使わないのが賢明です。使えるとしたら,暗号化などに使う公開鍵,秘密鍵ぐらいだと思います。
データベーススペシャリストは逆に,「正しい」を出題者側が結構使っていますね。例えば,平成21年度午後1の採点講評(PDF)では,何度も「正しく」という言葉が使われています。
主キーや候補キーは,数学的に正解が証明できるので,こういう言い方になるのだと思います。
試験の問題など,文章だけで伝える場合には,言葉選びはすごく大切になってきます。
問題を読むときには,相手の意図したことを,言葉に敏感になって正確に読み取りましょう。
そして,答案を書くときにも,相手にきちんと言いたいことが伝わるように,適切に言葉を選んでいきましょう。
