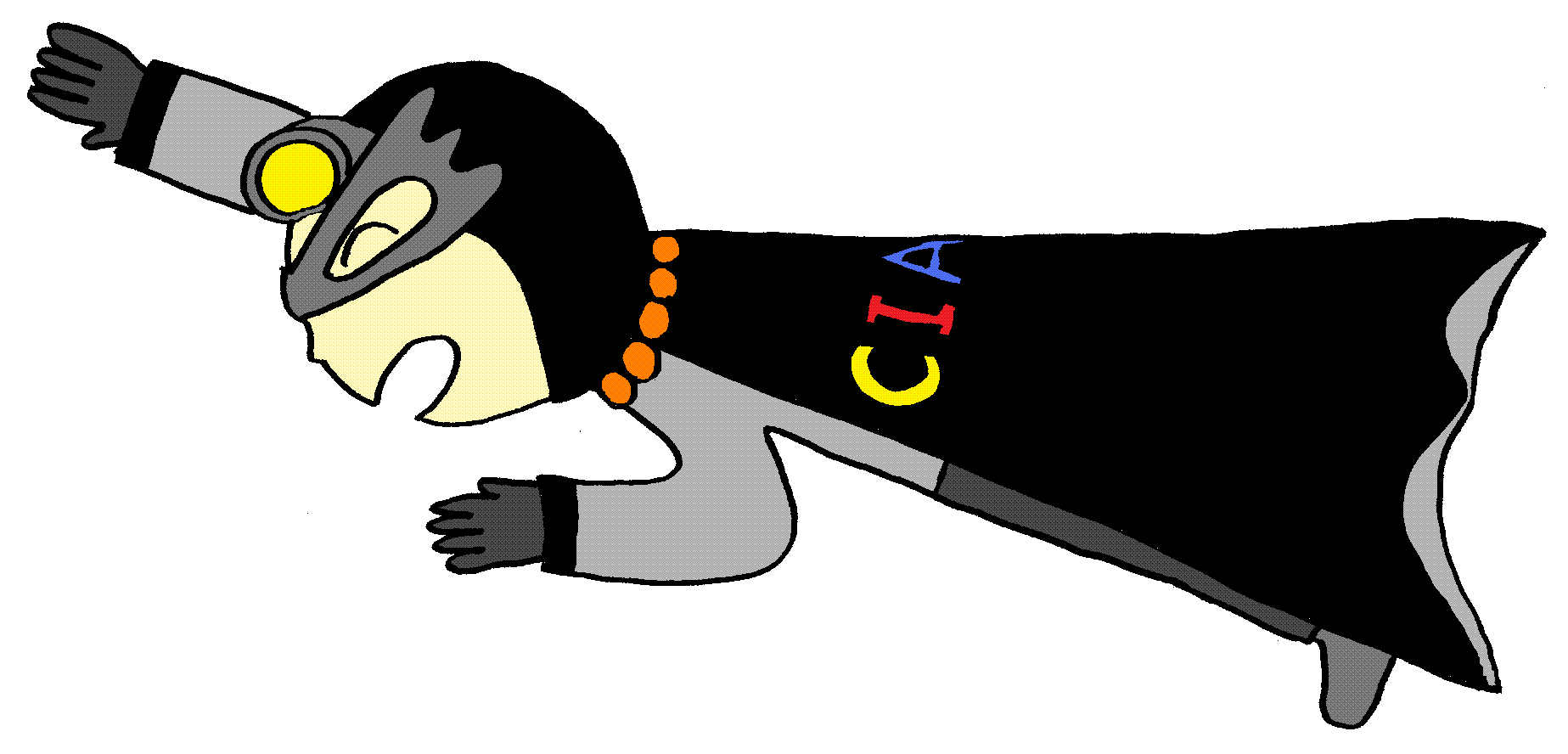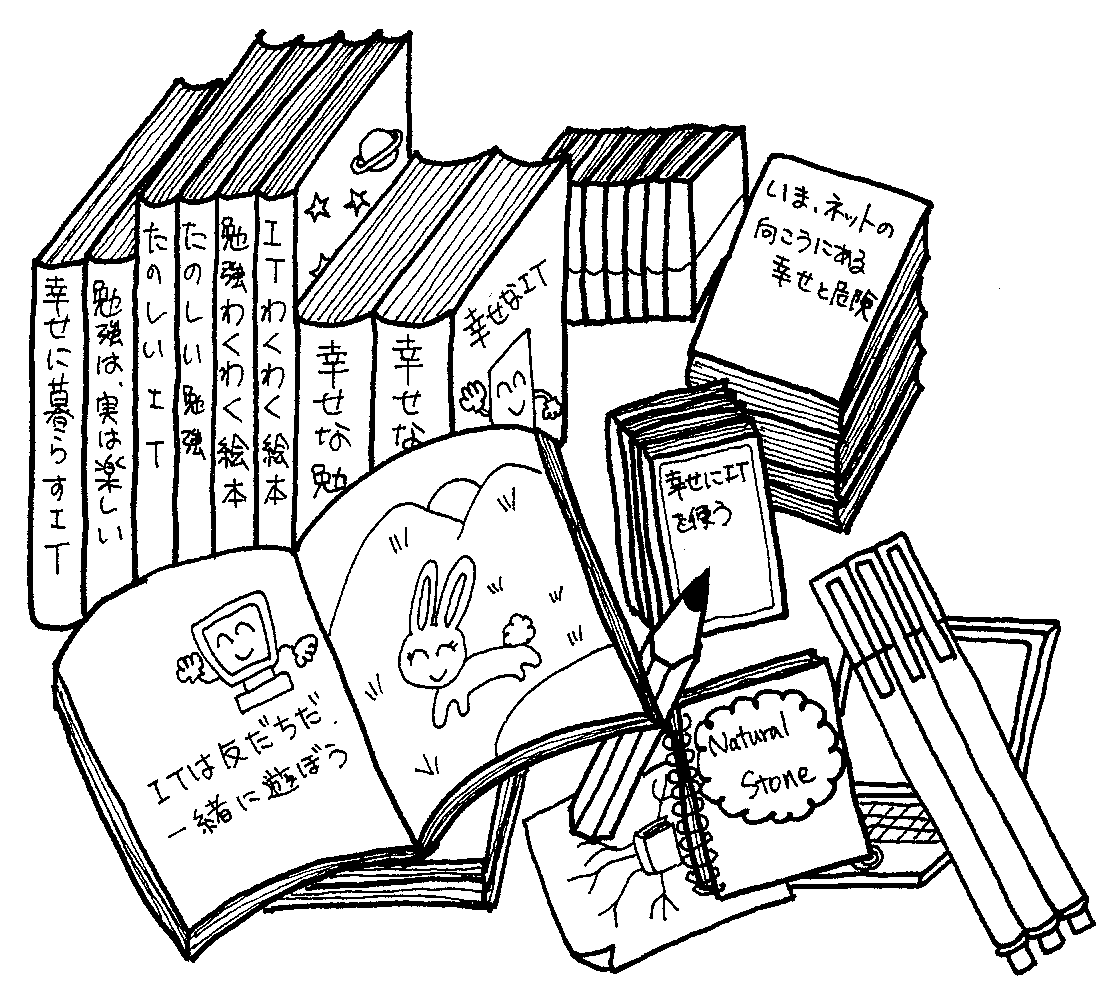残り1ヶ月の計画を立てよう
わく☆すた,美月です。
今日は3月18日,いよいよ春の情報処理技術者試験まであと1ヶ月ですね。
わく☆すたでは,今回は試験当日に応用情報技術者試験の解答速報を出します。
単純に,私が応用情報技術者試験を受けるので,「当日解答速報が出せるな」っていう,単純な思いつきです。
9割ぐらいの精度でアップして,それからブラッシュアップしていければいいかな,って考えてます。
このブログに載せていきますので,コメント,つっこみは歓迎です。
一緒に応用情報技術者試験を受ける方も,そのほかの区分を受験される方も,悔いの残らないよう,あと1ヶ月を有意義に過ごしていきましょう。
ということで私は今日,手帳を買いました。
1月に買った手帳がなんか気に入らなかったので,4月始まりの手帳で,新たな1年のスタートを切ることにしました。
買ったのは,「ほぼ日手帳」という手帳です。毎日1ページ,いろんなことが書き込める,自由な使い方ができる手帳です。
使ってみると,これがとっても使いやすくって面白いんです。
タイムスケジュールが立てられるので,1日の計画が,とても立てやすくなっています。個人的には,月間カレンダーの記入欄やノートが「方眼罫」なのがヒットで,予定をいっぱい書き込みやすい手帳です。
ついでに8色の色鉛筆や,4色の水性ボールペンなんかを買って,カラフルに手帳を彩りました。
そして,予定が空いてる日を色鉛筆で囲って,「試験まであと何日,自由な日があるのかな?」って確認してみました。
すると,そんな日は何日もないことに気づきました。;_;
なんか,まだまだいっぱいある,と思っていた試験日までの時間,じつはもうあまり残ってませんでした。
なので,合間を縫ってYouTubeをアップすることを,私の応用情報技術者試験の試験対策にしようかな,って考えてます。^^;
まだ,1ヶ月ある,といっても,1ヶ月まるまる自由に使える人は,ほとんどいないんじゃないかと思います。
土日や祝日は,今週末の3連休も含めてあと10日ありますが,全部自由ということもないんじゃないかと思います。
ちょっと,残り時間を数えてみましょう。
そしてその少なさを実感して,「残りの時間でできること」を考えてみましょう。
個人的には,残り1ヶ月になったら,ひたすら過去問演習というのが,定番のパターンです。そして,「試験に出てくる」弱点を,重点的につぶしていきます。
ゴールから逆算して,必要なことだけやっていく,という姿勢が肝心です。
あとちょうど1ヶ月です。
実際に,残りどれだけの時間勉強に使えるか,考えてみましょう。
そして,その少なさを感じつつ焦って勉強する,というのも前に進む原動力になると思います。
といっても,一度にできることは一つだけです。
あわてず,できることをしっかりやっていきましょう。