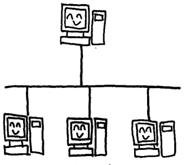上から目線で考える
昨日のブログのコメント欄で,エンバグさんが,文章を書くとき,上から目線で書く,という話をされていました。
確かに,試験の答案を書くときには,「上から目線」で断定的に書くことは大切です。
そしてそれは,ただ「書く」というときだけでなく,試験に臨む考え方としても大切なんじゃないかと感じています。
私の今までの経験では,情報処理技術者試験に連続で何個も合格する人は正直,上から目線で偉そうな人が多いです。
別に,試験に受かったから傲慢になった,というわけではなく,そういう人は基本,受かる前から自信たっぷりです。
他の人のことはあんまり言えませんが,「全区分制覇する」というのを,憧れではなくって,「2015年には全部取ってます」ぐらいの予定で言う人は,たまにつまづくことはあっても,大体受かります。
試験を受けにいく時には,「自分は今回の試験問題を解けるんだろうか」というよりも,「今回の試験問題,出来はどうかな?」と,試験問題を評価しにいくぐらいの姿勢でいる人は,まず受かると思います。
特に,システム監査試験は,この「上から目線」は重要です。
午後1などは,問題文を見てケチを入れていくわけですし,論文も,なるべく上から目線で書いた方が貫禄が出ます。
逆に,「控えめないい人」は,受かりにくいように感じています。
特に,「自分なんか,合格なんてとんでもない」「もっと努力しないと,自分なんてとてもとても」などといってる人は,その言葉通り,合格しない傾向はあります。
たまに,論文試験などで,「自分がプロジェクトマネージャって書くのはおこがましいので,サブリーダーって書きました」って言う人がいます。
この心構えでプロジェクトマネージャの論文を書いたら,間違いなく落ちます。
基本的に,論文試験がある区分は,「オレは会社の命運を担うリーダーだぜ」ぐらいのセルフイメージで書くとちょうどいいと思います。
ホントにベストなのは,試験に対して傲慢になるのでもなく,卑屈になるのでもない,中立な状態です。
ただ,試験に対しては,必要以上に卑屈になる人が多いので,意識して傲慢に,上から目線で考えるようにするぐらいでバランスがとれます。
なるべく,「上から目線」を意識して,試験問題を解いて,答案を書いてみましょう。