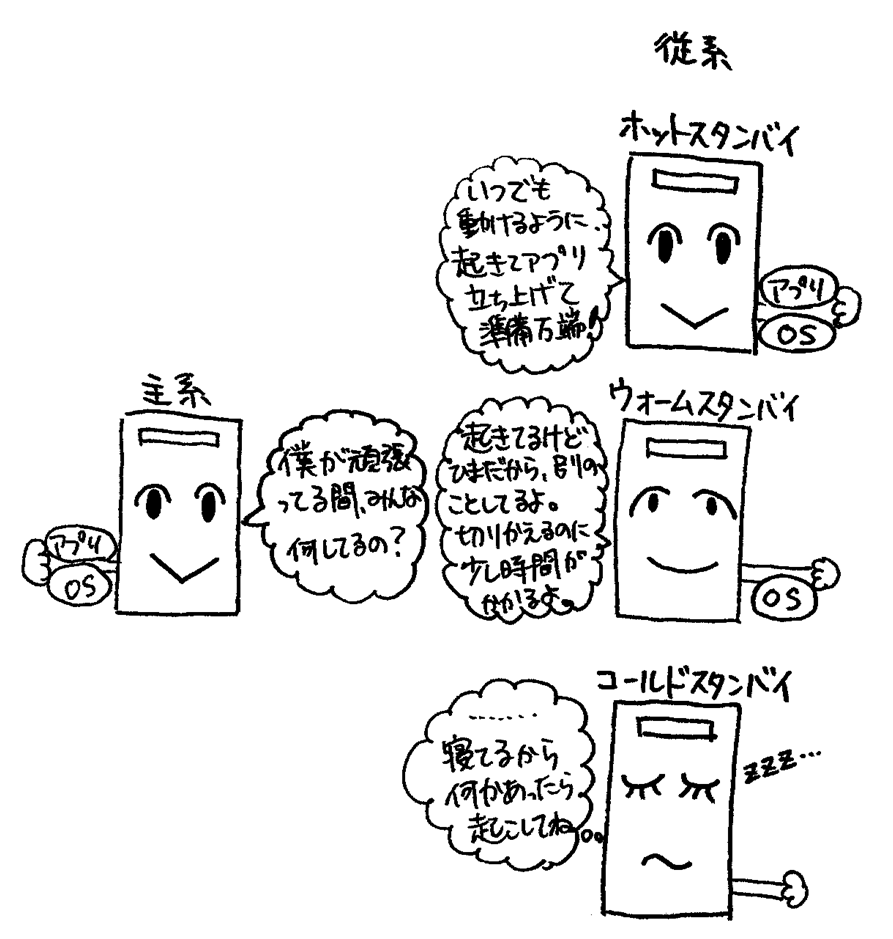試験時の緊急時対応手順を知っておく
わく☆すた,美月です。
まずは事務連絡です。
ホームページで案内させていただいていた,「10月12日から14日にわく☆すたでは通常業務ができない」旨,取り消させていただきます。
本来,今日から出張の予定だったのですが,幸か不幸か,それがなくなりました。私が東京におりますので,試験前ですし通常どおり対応させていただきます。
ですので,添削サービスをお申込みの方で,「間に合わないかなぁ」と感じられていた方は,14日ぐらいまでに到着すればなんとか対応できますので,よろしかったらご活用ください。
商品のご注文も,試験前の駆け込みでもOKです。
試験まであと5日,かなり迫ってきました。
この時期,試験を受け慣れている人はいいですが,そうでないと,緊急事態に遭遇したとき,あわててしまうかもしれません。
ということで,私やまわりが経験した,緊急事態と,その対応方法を紹介したいと思います。
まず,体調編。
試験日に,頭が痛かったりおなかが痛かったり,急に体調が悪くなることがあります。
情報処理技術者試験は来年もあるので,深刻な体の異変なら,やめて病院に行った方がいいと思います。でも,「よくある痛み」とか,対処できそうだったら,痛み止めを飲んで受験するのもありだと思います。
私も一度,おなかの激痛に襲われたことがあります。
このときには,カバンの中に忍ばせておいた頭痛薬で,なんとか最後まで受け切りました。論文試験なので,途中ちょっときつかったですが,痛みがなくなったので最後まで論文を書ききることができました。
あと,調子が悪くて,トイレが近いときは,情報処理技術者試験は途中退出が可能です。
試験官の人がついてきて,ちょっと恥ずかしいのですが,それさえ目をつぶれば,何度でも行くことはできます。これは気が楽です。
簿記試験の時には,それができず,最後かなりつらかったのを覚えています。
その点,体調が悪くてトイレに行きたいときには,情報処理技術者試験は安心です。
次に,忘れ物編
試験日に忘れるとどうしようもないのは,「受験票」です。これだけは,何が何でも忘れないようにしましょう。
写真も必要ですが,これは忘れたら,近くの証明写真が取れるところに駆け込んでください。ベストは,今頃に準備して,あらかじめ貼っておくことですが,忘れたらかけこめばなんとかなります。
昔は,証明写真が撮れる場所を探すのに苦労していましたが,今は「証明写真MAP」などもありますし,近所をGoogleマップで検索しても見つけることができます。
筆記用具は忘れたら,近くのコンビニや文房具屋で買いましょう。
私は一度,筆箱をまとめて忘れたことがあります。^^;
あわてて,近所のコンビニで,「削ってある鉛筆」と鉛筆削り,消しゴムを買いました。定規もあれば,時々便利です。
その他,イレギュラー対応編
試験会場が寒すぎたり,暑すぎたりすることって結構あります。
寒いときに備えて,何か布が一枚よけいにあると便利です。私は最近は,ひざかけにも上着にもなる,ボタン付きストールを愛用しています。
暑いときに備えて,半袖のTシャツを下に着ていって,暑かったら脱ぐ,というのもおすすめです。
あと,10月って,「試験日に台風が来る」ことって,意外とあります。
これは,前日から天気予報などをチェックしておいて,危ない場合には前日移動したり,迂回経路を調べておいたりするといいと思います。
私の経験だと,関東近辺は武蔵野線とか京葉線などの古くからある路線は,結構簡単に止まるので,つくばエクスプレスとか大江戸線とか,比較的新しくできた路線を使った経路を考えておくのもおすすめです。
せっかく今まで勉強してきたことを,試験の内容以前のところで無駄にするのももったいないですよね。
できるかぎり緊急時の対応手順を考えておいて,当日落ち着いて試験に臨みましょう。