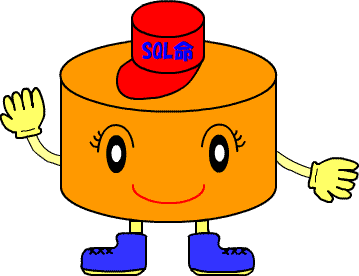わく☆すた,美月です。
気がついたら,今日で8月も終わりですね。
子供の頃には,明日から始業式~,とあわてて宿題をやっていたのを思い出します。
私は,一気に仕上げるのは得意だったのですが,毎日コツコツとやるのは苦手で,絵日記など,積み重ねが必要なものに手こずっていました。新聞の天気予報とかチェックしながら,無理矢理天気を埋めていったのを覚えています。^^;
最近は,ネットがあるから,そのあたりは楽そうですね。
ただ,改めて振り返ってみて,小学校とか中学校の宿題は,「毎日コツコツと積み重ねる」練習をするものだったんだな,とすごく感じます。
勉強って,1日すごく頑張ってもあんまり身につきません。積み重ねて少しずつ,というのは,実力をアップさせるための王道なんだな,というのは,いろいろ失敗してきて,すごく感じます。
私は,一夜漬けが得意だったので,テストの前には一気に暗記して,いい点を取る,というのをよくやっていました。でも,それだと,その場でいい点は取れるのですが,毎回やり直しになってしまって,あんまり効率は良くありません。定期テストはいい点が取れても,一夜漬けの効かない実力テストや模擬試験では通用しませんでしたし。
そこで,学校の授業の予習復習をちゃんとやったり,毎日少しずつでも勉強を続けていると,そのうち実力は身についていきました。情報処理技術者試験も,一夜漬けで取ったときの二種(今の基本情報技術者)の内容はほとんど忘れてしまいましたが,半年かけてじっくり勉強した一種(今の応用情報技術者)の内容は身についている感じがします。
情報処理技術者試験だと,応用情報技術者試験とかネットワークスペシャリストとか,身につける知識の量が多くて積み重ねでの理解が必要な種目は,一夜漬けはあんまり効かないので,コツコツ勉強する必要はあると思います。基本情報技術者とかは,IT関連の業務をやっていれば,一夜漬けで知識を身につければ取れるかもしれませんが,それだとより高度な試験区分の時に苦労すると思います。
業務が試験区分と一致している人は,業務自体が日々の勉強と連動していますので,あまり勉強しなくても受かるかもしれません。ただ,それでも,論文の書き方とか問題の解き方などは,ある程度練習して身につける必要はあると思います。
今からだとまだ1ヶ月半あるので,これから毎日コツコツやれば,なんとか間に合う,ぐらいの時期です。
そろそろ勉強を始めよう,と思っている方は,キリもいいので,9月からしっかり勉強していきましょう。