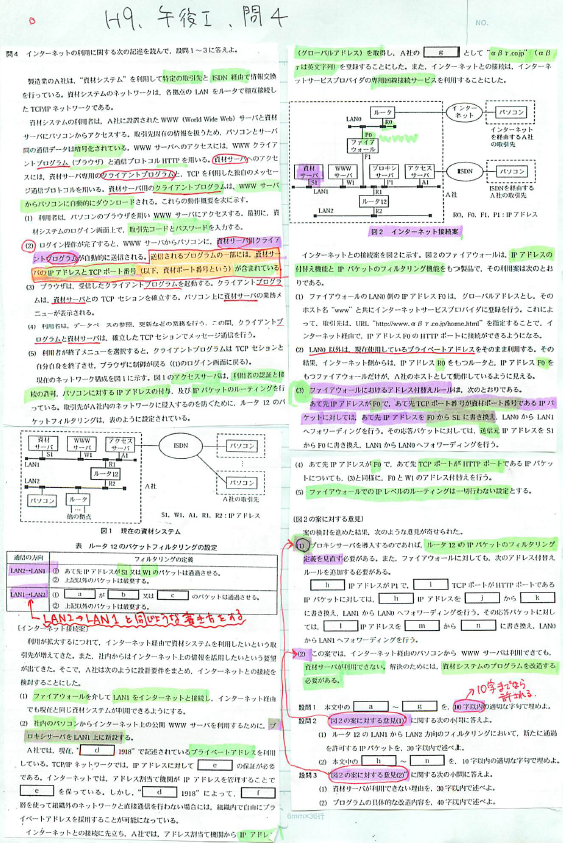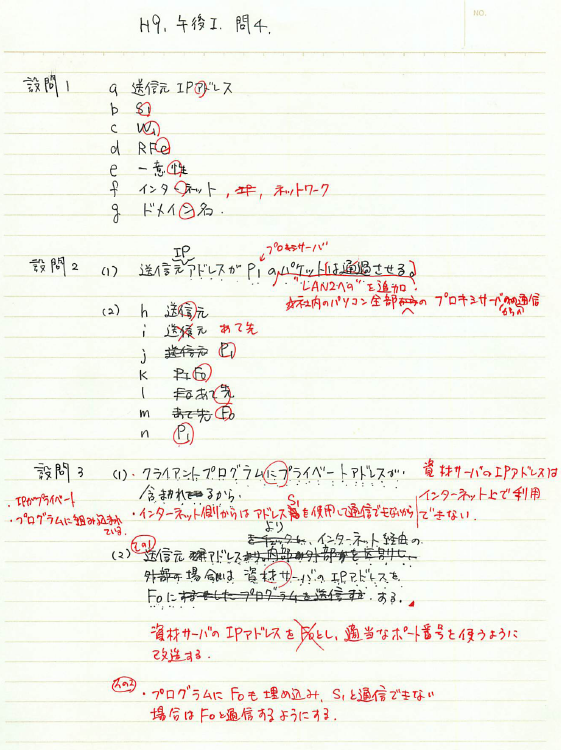試験には「応用編」まではいらない
わく☆すた,美月です。
先日,ネットワークスペシャリスト受験生の方から,「マスタリングTCP/IP,入門編は読み終わったので応用編読んでるんですが,難しくてなかなか頭に入りません。。。」という話を聞きました。それだったら,入門編を読み返して理解を深めた方がいいよ,という話をしたのですが,本音としては,ネットワークスペシャリスト試験を受けるのに「応用編」はいらないかな,って思ってます。
以前から,「ネットワークスペシャリスト試験のバイブル」など,このブログでは何度も紹介している本に,「マスタリングTCP/IP 入門編 第4版」があります。
私自身,この本にすごく助けられたと感じているので何度も紹介しているのですが,ここで紹介しているマスタリングTCP/IPは,あくまで「入門編」です。
このシリーズには,他にも応用的な「マスタリングTCP/IP 応用編」や,各技術を詳細に解説した「マスタリングTCP/IP SSL/TLS編」や「マスタリングTCP/IP IPsec編」があります。それぞれに,とってもいい本だとは思いますし,私も持っていて調べる時にはよく使ってます。
ただ,実は,ネットワークスペシャリスト合格レベルには,応用編までは必要ありません。入門編+αで十分合格できます。
ネットワークスペシャリスト試験は,確かにスペシャリストのための試験なのですが,ネットワークの専門家として生きていくことを考えると,入門の資格になります。その他の高度区分も全部一緒で,ITスキル標準で言うと,7段階あるレベルのうちの真ん中,レベル4です。試験で測れるのはこのレベルまで,ということだったと思いますが,最高レベルの認定資格というわけではありません。
ですので,応用的なことをいっぱい知っているということではなく,基礎をきちんと理解できているか,ベースとしての知識が身についているかについて問われます。もちろん,応用的なことも知っておくに越したことはないと思いますが,試験ではそこまでは要求されていません。基礎を固めて,典型的な事例の問題を読んで適切な解決策が思いつくようになるぐらいのレベルで合格できます。
なんとなく,「スペシャリスト」などという名前がついているので,ものすごく難しそうなことを問われそうな気がするのですが,実際やってみると,基礎がかたまって理解が進むと結構解けるものです。試験ではあまり重箱の隅をつつくような事例は出てこず,どこの会社でもありそうな典型的な事例が出てくるので,何でも解決できるスーパーマンである必要はありません。
ですので,応用的なことをあれこれ手を広げすぎるよりは,基礎を固めて,その上で過去問演習をしてみた方が,合格には近くなると思います。いたずらに難しいことをいっぱい勉強する必要は,実は全然ありません。
今の時期だと,試験に必要な基礎をかためておいて,過去問演習などに備えるというぐらいでも,試験には十分間に合います。
難しいことにいろいろ手を広げて中途半端になるよりも,基礎がしっかり理解できている方がその後の進歩も早いです。応用編に手を出す前に,目の前の入門編の内容を確実にしていきましょう。