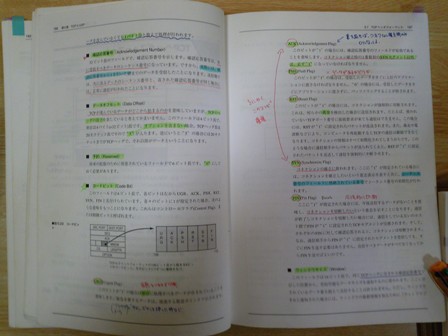しないこと
わく☆すた,けんけんです。
今朝,6,7月に開催する公開セミナー会場の予約に出かけてきました。
詳細は,Web上に掲載しますので,決まりましたらこのブログでも紹介しますね。
さて,会場までの往復の電車の中で,昨日美月さんが読んでいた『スローライフのために「しないこと」』を自分も読んでいました。今の風潮に対して逆行するような「スローライフ」の考えが書いてありますが,ある意味こっちの方がいいかもと思える本です。
ここで,ふと「情報所技術者試験を受けることは,もしかして,しなくてもいいこと?」とか思ってしまいました。
これは人によると思いますけど,試験会場に行って欠席の机を見るたび,「前後左右いなくてラッキー」と思う反面,「仕事になっちゃったのかな。」とか,「逃亡したかな」などと,いろいろ思いをめぐらしています。
試験勉強って,時間労力を結構使うものです。それがもしも,その人にとって,しなくてもいいことだったとしたら・・・
著者の辻信一さんは,「する」の反対語を「ある」と定義しています。英語で言えば,DoとBeですよね。しないことでできた時間で,他のことをするのではなく,“いること” “存在していること”が軽視されれいるのではないかと訴えます。
本を読んでいて,反省と言うか思い当たることばかりで,自分も忙しくしているのが美学と思って行動していたなぁと,電車の中でうなずきながら,しみじみと思いをはせていました。
まだ2/3あたりを読み終えたばかりなので,読み切って思考を深めてゆきたいと思います。