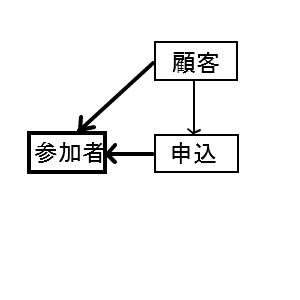わく☆すた,美月です。
昨日,「一生太らない体のつくり方―成長ホルモンが脂肪を燃やす!」という本を読んで,ダイエットの基本的な考え方,理論について学んでいました。
基本的な考え方としては,筋肉があることで,基礎代謝が上がって太りにくい体ができる,という話です。科学的にもとても納得できる考え方でした。今までの自分のダイエット法が,かなり間違ってたなぁ,といろいろ反省することも多かったです。今後は,週2回ぐらい,筋トレをして,筋肉を増やしていこうと思ってます。
その本の中で,「下手なダイエットは,かえって太りやすくなる」という話がありました。
食事制限などで極端なダイエットをして体重を落とすと,一緒に筋肉が落ちてしまいます。そうすると,基礎代謝が下がって,「太りやすい体」になってしまう,という理論です。こういうダイエットだと,全然やらないときよりも筋肉が落ちて,リバウンドして元の体重以上になってしまう危険が大きいそうです。
「なるほど!」と,とっても納得しました。
。。。そこで,ふと疑問がわきました。
危険なダイエットと同じく,「危険な勉強」というのもあるのではないかと。
筋肉を落とすダイエットと同じように,やるとマイナスになる勉強もあるのではないかと気がつきました。
勉強っていうのは,一般的に「やればやるほどいい」と信じられているように感じます。
でも,実は,「そんな勉強だったら,やらない方がいい」と思える勉強も,実は結構あります。勉強して効果が上がらない場合には,「やり方がまずい」ということも疑ってみる必要があると思います。
私が考える,やるとマイナスになる勉強は,次の3つです。
1.イヤなことを苦しみながらやり続ける
2.間違った知識や理解を身につける
3.段階を飛び越して,今のスキルでは学べないことをやる
個人的に,一番やめて欲しいと思っているのは,1のイヤイヤやる勉強です。
これは,勉強をやり始めるときがおっくうでイヤだったり,なんとなく続かない,とかそういうレベルの話ではありません。そう言うのは,結構誰でもイヤなものですし,やり始めてからの作業が苦痛でなかったら問題はないと思います。
やって問題なのは,「やっていてずっと苦痛な勉強」です。
例えば,机に向かって,用語をひたすら暗記し続ける,というのは,逆効果の部分が大きい勉強法です。丸暗記は,短期的に効果があるように見えても,実はあんまり身になりません。そして,作業が苦痛なので,勉強自体がイヤになる可能性が高いのです。
イヤなことというのは,人間忘れるようにできています。それは本能的な部分なので,頑張って無理矢理覚えようとすればするほど忘れます。暗記物は,ちょっとした時間に気軽にやるのがコツです。何より,情報処理技術者試験の勉強では,単なる暗記の部分はなるべく少なくして,理解して覚えるのがおすすめです。
なにより,イヤな勉強は,「リバウンド」が起こります。
無理矢理イヤなことを我慢して勉強すると,あまり効果が出ないため,試験に合格する可能性は低いです。そこで,「あんなにイヤなことやったのに,結果が出なかった。もう二度とやらない!」となってしまって,もう一度挑戦する意欲は,完全に削がれてしまうことになります。
こうなると,ひどい場合は,他の情報処理技術者試験を受験する人にも当たり散らして,「そんな勉強するだけムダ」みたいになりがちになると思います。
ですので,「やり続けるのがイヤ」な勉強は,極力しないようにしてください。
2番目の間違った知識というのは,そんなに多く起こることではないですが,あると大変なものです。
例えば,正規化などの関係データベースの理論は,頭がまっさらだと良く頭に入ります。ですので,新人研修で正規化を教えるのは,実は結構簡単です。
でも,階層型データベースが頭に入っている人に,正規化を教えるのは結構大変だったりします。既存の知識が邪魔をして,新しい知識が受け入れられなくなってしまうパターンです。
データベーススペシャリスト研修などでは,正規化理論は「実務と違う」と文句を言って,全く受け付けない人もいます。
既存の古い知識が,新しい学習を邪魔することもあるのです。
あと,間違いだらけの下手な参考書などで勉強すると,次にちゃんとした正しい知識が入りにくいという危険はあります。あんまり数は多くないですが,データベースやネットワークではたまにありますので,ご注意ください。
最後の,「段階の飛び越し」は,勉強しても学べないパターンの典型例です。
初心者が,いきなりスペシャリスト系の試験の挑戦,というのは無理があるのは誰でも分かると思います。でも,年齢がある程度上がってくると,そういう無茶をやろうとする人は,意外に多いです。
あと,情報処理技術者試験は,基本的に,「高校程度の基礎学力」が求められますので,これがない場合にも勉強が進みません。高校レベルの国語や数学は,ちゃんとマスターしておかないと,問題文の読解など,変な部分で足を引っ張られることがあります。
段階を飛び越して勉強すると,勉強内容を理解できないばかりか,間違って解釈してしまう怖れが大きいです。何より,勉強していてつらいとも思いますので,効果はあまり期待できません。ですので,順を追って,ひとつひとつステップアップしていくことをおすすめします。
以前,「「勉強した気」になると成績が下がる」でもお話しましたが,勉強は,やればいいというものでもありません。
基本的に,「イヤ」とか「苦痛」を感じるのは,「自分に合ってない」というサインですので,ちゃんと聞き分けて,別の方法を試した方が,効果が上がると思います。
正しいやり方,というよりは,なるべく「楽しいやり方」で勉強していきましょう。