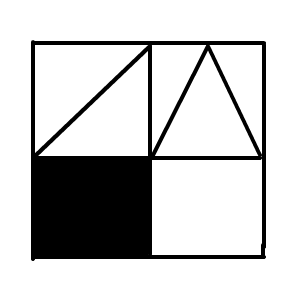応用情報技術者試験の解答例について
わく☆すた,美月です。
6/16に,応用情報技術者試験の午後問題の解答例が発表されました。
試験からもう2ヶ月経っているので,忘れている人も多いとは思いますが,できる限り確認しておくのはおすすめです。次にもう一度応用情報技術者試験を受ける人はもちろん,受かって高度試験を受ける際にも,基礎知識としてとても役立ちます。
ってことで,解答例を見ての感想です。
まずは,必須問題の2択 (問1 or 問2) です。
問1の経営戦略は,知識がなくても半分ぐらいは解けるとは思いますが,ちゃんと勉強しておかないと解けない部分も結構多いです。マーケット・セグメンテーションで,行動的変数・地理的変数という区分けがあることや,価格弾力性・シナジー効果・ブランドエクイティ・サンクコストなどの用語をある程度知っておく必要があることなど,前提知識は必要な問題でした。
あと,一番ポイントになるのは設問4で,B社で「健康補助食品・医薬部外品の取り扱いをしない理由」を聞いてる設問です。店舗コンセプト”豊かな食の提供”がポイントになるということを読み取って,ちゃんと文章で表現する必要があります。こういう「問題文をちゃんと読み込んで答えを出す」形式の問題は,ソフトウェア開発技術者試験にはあまりなかったのですが,高度系の試験だと定番です。この問を見る限り,選択で問1を取るなら,文章の読解力は必須だと思います。
問2のアルゴリズムは,応用情報技術者試験のアルゴリズムに必要な要素の記事でも述べましたが,難易度自体は易しいです。ただ,C,C++,Java寄りの考え方が必要なので,プログラミング経験が少ない人には難しく感じる人も多かったのではないかと考えています。
あと,ソフトウェア開発技術者試験と違う点としては,設問1と設問4で文章を書かせる問題が出ていて,文章の記述が増えたという印象です。文章問題は,「衝突って何?」ということを文章で表現するだけなので簡単なのですが,文章を書くのが苦手な人は戸惑ったのではないかと思います。
それ以外の問題は,10問中5問選択なので,軽く見ていきます。
問3の戦略立案・コンサルティングの問題は,文章が読めて書ければ,比較的簡単だったのではないかと思います。記号も多く,記述は問題文から探せばOKです。
問4は,設問2の方式B(非同期コピー)について,更新データのコピーが完了するのを待たずに次の処理に進めるので,トランザクションの処理時間に影響がないことを,表からちゃんと読み取る必要があります。数値計算も含め,知識よりも問題文の読み込みが大事な感じです。
問5は,DHCPの問題ですが,IPアドレスの割当方法を,ちゃんと知っておかないと解けないので,ちょっと敷居が高いです。DHCPオファーなどのDHCP設定のパケットは全部ブロードキャストなことを知っておくか,もしくは表2から読み取る必要があります。また,192.168.10.64/26で割り当てられるIPアドレスの範囲を,正確につかめないと,設問3は連続して間違えてしまいますので,ネットワークの知識はそれなりに高度なものが必要です。ただ,知識があれば,解答に迷うような問題はありませんでした。
問6は,複数のクエリを結合する集合演算子が初めて出てきました。
集合演算子には,UNION, UNION ALL, MINUS, INTERSECTの4種類がありますが,このうちのUNIONかUNION ALLのどちらになるか,が設問2(e)のポイントでした。UNIONだけだと,重複行が1行にまとめられてしまうことを知っているかどうかが問われているので,なにげに設問2(e)だけ,難易度は高いです。他はほぼ定番の問題だと思います。細かいことを言うと,設問1(a)の顧客番号は,点線の下線がないと×になります。
問7は,組込としては定番の問題でした。クロック制御タスクは,他のタスクより優先度を低く設定するので,他のタスクが実行可能状態になったら,クロック制御タスクは実行状態から実行可能状態に追いやられてしまいます。ってことで,タスクの状態遷移図を考慮して,クロック制御タスクが実行状態の場合には,他のタスクは待ち状態しか取りえない,ということを考える必要があります。勉強していない人には敷居は高いですが,ちゃんと問題文が理解できれば,全問正解できる問題です。
問8は,オブジェクト指向の問題です。ポリモルフィズム(多態性)がわかってないと考えづらい問題です。ただ,オブジェクト指向ばりばり,と見せかけておいて,最後の設問3の答えは,データベースの「デッドロック」なところに,ちょっとひねりを感じます。単にオブジェクト指向を知っておけば,というのではなく,この問題は「情報システム開発」全般を聞いてるんだぞ,という意志を感じます。
問9は,セキュリティのファイアウォールの問題です。ファイアウォールの設定自体は,定番の問題でした。ちょっと解答で悩んだのは,RADIUSの機能を聞いている,設問3(k)です。RADIUSサーバには,「利用の可否の決定(認証)」の機能と「認証の記録(アカウンティング)」の2つの機能があります。ここはひねって,アカウンティングの話かなぁ,とも考えたのですが,解答例を見ると単純に,「認証の一元管理」で良さそうです。
問9のプロジェクトマネジメントの問題は,常識で考えれば解ける,というタイプの問題です。解答例も,「実際,現実ではそうするだろう」というものばかりなので,実務経験がそれなりにあれば,簡単だったのではないかと思います。逆に,学生にはきついかもしれません。
問11のITサービスマネジメントの問題は,ちょっと考える必要がある問題でした。出てくる「T社」と「U社」の関係をちゃんと把握して,それぞれの立場から問題を考える必要があります。設問1は,「T社」のメリットを答える問題です。設問2は,「U社」の立場からの防御を記述します。運用管理,というより,「マネジメント」色の濃い問題です。とはいえ,ちゃんと会社どうしの関係を把握して,きちんと読み込めば,十分全問正解できる問題です。
問12の監査問題は,結構穴場というか,解答のぶれが少ない問題です。「監査の考え方がわかっていて」問題を読めば,問題文の中に解答や解答のヒントは書いてありますので,全問答えが正確に導けます。ちゃんと,監査の考え方,原則について勉強しておけば,今後も監査問題は解きやすい可能性が高いです。
ということで,ざっと解答例をみながら振り返っていきました。
やっぱり,応用情報技術者試験は,幅広いですね。
このあたりを踏まえた上で,午後問題の解答解説DVDをテクノロジ編(問2,4,5,6,8,9),その他編(それ以外)に分けて発売する予定です。