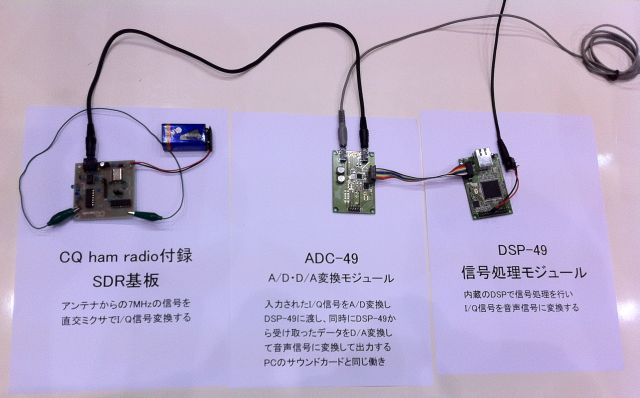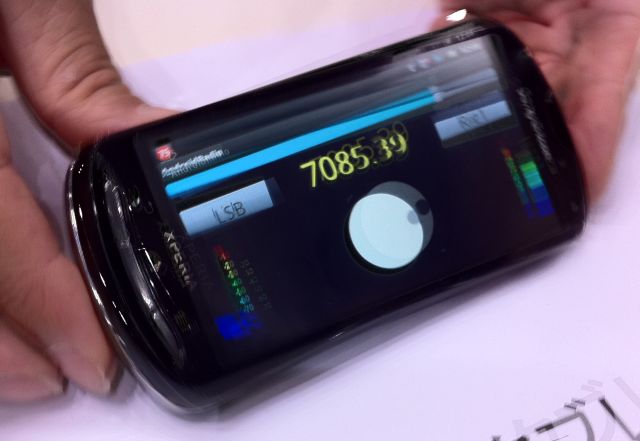こんな情報処理技術者試験があったらイヤだ
昨日,セミナー後の懇親会で盛り上がったネタに,「こんな情報処理技術者試験があったらイヤだ!」というのがありました。
その時出たネタ+後にいろいろ思いついたのを並べると,こんな感じです。
・試験を受けるのに抽選があって,当たらないと受けられない。
(東京マラソンみたいな感じ。受ける権利がプラチナチケット。)
・午前が終わったら速攻で採点されて,点数が足りないと午後椅子に座った時に「ブーッ!」っと鳴って受けられない。
・いすがなくって,立って試験を受ける。またはちゃぶ台で座って受験。
・午前の試験の成績でAクラスからFクラスまで分かれて,Aクラスはリクライニングソファにドリンクバー,Fクラスはちゃぶ台で受験。
・試験会場に屋根がない。雨が降ると濡れないようにするのが大変。
・受験するのに年齢制限(下限だけじゃなく上限)がある。40歳以上お断りとか。
・受験申し込みのときに書類選考がある。志望の動機とか,400字ぐらいのエッセイを書かされるとか。
・1つの面(試験)をクリアしないと次にいけない。ITパスポート(レベル1)に合格しないと基本情報技術者(レベル2)を受けられないとか。
それだけじゃなく,ペナルティ(3回落ちるとか)があるとレベル1に戻る。
・チーム対抗で,3人1組で受ける。全員で協力して解くんだけど,1人でも基準点に達しないと不合格。
・試験官が寝てる。または,気がついたら試験官がいなくなってる。
・「始めてください」のかけ声があっても,まだ問題用紙が配られてない。
・試験問題が袋とじ。うまく破かないと問題が破れる。
・試験終了時刻に誰も残ってない。試験官さえも。
・猫とかイグアナとか,人間以外の人も試験を受けている。
・論文試験のアンケートで,趣味とか血液型とか,理想の異性のタイプを聞かれる。
・試験問題の事例が残酷すぎて泣けてくる。
・O主任とU君の,プライベートな人間関係について問題文に書かれている。
・試験問題が手書きで,字が汚くて読めない。
・論文試験の採点官が自分の上司。それで,「お前こんなことやってないだろ」と突っ込まれる。
・実技試験で,実際に激しく火を噴いてるプロジェクトに送り込まれる。
・IPAの取引先に父親がいるなど,コネがあると合格しやすい。
・試験の開始から終了までの間に,5km移動しなければならない。
・お昼ご飯は給食。でも,全部食べないと昼からの試験が受けられない。
。。。などなど,いろいろありますね。
そう考えると,申し込めばみんな受験できる,自由な情報処理技術者試験が,素晴らしく感じられるようになりました。
皆さんも,何か面白いネタありましたら,教えてくださいね。^^