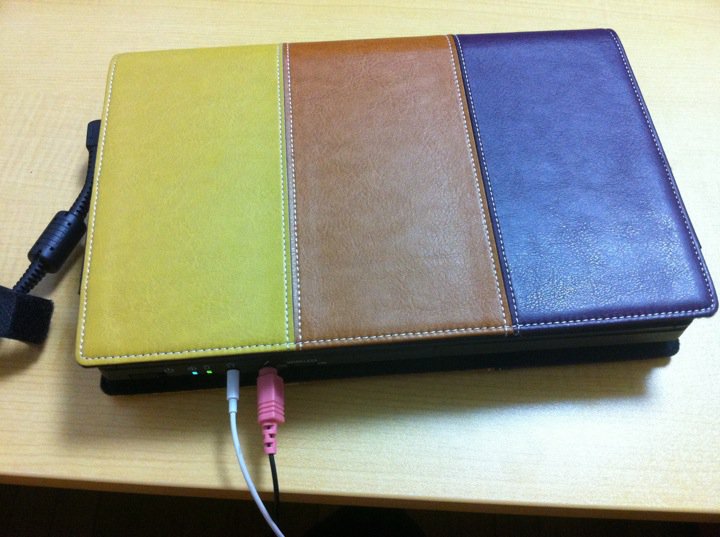情報処理技術者試験の試験地について
アキバのヨドバシカメラにいったら,情報処理技術者試験の願書が置いてありました。
一度回収されて,先週はなかったのですが,無事,新しいものと取り替えられたようです。
比べてみた感じとしては,以前「早めに受験種目を決めていきましょう」で書いたとおり,13ページの,試験地での実施試験区分が変わっているぐらいだと思います。
試験地といえば,特に巻頭では,試験地の会場というのは,その名前がついている市町村とは限りません。
ちゃんと,「案内書・願書」の13ページの注意事項にも,
(2)試験地は,周辺の市町村を含みます。藤沢試験地は,小田原地区を含みます。
(3)各試験地で収容能力を超えた場合には,それぞれ隣接の試験地での受験となります。
なお,事前に通知はいたしません。
とあります。
前回の特別試験の時には特に,遠方の会場に回された人も多かったようですが,普段から,近くの会場とは限らないのです。
私自身,試験会場「柏」でよく受験していましたが,隣接の,我孫子市や松戸市のことの方が多かった気がします。
八王子,横浜・川崎,藤沢,厚木も,そんな感じのようです。
埼玉,千葉などは,それぞれ,さいたま市,千葉市の近郊がメインのようです。
昔私は,埼玉県の所沢市で会社の寮に住んでいたのですが,埼玉県で近くになると思って埼玉で申し込むと,大宮の会場に飛ばされた,という先輩の話を聞いて,東京の試験地で申し込みました。
情報処理技術者試験は,同じ試験区分でも,様々な受験会場があります。
特に,東京は,「情報処理技術者試験事業 民間競争入札実施要項(案)(PDF形式)」の24ページに載っている会場から見るとおり,いろんな会場に分散されているようです。
ある程度郵便番号は勘案されるでしょうか,基本,どこの会場に割当てられるかは,運の要素が大きいと思います。
同じ住所から同じような時期に出していても,試験会場が異なることがほとんどですし。
今回から,「郵便番号を勘案して割り付けます」という記述がなくなりましたので,より,ランダム性は高くなるのかな,とは思います。
とはいえ,東京試験地で出せば,ほとんど23区内の会場には割り当てられます。
地方だと,選択肢が少ない分,逆に試験会場のブレは少なかったりします。
平成22年の「情報処理技術者試験事業の実績評価について(案)」によると,高松試験地の受験会場は1ヶ所(香川大学(教育学
部)もしくは英明高等学校),那覇試験地の受験会場は1~4ヶ所(沖縄大学とその他中学校など)のようです。
ですので,地方の方が,同じ会社や学校の知り合いと出会う確率は高くなります。
それを狙って,旅行を兼ねて集団で試験を受けに行く人も,結構いるみたいです。
私も一度だけ遠征(熊本)して受験したことがあるのですが,なんか旅行気分で調子が狂って,試験に集中できなかったのでやめました。(ちなみに,その時受けた試験(システム監査)は落ちました。)
コントロールできるところはコントロールして,できないところは運を天に任せる,というのは大切だと思います。
試験地については,早めの方がいい場所になる可能性は高いとは思いますが,万全ではありません。
申し込んだ後は試験会場については手放して,10月の受験票到着を待ちましょう。