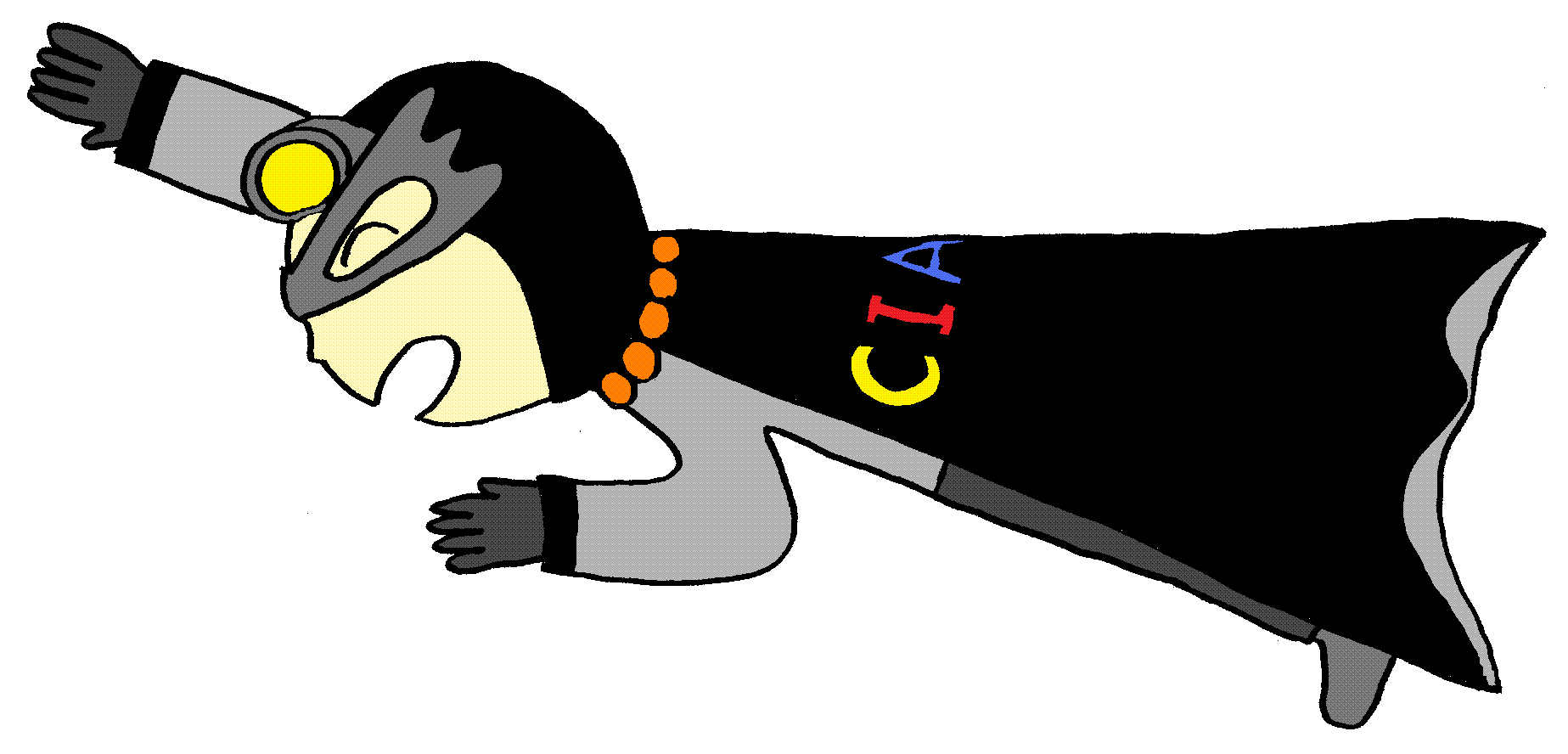わく☆すた,美月です。
私は,大人になった今になっても,マンガもゲームも大好きです。^^
子どもの頃は,まわりの大人は別にマンガなんて読んでなかったので,大人になったら興味がなくなるのかなぁ,と思っていたのですが,やっぱり今でも面白く感じます。ゲームだって,どんどん進化して面白くなっていますし,感動的なゲームは,今でも泣いてしまいます。
大人になったおかげで,コミック全巻一気買いしたり,欲しいゲームのためにゲーム機も一緒に買えるようになった分,子どもの頃より幸せかな,とも思います。^^;
マンガやゲームは,単なる趣味かな,と思う反面,実際に役立っていたり,結構人生に大きな影響を与えることも多いんだなぁ,というのを,最近改めて感じました。
以前,「プログラミングは遊び ~おすすめ本 C言語編~」でも書きましたが,私がコンピュータに触ったきっかけは,「こんにちはマイコン」というマンガでした。
ゲームを作りたくってBASICを覚えたのですが,小学生のときに身につけたプログラミングの考え方は,今でも役立っています。マンガから楽しく入ったおかげか,プログラムを作る,というのはいまだにワクワクすることの一つです。
そこでもう一つ,私の人生に大きな影響を与えたマンガがあります。
私が小学生の頃,このブログでテーマになっている「勉強法」について興味をもったのも,マンガがきっかけでした。
それは,「とどろけ一番」というマンガで,30年前ぐらいにコロコロコミックに連載されていました。
当時小学生だった私は,これを読んで夢中になっていました。
「試験」を通じてバトルを行う,今読み返すとすごく笑ってしまうマンガなんですが。^^;
試験でバトルして日米決戦したり,ロボットと対戦したり,命をかけたとっても熱い戦いが繰り広げられます。
実は,影響されやすい小学生だった私は,マンガに出てくる必殺技を使って,学校のテストを受けることに,密かに燃えていました。
とどろけ一番の主人公,轟一番には,「二枚返し」という,両手に鉛筆を持って答案を書く,という必殺技があります。
私は,実は,小学生のときにこれをいっぱい練習したので,左手でも字が書けるんです。^^;
この必殺技が今までの人生で役立ったのは,論文試験で最後に右手が痛くなったときに,書ききるために左手を使った時ぐらいですが,普通に使える技も,実はいっぱい学びました。
鉛筆を2本持って一気に書く,というのは現実的ではないのですが,「右手に鉛筆,左手に消しゴム」というのは,時間を節約するときには普通に役立ちます。左手で消しゴムを使えるようになっていれば,ちょこちょこっと誤字を消しながら,鉛筆を持ち替えずに書き進めることができます。時間との戦いの時には,意外と役立つテクニックです。
あと,今でも試験を受けるときに,気をつかってやってるのは,「短めの長さの鉛筆を用意する」ことと,「消しゴムは必ず2つ以上用意する」ことです。
試験会場で使う鉛筆は,長すぎると実は使いにくいし,手が疲れてきます。とどろけ一番の必勝勉強法では,「鉛筆の長さは,11cmが最高!」と書いてあったので,いまだにこれは,守り続けています。長い鉛筆は,普段の生活で使って,長さが11cmぐらいになったらとっておいて,それを試験会場に持っていきます。大人の男の人には,もうちょっと長い方がいいかもしれませんが,私の手は小学生とあまり変わりませんので,今でも11cmぐらいが最高です。
自分が「最高」だと思っている長さの鉛筆がずらっと揃っていると,それだけで,「勝った」という気にもなってくるものです。\(^^;ヲイ
消しゴムの方は,2個用意するのは,落としても慌てないためです。私は結構そそっかしいので,試験中に何度か,消しゴムを落としたことはあります。その時,予備があると,慌てないで試験に集中することができます。たいていは試験管の人が拾ってくれるのですが,2つあるとやっぱり,気分は楽です。
そんな感じで,マンガにもいろいろ,役立つ知識が詰まってます。
息抜きに,でもちょっぴり役立つことを期待して,遊んでみるのもおすすめです。