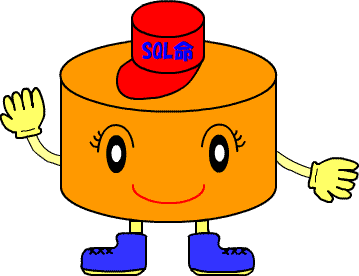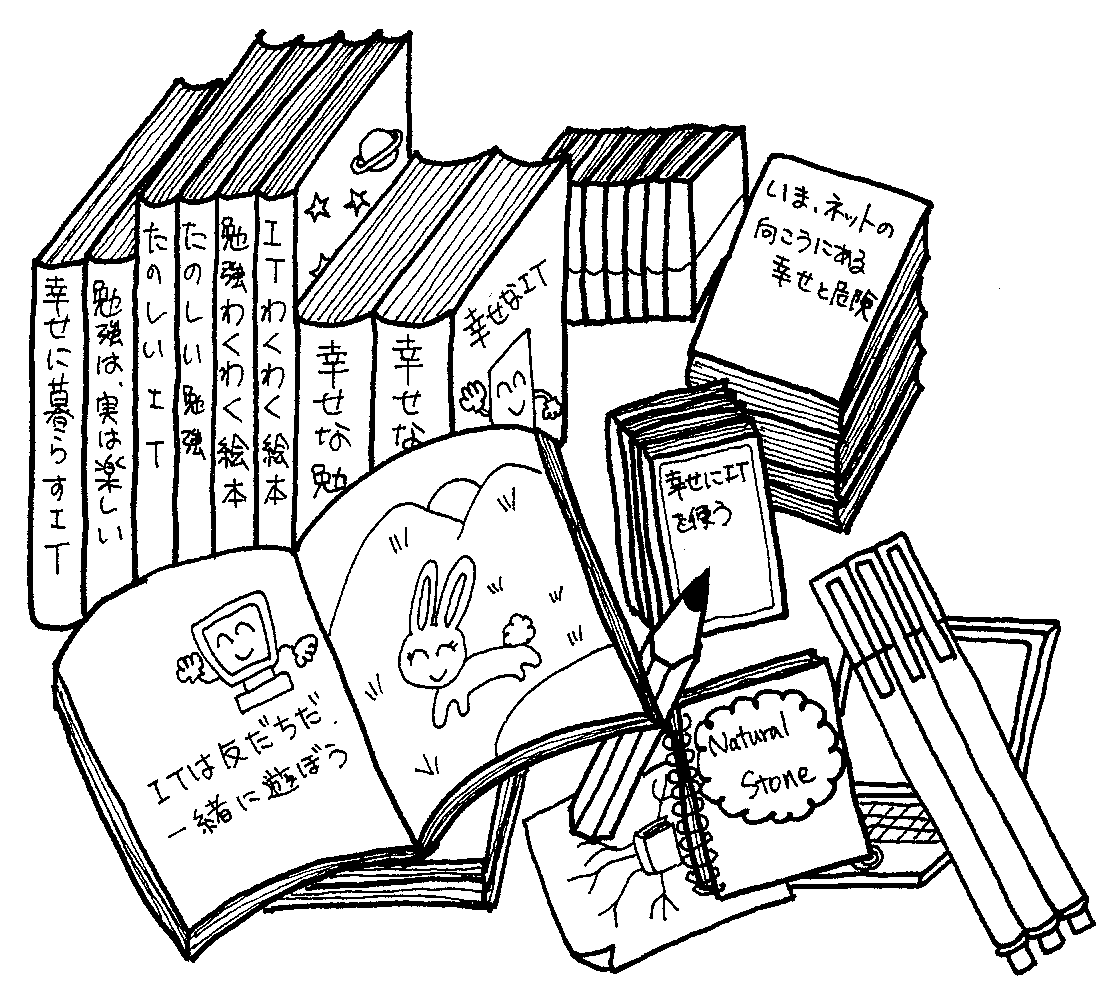春に向けて勉強をスタートしましょう
わく☆すた,美月です。
試験が終わってちょうど1ヶ月,基本情報技術者の合格発表も終わりましたし,そろそろ春に向けて勉強をスタートする時期です。
11月にスタートを切っておくと,いろんな意味で有利です。特に,付け焼き刃ではない,本質的な実力アップには,どんな内容でも,大体3ヶ月ぐらいはかかりますので,今の時期から長期計画で,いろいろ始めることをおすすめします。特に,国語力とか,アルゴリズムとか,データベース設計とか,ネットワークをきちんと理解するとか,そういったことに時間をかけると,試験だけでなく,実務や普段の生活,いろんなところで役立ちます。
ということで,わく☆すたでは,公開セミナーについて,日程を確定して募集を開始しました。
今回行う予定なのは,次の3つです。
1.データベーススペシャリスト対策3回セミナー
2.情報セキュリティスペシャリスト対策3回セミナー
3.分野別徹底学習 基礎理論・アルゴリズム
かねてより要望の多かった,スペシャリスト系の続き講座を,今回から開始いたします。データベーススペシャリストと情報セキュリティスペシャリストについて,大体月1回程度の学習で,体系的な学習を行います。
ビデオ撮影も合わせて行い,後日DVD教材として発売いたします。ですので,途中の回で都合が悪い方,遠方で来られない方も大丈夫です。
応用情報技術者(AP)試験向けには,複数回の講座というのは行いません。
APは,午後の選択において,人によって学ぶ内容が大きく異なるため,統一した講座が行えないことと,「これさえやれば合格」的な講座を行うと,かなりの回数になってしまうからです。
ですので,分野別に,1つ1つ行っていく予定です。
今回は,一番苦手な人が多そうな,「アルゴリズム(プログラミング)」を中心に据えて,1日集中講座を行います。今後,様子を見ながら,別の分野も増やしていく予定ではあります。
分野別講座も,DVD教材として販売する予定です。
もしご都合が合うようで,来てみたいと感じられれば,ぜひご参加ください。
そうでない方も,この時期に,参考書を買うなど,行動を開始してみるのをおすすめします。うちの「合格への道標」では,勉強のやり方に加えて,シークレットページで,おすすめ教材,おすすめでない参考書などを紹介しています。今期より,おすすめ,おすすめでない参考書以外の参考書の講評も追加しています。
ちょっと,今日は宣伝が多いですね。^^;
いずれにしても,試験の後は,1ヶ月ぐらい休んだ後,早めに次の試験に向けてスタートする,という年間サイクルを作って,毎回受け続ける,というのが,高度区分の資格をいっぱいとるためのコツです。
そろそろ受験区分を決定して,なんでもいいのではじめてみてください。