
「わく☆すた公開セミナー 応用情報技術者午後対策 3回コース」1回目を開催いたしました
本日,わく☆すた公開セミナー「応用情報技術者午後対策 3回コース」の1回目が無事終了しました。
ご参加いただいた,皆様ありがとうございました。
いつものオープニング板書は,弊社facebookページに公開しています。
今回から,応用情報技術者試験対策は,午後に特化して行っております。
今日改めて感じたのは,「記述式で求められたことを書く」ことの難しさと大切さです。

本日,わく☆すた公開セミナー「応用情報技術者午後対策 3回コース」の1回目が無事終了しました。
ご参加いただいた,皆様ありがとうございました。
いつものオープニング板書は,弊社facebookページに公開しています。
今回から,応用情報技術者試験対策は,午後に特化して行っております。
今日改めて感じたのは,「記述式で求められたことを書く」ことの難しさと大切さです。

来週,7月23日(月)より,「平成24年度秋期試験」の受験申込が始まります。
受験区分がすでに決まっている方は,なるべく早く申込を行うのがおすすめです。
個人的な感覚として,申し込み開始初日に「早速申し込みました!」という人は,合格率も高いように感じています。
あと,現実的なメリットとして,早く申し込んだ方が自宅近くの会場になる可能性が高いです。
基本的には,郵便番号を基準に最寄りの会場を割り当てるので,状況にもよりますが,最初の方に申し込むと,一番適切な会場に割り振られると思います。
また,各受験地で定員を超えた場合には,隣接の受験地に回される場合もあります。
そんなにめったに起こることではありませんが,去年の特別試験の時には,結構遠くの会場に回された人が多かったようです。
不測の事態に備えて,という観点からも,早めの申込は大切です。
そして,受験区分に迷われている方は,早めに受験区分を決めて申し込むことは重要です。
できれば,7月23日までには決めて,とりあえず申込をすませておくと安心です。
受験区分の選択基準としてはまず,情報処理技術者試験に関しては,「背伸びしない」「段階を踏む」ことをおすすめします。
いきなり高度区分を受けたり,レベルの高いものを受けようとすると,合格は遠のきます。
高度の午前1は,単なる足切りの機能しかないので,ぎりぎりでも突破したから大丈夫,というものでもありません。
「年齢が高いから」「今さら基本情報や応用情報なんて受けるのが恥ずかしいから」ということで高度区分を申込続けていると,かえって遠回りです。
段階を踏んで,基本情報技術者,応用情報技術者と受けてみる方が,結局は合格が早くなると思います。
高度区分の中では,ITストラテジストは,はじめての高度区分,はじめての論述系区分としてはあまりおすすめしません。
論述式の試験に受かったことがなく,論文自体がうまくかけないのに受けると,勉強がかなり大変になります。
システムアーキテクトかITサービスマネージャかで一度論述式試験に受かってから受けると,無理がありません。
もちろん,中小企業診断士など論述がある試験に受かっている場合は,いきなりITストラテジストでも受かる方は多いです。自分の状況に合わせて,段階を飛び越しても大丈夫かどうかは見極めてください。
それ以外の高度区分は,好きなものを受ければいいんじゃないかとは感じています。
普通は,自分の実務経験がある分野,専門分野を受けることが多いんじゃないかとは思います。
ただ,勉強することでスキルが身につくというのが,試験の大きな利点でもあるので,「実務経験がなくても,自分の進みたい方向」の試験を受けるのはおすすめです。
実際,ネットワークの仕事がやりたくて,実務はちょっと離れてるけどネットワークスペシャリストの勉強をして,合格して転職や配置換え,という人も大勢います。
あと,「春試験が目標だから,秋は受けるものがない」という方も,とりあえず受けることを検討してみるといいと思います。
例えば,春のエンベデッドシステムスペシャリストが目標の場合,システムアーキテクトやITストラテジストを組込系分野を選択して受けると,春にもつながります。
春のデータベーススペシャリストが目標の場合,システムアーキテクトの勉強をすると,データベース関連以外のシステム開発の知識が身について,問題選択の幅が広がります。
個人的には,情報処理技術者試験は,半年ごとに受けにいくこと自体が大切だと感じています。
受け続けるとそれが習慣になって,行くのが当たり前になります。その方が,「今回は受けに行こうか」など,いちいち悩む必要がなくなりますし,試験慣れすると合格しやすくもなります。
何より,半年に1回のイベントですし,参加しないとなんか取り残された感がして,つまらないのです。
コミケなどと一緒で,外から見ているよりも,実際に参加した方が楽しめると思います。
申込を行うと,試験勉強のやる気もでてきます。
早めに受験区分を決めて,試験に向けて集中していきましょう。

今月から,ヨガのスタジオに入会して,週に2~3回ぐらい通ってます。
私はめちゃめちゃ体が硬くて,肩こりや腰痛対策にヨガをはじめたのですが,体もほぐれてきていい感じです。
そこで,体を動かしながら感じるのは,ちょっとでも自分で進歩を感じると楽しい,ということです。
昨日よりちょっと,今までできなかったことができるようになる,また,体の中をより感じられるようになると,それだけでかなりうれしかったりします。
多分,もともと体が柔らかい人は当たり前にできるようなことが,私は当たり前にできない,ということが多いです。
でも,その分,できたときに喜べることが多いのかな,と感じています。
例えば足の指先に手が届くようになった,ということが,とってもうれしかったりします。
ちょっとずつの進歩,というのは,身近な喜びのわりにうれしさが大きくって,結構お得な感じです。
ランニングは,進歩がタイムなどの数値で分かる面白さがありますが,ヨガは地味に,自分の内側に進歩を感じる感じです。
そのゆるさが,あまり頑張る感じじゃなく,心地いいかな,って思ってます。
試験勉強も,最初からできていたら,全然面白くないと思います。
勉強しなくても受かる試験というのは,優越感を満たしたり,自信をつけたりするのにはいいですが,勉強するやりがいはあんまりないと思います。
ですので,ある程度勉強しなきゃ受からない試験の方が,受けていて面白いと思います。
試験の場合,よく言われるのは,「自分の今の実力では無理だけど,勉強すれば受かりそう」と感じられるぐらいのレベルの試験が,一番やる気が出ます。
難しすぎて全然ムリ,というぐらいだと,最初からやる気を失いますし,今のままでも大丈夫,と思えば勉強する気も起きません。
適度に難しくって,「3ヶ月ぐらい勉強すれば受かりそう」と思えるぐらいが,試験の選択としては適当です。
個人的な経験だと,第一種情報処理技術者(今の応用情報技術者)やネットワークスペシャリストを受験するときには,「ちゃんと勉強しないと受からなそうだけど,やったらできそう」と感じで,やる気にあふれて勉強できました。
そして,その時に,最初は全然解けなかった問題が,知識を身につけて演習を繰り返していくことで段々解けるようになっていくところが,すごく楽しかったです。
ゲームの時の,1つ1つ面をクリアしていく感じで,1年ずつ過去問をクリアしていって,そのたびに力がついていく感覚でした。
やる気が全然起きなかったのは,最初の論文試験で見栄をはってシステムアナリスト(今のITストラテジスト)を受けようとしたときです。
なんか,やらなきゃと思うんだけど進まない。。。という状態で,全然勉強できませんでした。
今思えば,段階を飛び越していたので,やっても無理,と心の底でわかっていたんだと思います。
逆に,システムアナリストに受かった後に上級システムアドミニストレータを受けようとしたときにも,あまりやる気が起きませんでした。
そんなにやらなくても行けそうな気がしたのと,なんか勉強しても面白い知識や役に立つ知識にあまり出会えそうにないなぁ,と感じていたのが原因です。
(このあたりは,個人の好みの問題だとは思います。)
できないことがいっぱいある,ということは,それをできるようにしていく面白さがいっぱい残されてる,ということでもあります。
今できないからといって落ち込まず,1つ1つクリアしていくことを楽しみましょう。

最近読んで感動した本に,「ねこ背は治る! ──知るだけで体が改善する「4つの意識」」があります。
この本はねこ背を直す本ですが,トレーニングをしたり頑張ったりする本ではありません。
体に対する意識を変えることで行動を変える,という本です。
確かに,本に書いてあるようなところに意識を向けると,あっというまにねこ背は改善しますし,呼吸も深くなります。
内容も面白いのですが,改めて,「一般常識として思い込んでいること」が実はそうじゃない,ということも多いんだなぁ,と感じました。
実はこの,「ねこ背は治る! 」の本の中にも書いてあるのですが,良質な知識は,勉強してそれを知るだけで,今までの意識をガラリと変えることがあります。
ねこ背の本だと,それは「肩甲骨の知識」だったりするのですが,確かに,肩甲骨についてきちんと知ると,体の動かし方が変わってくるのが分かります。
同じように,IT関連の知識でも,きちんと知ることによって意識が変わってくるものって,いっぱいあるように感じます。
私の経験で真っ先に浮かぶ,きちんと知ることで仕事のときに意識が変わったものに,「OSI階層モデル」があります。
ネットワークの勉強をすると出てくる,「物理層,データリンク層,。。。。」という定番の7階層です。
この7階層を,単に覚えるのではなく,深い知識としてその意味や役割が腑に落ちたときに,見えてくるものが変わりました。
その当時,Web系のエンジニアで,ネットワークのトラブルシューティングをしていたのですが,トラブルが起きた時の対処法が,明らかに変わりました。
昔だと,トラブルが起こったらその状況に気を取られて,全体を見ることはしなかったのが,まず状況を大局的に見て,OSI階層モデルのどの層あたりかを考えてから動くようになりました。
トラブル解決の速度と精度が,格段に上がったのを覚えています。
データベースの正規化などは,業務でやる前に勉強したので,それで変わったという意識はありませんが,知らなかったら多分,苦労しただろうな,というのは予想できます。
もちろん,試験勉強以外でも,勉強することで意識が変わることはいろいろあると思います。
プログラミングや開発手法などは,ただ実際に組むというだけでなく,達人が書いた本を読むことで,「なるほど!こう考えればいいんだ!」と気づくことも多くあります。
「達人プログラマー―システム開発の職人から名匠への道」や,「コードコンプリート―完全なプログラミングを目指して (Microsoft PRESS)」などを読むことで,先人の知識を自分の中に取り込んで,意識を変えることができます。
ちなみに,「コードコンプリート」は,新しい版が出ていて,「Code Complete第2版〈上〉―完全なプログラミングを目指して」と「Code Complete第2版〈下〉―完全なプログラミングを目指して」の2巻に分かれているんですね。
ただやみくもに,新しい知識を覚えることを勉強だと思うと,つらいと思います。
新しいことを知って,自分の意識を変えたり,視野を広げるのが本来の勉強です。
新しいものに,「こんなのがあるんだー」と感心しながら,楽しく勉強していきましょう。

本日,わく☆すた公開セミナー「論文対策」が無事終了しました。
ご参加いただいた,皆様ありがとうございました。
弊社facebookページで写真を公開しています。
論文は,実際に書いていただくと,その大変さが体感できます。
その分,達成感もあって,1本書き上げると,すごくやり遂げた気分になります。
終わった後の懇親会では,みなさん一様に,「手が疲れた~」と楽しそうに言われていました。
今日,改めて感じたのは,文章を書くということは,才能よりも何よりも,「慣れ」が肝心だなぁ,ということです。
実際に,勉強や仕事で,手書きの文章を書き続けている文章は,読みやすいですし論文の質も高いです。
「鉛筆なんて持つの久しぶり」だと,書き上げる前に手が痛くなりますし,書き続けるのはつらいです。
スポーツや楽器の演奏だと,初日からいきなりできる,というわけにはいかないのは,当たり前に感じると思います。
それと同じで,実は文章を書くというのも,頭と言うより体の動作がもとになりますので,練習が大切です。
ちなみに,文章だけでなく,英会話なども,体が中心なので,練習と慣れが大切です。
文章は,いきなりは無理ですが,3ヶ月もあれば,慣れて上達します。
今の時点ではできなくても,試験までは3ヶ月以上ありますので,まだ間に合います。
必要な練習をじっくり,今から行っていきましょう。
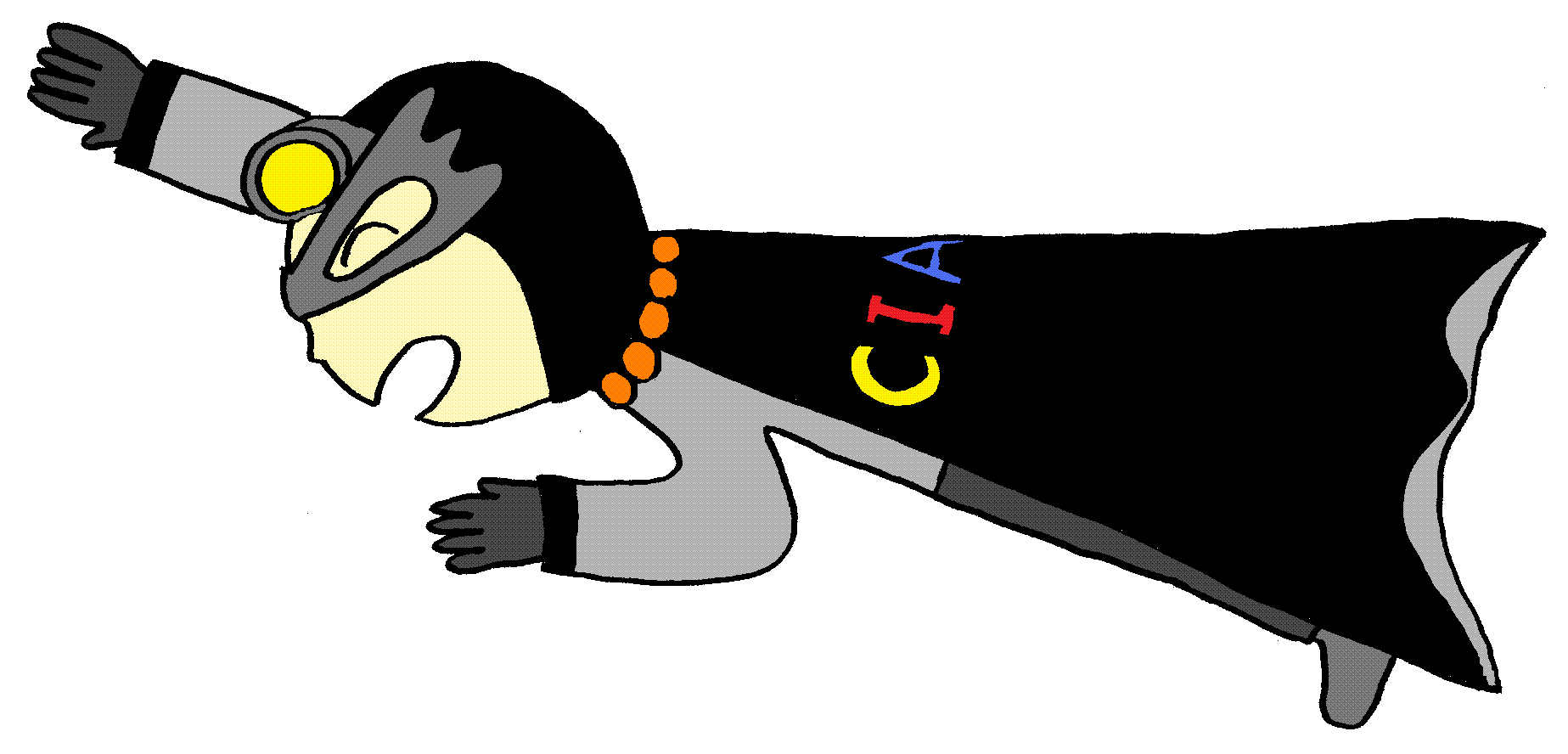
わく☆すた,けんけんです。
今日は,2012年秋向け公開セミナー「情報セキュリティスペシャリスト対策3回コース1回目」を開催しました。
連休の中,ご参加いただいた皆様,ありがとうございました。
いつものオープニング板書は,弊社facebookページに公開しています。
このセミナーはDVD化して販売いたします。一週間ほどで完成の予定です・・・。と言いたい所なんですが,7月に入ってから1日セミナーが今回で3回目なので,編集が遅れております。今月中には編集を終わらせたいと考えています。がんばって編集しますので,しばらくお待ち下さい。
ちょっと前のブログでゲームの話題が出ておりましたが,実は,わく☆すた社内では,iPhoneのゲームが流行っていたりします。種類は2つ,「なめこ栽培キット」と「ぐんまのやぼう」です。
始め,美月さんが「ぐんまのやぼう」をやり始め,社内に「ぐんま~」の合唱を響き渡らせ,さっと宇宙まで群馬県にしてしまい,話題になっていた「なめこ」に手を出し始め,それなら自分も流行に乗るかと,同時に始めました。
(とその横で,「ぐんま~」とこだましてたりします。)
この2つのゲームの共通点は,“がんばってもできない”点です。ぐんま・・・は作物を収穫してぐんまポイントをGETしてゆき,なめこは,生えてくるなめこを収穫して,Np(なめこポイント)を稼いでゆきます。
どちらも“収穫”なので,生えてくるのに時間差があります。なので,時間をあけて画面を開いて収穫する動作を繰り返します。地道なゲームですよね。
人によっては,シューティングゲームがいい。と言う人もいれば,フライトシュミレーターだ,RidgeRacerだ。と言うひともいるでしょう。
ひとそれぞれ好きなタイプがあって,自分はシューティングとかの反射神経系のゲームは苦手です。
勉強法にしてみても,短期集中型で行ける人もいれば,毎日の積み重ねが得意な人,電車の中で本を読むとか,スターバックスだと気分が乗るなんてのもあるかもしれません。
もし,勉強があまり進まない,気乗りがしないと感じているのであれば,勉強のスタイルが自分向きでないのかもしれません。このブログでは,いろいろな勉強方法を紹介しているので,ちょっとサイト内検索するとか,カテゴリ「勉強法」を眺めるとかすると,自分向きの勉強法が見つかるかもしれません。
明日もセミナーなので,今日はこの辺で。
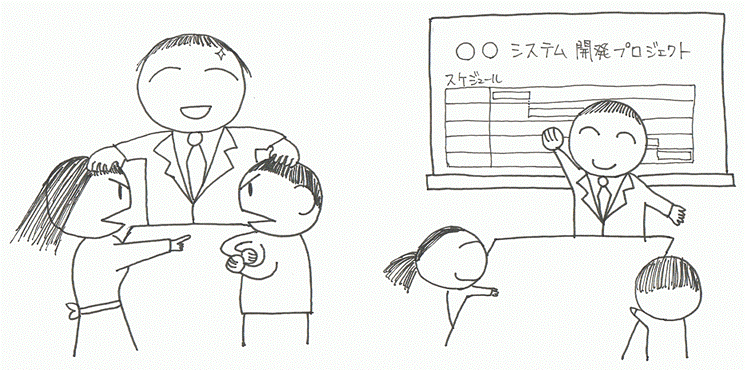
プロジェクトマネージャ試験などの論述式の試験は,一度しっかり論文の書き方を練習すると,合格する可能性は格段に上がります。
今回の合格体験記は,午後2のB判定から,2回目の挑戦でプロジェクトマネージャ試験に合格されたdekochanさんです。
********************
【基本情報】
氏名:dekochan
年齢:41歳
プロジェクトマネージャ受験:2回目

私は,SunのJava認定資格,SJC-P(Sun Certified Programmer for the Java Platform)を持っているのですが,今日,Oracleから,「Java SE 7 認定資格」の案内が届きました。
今なら,アップグレード試験に合格すれば,いきなり「Oracle Certified Java Programmer, Gold SE 7 認定資格」を取れる,ということで,受けようかな,とちょっと迷ってます。
国家資格にしろ,ベンダー資格にしろ,IT関連の資格は,結構いっぱいあります。
以前も紹介した,「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ(Ver.6 Rev.1)」によると,いろいろな資格が,レベル・分野ごとに位置づけられています。
ちなみに,先ほどのSJC-P(今は,OCJ-P)は,この表だと,アプリケーションスペシャリストとソフトウェアディベロップメントのレベル2に位置づけられています。レベル3がOCJ-D,レベル4がOCJ-EAという上位資格になっています。
資格のバージョンが変わって,Bronze,Silver,Goldがどういった位置づけになるのかも,ちょっと楽しみです。
最近,時々思うのが,「試験って,ゲームみたいなものだなぁ」ということです。
世の中にさまざまなゲームがあるのと同じように,世の中にはさまざまな試験があります。
試験によって,レベルも違いますが,ジャンルもさまざまです。
ゲームと同じように,試験にもルールがあります。
「こういうスキル・知識があることを確認する」というクリアポイントがいくつかあって,それをクリアすれば合格です。
ある程度失敗してもよく,6割ぐらいのポイントがクリアできていればOKです。
そういう風に考えると,攻略の仕方も見えてくると思います。
たまに,試験内容ややり方そのものにケチをつけて,「こういう試験はおかしい」「答えはこれとは限らないはず」などいろいろ言う人がいますが,それはゲームのルールにケチをつけているようなものです。
ゲームをクリアするのが目的なら,自分の意見で批判するより,クリアする方法を知った方が早いです。
情報処理技術者試験は,IT各分野の専門家が集まって,「この分野の専門家は,こういうスキルを持っていて欲しいよね」といういくつかのクリアポイントを決めて,それを試している試験です。
「こんなスキルがあった方がいい」という独自の自己主張を求められているわけでもなく,趣旨に素直に従って答案を書く人が高得点をもらえます。
ロールプレイングゲームと同様,「仕事の現場」というダンジョンに出かけて,経験値を稼いでスキルを身につけるのが王道です。
試験勉強は,現場とはちょっと違う,経験値を稼げるダンジョンに行って,試験のために効率的に経験値稼ぎをするようなものです。
そして,恋愛シミュレーションゲームと同じように,「攻略する女の子」じゃなく,「攻略する試験区分」が好む解答を書かないと点数にはなりません。
ITストラテジストの論述式で,システムアーキテクトが好むような論文を書いても,「私の好みじゃない」とバッドエンド一直線です。
現実の世界は確かに,ルールや答えのないことだらけです。
でも,試験やゲームの場合,それをプレイするために設定されているルールやクリアポイントが必ずあります。
それを見つけていくのが,試験やゲームの醍醐味でもあります。
勉強に煮詰まりそうになったら,ちょっと引いて,ゲームでもやってるつもりで問題を眺めていきましょう。
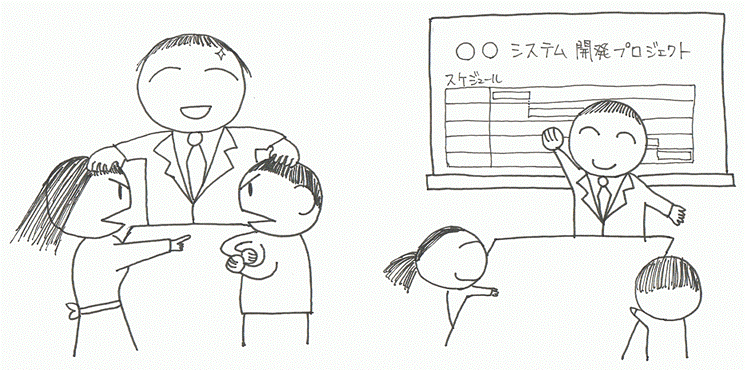
初のプロジェクトマネージャ合格体験記の掲載になります。
今回は,プロジェクトマネージャ試験の合格体験記を数多くいただいていますので,順次掲載していきます。
秋試験でも,論述式の試験(ITストラテジスト,システムアーキテクト,ITサービスマネージャ)を受験される方には,いろいろ参考になると思います。
それでは,昨年秋に「情報セキュリティスペシャリスト合格体験記」を書いていただいて,さらに連続でプロジェクトマネージャ試験に合格された,ザウルスさんの合格体験記です。
*************
昨年秋のSCに続きこの春はPMに合格できました。
皆さんの参考になればと思い体験記を書きしるします。
【基本情報】
氏名:ザウルス
年齢:53歳
プロジェクトマネージャ試験 受験:1回目

続々と合格体験記をいただいています。
ご応募いただき,ありがとうございます。
現時点でいただいた体験記から,今回の応募の特徴としては,「常連さんが増えた」ことと,「データベーススペシャリストとプロジェクトマネージャが多い」ことが挙げられます。
情報処理技術者試験には,実は,「受かると次も受かりやすい」という特徴があります。
自分の経験からも,受講生さんや知り合いの状況からも,「受かる人は連続で受かる」ことがすごく多いのです。
今回は,去年応用情報技術者に合格された方が,今年やデータベーススペシャリストに受かった,とか,前回は情報セキュリティスペシャリストだったのが,今回はプロジェクトマネージャ試験に合格した,という感じで,順番にレベルアップしている体験記をたくさんいただいています。
改めて,徐々にステップアップしていくって大事だなぁ,と感じています。
自分の実力で,段階の飛び越しをせず,勉強すれば無理なく取れる資格から順にとっていくと,連続して合格しやすくなります。
基本情報技術者や応用情報技術者の勉強をきちんとやると,次の高度の勉強に確実につながります。
私の感覚では多分,情報処理技術者試験でステップアップしてくときの大きなステップは3つあって,
1つは初めて情報処理技術者試験に合格するとき,
次は初めて高度区分に合格する時,
もう1つは初めて論述系区分に合格する時
です。
最初は,情報処理技術者試験というものがどんなものかわからないので,いろいろ戸惑うことも多いと思います。
まずは,簡単な試験から順に受けていくのが,一番確実です。
それを突破して応用情報技術者まで合格したら,次は最初の高度区分で,レベル差に圧倒されることが多いです。どの区分を受けるにしても,内容はかなり深くなりますし,文章も長文になります。
いきなり高度区分だと,乗り越えるべきハードルが多すぎて,かなり苦労すると思います。
そして,論述系になると,スペシャリスト系の高度とはまた,違った準備が必要になります。
「論述式の文章を書く」こと,「題意に合わせて,専門家として文章を書く」ことなど,知識だけでは太刀打ちできないことが増えてきます。
ただ,それぞれのステップを超えた後は,比較的楽に,次に行けると思います。
ネットワークスペシャリスト,情報セキュリティスペシャリスト,そしてデータベーススペシャリストは,結構毛色が違いますが,1つ受かると,2つ目,3つ目は意外とすんなり合格したりします。
論述系はもっと顕著で,なにか1つ受かってコツをつかむと,その後は連続で合格する人が多いです。
特に,システムアーキテクトとプロジェクトマネージャなど,立場の違う2つの試験が書き分けられるようになると,他の試験区分も合格しやすいです。
人によって,壁だと感じるステップは違うとは思いますが,1つ1つのステップがすべて大変なわけではありません。
まずは一歩一歩,目の前のステップに,全力で取り組んでいきましょう。
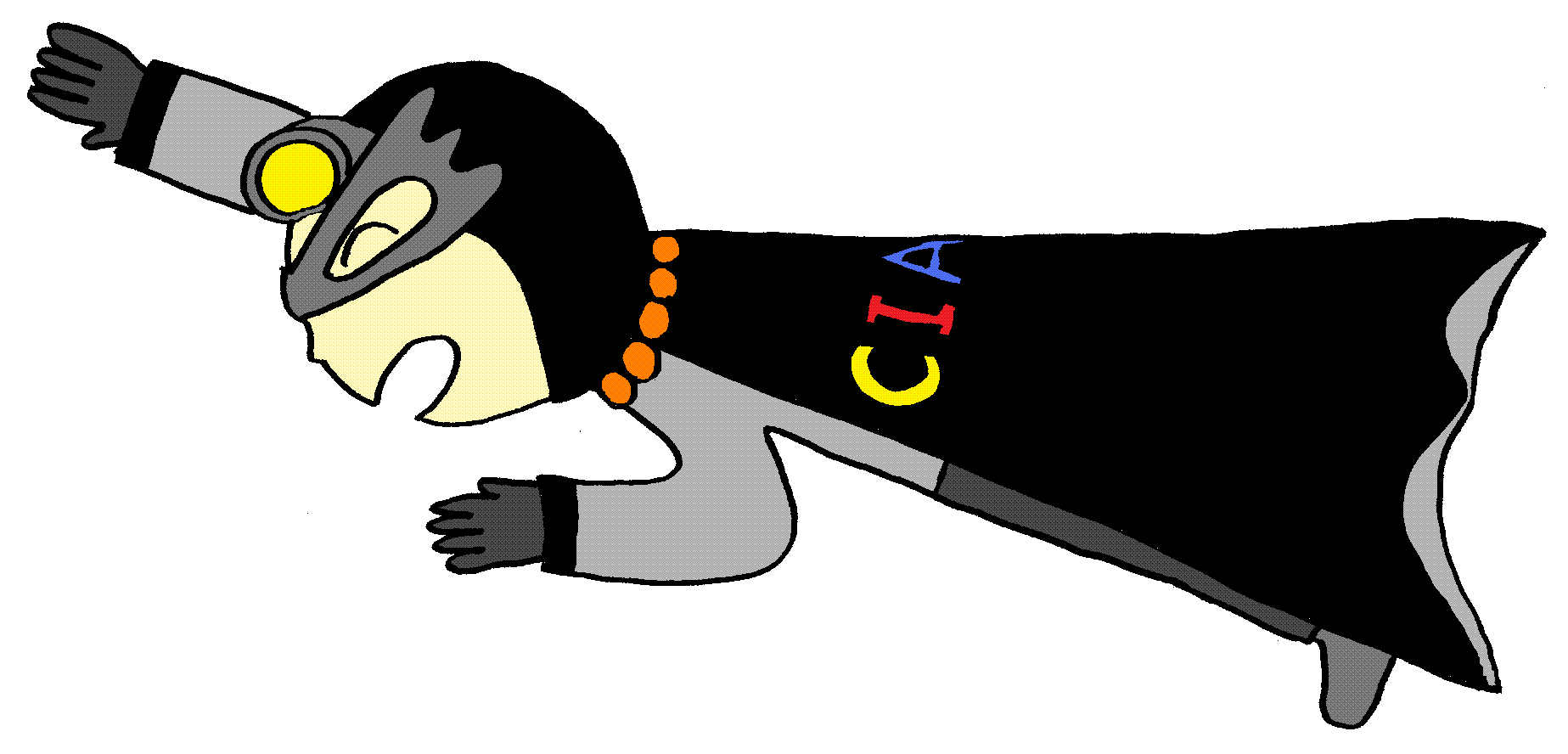
平成24年春期試験版,合格体験記の第1弾は,募集する前に体験記を送ってきていただいた風太さんです。
風太さんは,以前にも「システムアーキテクト合格体験記:風太さん」「データベーススペシャリスト合格体験記:風太さん」でも合格体験記をいただいており,こちらが3回目の合格体験記となります。
--------------------
【基本情報】
氏名: 風太
年齢: 38歳
情報セキュリティスペシャリスト試験受験:1回目
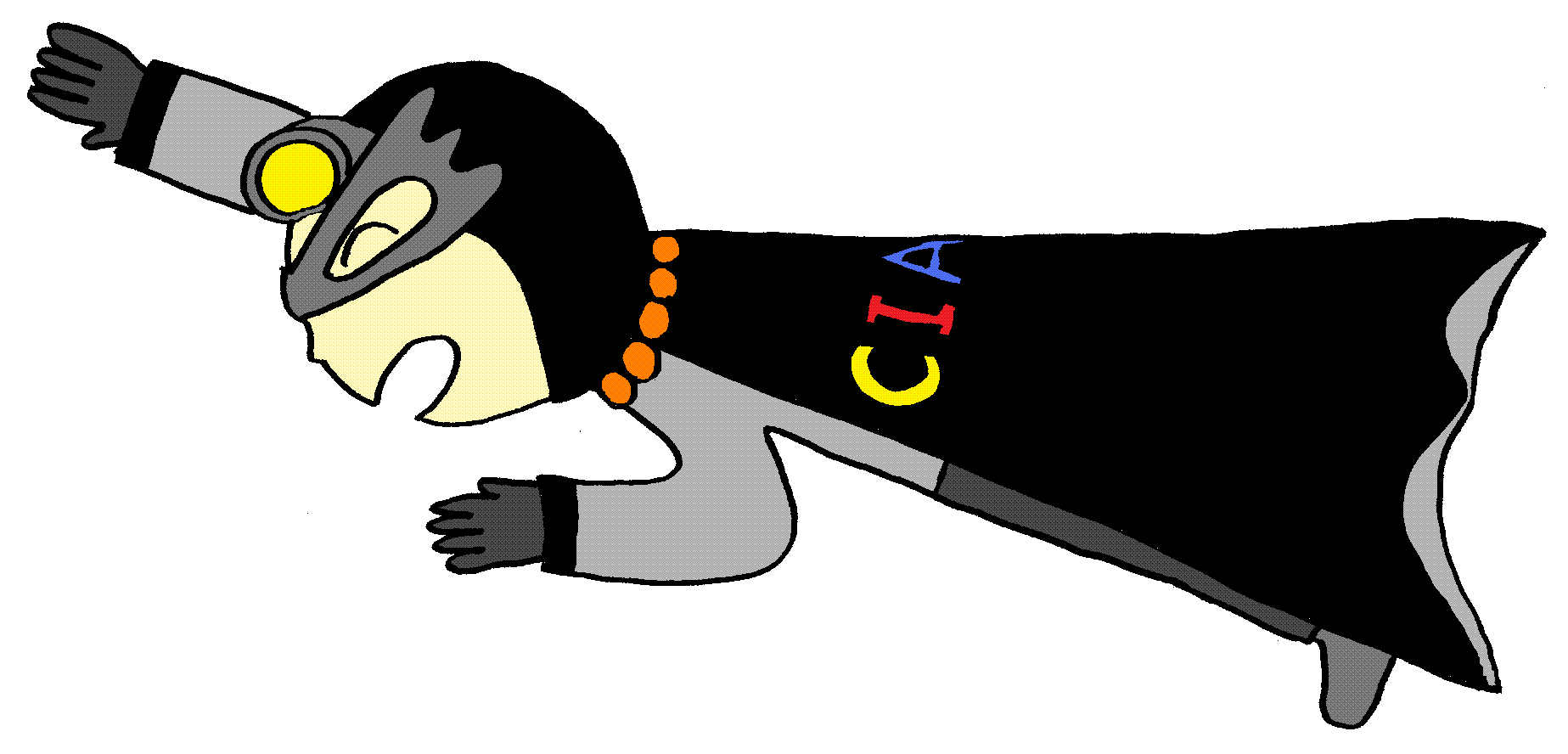
新しい情報があったので,本日2つ目のブログです。
さっきAmazonで,「情報処理教科書 情報セキュリティスペシャリスト 過去問題集 平成24年度秋期試験/平成25年度春期試験」が発売されるのを見つけました。
発売日は2012/7/13となっていますので,さっそく予約注文しました。
著者の上原 孝之さんは,「情報処理教科書 情報セキュリティスペシャリスト 2012年版」の著者でもありますし,今までの解説を見る限りでも,内容はかなり期待できそうです。
アイテックの2012年秋向けの「2012秋 徹底解説 情報セキュリティスペシャリスト 本試験問題」も,アイテック直販で,本日発送されました。Amazonや書店では,2週間後ぐらいになるようです。
情報セキュリティスペシャリストの過去問集は,今まであまり充実していなかったのですが,これである程度出揃った,という感じですね。
スペシャリスト系の試験の場合,過去問演習をしっかりやって,試験に求められていることを把握することが大切です。
書店で見比べてからでも遅くはないと思いますが,内容がしっかりしている過去問集は,1冊は手元に置いておくのがおすすめです。

今日,予約していた「ネスぺ23 本物のネットワークスペシャリストになるための最も詳しい過去問解説と合格のコツ」が届きました。
このシリーズは,1年分の午後問題だけを解説することに特化した本です。
これで,「ネスペ21」「ネスペ22 β版」と合わせて,過去3期分揃いましたので,3年分の過去問をしっかり学ぶ,という用途にも使えます。
ざっと目を通してみましたが,相変わらずの詳しい解説でいろいろ面白いです。
コラムも充実していて,SEならコラムを読むだけでも楽しめると思います。
今回は最初から,β版ではなく正式版ですし,出版社(星雲社)からの出版のようです。
Amazonでは現在,「通常1~3週間以内に発送」となっていますし,想定より売れていそうです。
現在のところAmazon限定発売のようですし,試験に役立てたい方は,在庫切れになる前に早めに手に入れるのがおすすめです。
ネットワークスペシャリスト試験は,私が最初に受験してた頃(平成9年ぐらい)には,過去問集が少なく,なかなか納得のいく解説がなくて,かなり苦労した覚えがあります。
今は,アイテックの「2012 徹底解説ネットワークスペシャリスト本試験問題」や,翔泳社の「情報処理教科書 ネットワークスペシャリスト 2012年版」など,過去問解説の充実した本が増えてきて,勉強しやすくなったなぁ,と感じます。
ネットワークスペシャリスト試験の合格には,過去問対策は欠かせません。
できれば,複数冊過去問集を購入して,自分で調べたりもしながら,徹底的に過去問をマスターしていきましょう。

本日は,わく☆すた公開セミナー「ネットワークスペシャリスト対策 5回コース」の2回目を開催しました。
ご参加いただいた方々,お疲れさまでした。
今日は,TCP/IPとLAN,WANという,ネットワークの中核技術について学びました。
過去問は,平成23年午後1問2を扱い,待ち行列を中心に,計算問題の解き方について学びました。
ネットワークスペシャリスト試験は,基本となるOSI各階層の技術をしっかり理解することが,合格のための土台になります。
最新技術に走る前に,基本をしっかり理解しておくことはとても大切です。
去年(平成23年)のネットワークスペシャリスト試験の午後1では,問2の問題が多分,内容としては一番やさしいのではないかとは感じています。
でも,選択している人も少ないですし,実際,受験するとしたら私も避けるかもしれないです。
計算問題は,確実に解けると満点が狙えますが,ミスをするとダメージが大きいです。
特に,今回のように計算が空欄ア,イ,ウ,エと続くときには,最初の方を間違えると連鎖して間違えてしまいます。
ハイリスク,ハイリターンな問題なのです。
情報処理技術者試験の場合,計算問題が多く出てくる高度区分は,ネットワークスペシャリストとエンベデッドシステムスペシャリストぐらいだと思います。
基本情報技術者と応用情報技術者も,それなりにいっぱい出てきます。
個人的には,計算問題は得意な方ではあるのですが,選ぶ時にはちょっと怖いです。
計算問題を解くときには,他の問題よりもかなり注意を払って解きます。
以前,「計算問題を間違えない方法」で,間違えない方法はまとめていますので,よかったら参考にしてください。
何度か過去問演習で解いてみて,自信がついたら選択してみるのも悪くないと思います。
計算問題を選ぶか選ばないかは,当日の状況で決めればいいと思いますが,準備不足だと,焦って足元をすくわれる可能性が高いです。
十分に練習してから,本番に臨めるように今から演習をしていきましょう。

合格体験記の応募,続々いただいています。
おかげさまで,プロジェクトマネージャ試験の合格体験記が多く,今期は論述系がすごく充実しそうです。
論述系の試験区分の方の合格体験記は,みなさん文章がしっかりされていて,ほとんど手を入れる必要がないのも,ありがたいところです。
さすが論述系の午後2に合格されるだけあって,人にわかりやすい文章を書くことに長けているなぁ,と感心しながら読ませていただいています。
まだ,引き続き募集中ですが,来週から順次,公開していきたいと思います。
私事ですが,今日は私の誕生日でした。
そこで,けんけんからの誕生日プレゼントは,リクエストして,何かものをもらうのではなく,「家・事務所のいらないものを減らす」ことにしてもらいました。
欲しいもの,ということでものを増やしていくと,その分空間が減ってしまいます。
何かをもらってものを増やすより,多すぎるものを減らしていく方が大切だな,って最近すごく感じています。
自分のものは大分断捨離して減ったのですが,そうすると今度は,一緒に仕事しているけんけんのものが気になってきてしまっていました。
勝手に捨てることもできないので,「荷物を減らしてもらう」ことを,プレゼントにお願いすることにしました。
私の本は,3年前に比べると,4分の1ぐらいに減りました。
なるべく電子書籍を買うようにしたり,スキャンして自炊したりしているのもありますが,残しておきたい本って,思いの他少ないな,というのを最近感じています。
ものがない空間が増えると,すっきりしてとてもいい感じです。
40歳を超えて,そろそろ人生も折返し地点になりました。
死ぬ時にはなにも持っていけないので,これからは少しずつ,不要なものを減らしながら進んでいきたいな,って思ってます。

本日,平成24年度春期試験について応用情報技術者・高度区分午後の採点講評が公開されました。
自分の受けた区分について見直してみると,いろいろなヒントになると思います。
例えば,データベーススペシャリスト試験では,受験生の方に聞いた限りでもそうでしたが,午後1が全体的に正答率が低く,午後2が高かったようです。
特に,午後1の問1と問2は,選ぶ人が多い問題でもありますし,この2問が難しめだったのは影響が大きかったのではないかと思います。
私が受けたエンベデッドシステムスペシャリストは,午後1の問1~問3,午後2の問1・2の全部が,「正答率が高かった」となっています。
受かりやすかったかどうかはともかく,解答が一意に導けて,解きやすい問題だったとは思います。
そして,応用情報技術者試験の場合,今回,受験生の方から聞いた限りでは,マネジメント系,ストラテジ系を中心に選んだ人の合格率が低めでした。
逆に,テクノロジ系を中心に選んだ方は,かなり合格しています。
採点講評を見る限りでも,問1より問2を選んだ人の方が,受かりやすかったようです。問2のプログラミングは問題も易しかったですし,「正答率が高かった」とはっきり明記されています。
全体として「正答率が低かった」と書かれているのは,問10のプロジェクトマネジメントです。この問に限らず,今回はマネジメント系3問は,結構難しかったように思います。
プロマネは,今回D判定がかなり多めだったのですが,午後2の採点講評を見る限り,「プロジェクトについて記述して欲しいのに,システムとか他のことについて書いちゃってる答案が多いよ」ってことなのかな,と感じます。
情報セキュリティスペシャリストは,午後2の問1と問2で,問1が「正答率が高かった」で,問2が「正答率が低かった」なので,選択問題によって明暗を分けた感じもあります。
システム監査の午後2講評も,「題意とあっていない」「出題の趣旨に合致していない」などの記述が多いですね。
採点講評を見ると,「出題者がどんなところを意識して採点しているか」がよくわかります。
自分が受けた試験は特に,解答を振り返るだけでなく採点講評を見て,どれだけポイントを押さえていたかを確認していきましょう。

なんとなく,平成24年秋向け情報処理技術者試験の案内書を見ていて思ったのですが,12ページの願書の作成要領に記載されている「高杉謙信」さんって,40歳なんですね。
1972年4月1日生まれ,ってことは同学年かぁ。。。で,FE受験なんだ。。。と,妙なところがツボにはまってしまいました。
昔は,サンプルの人の年齢って,もっと若かった気がするのですが,試験を受ける人も高齢化が進んでいるのでしょうか。
ってことで,ちょっとだけ統計情報を調べてみました。
平成21年以降の情報処理技術者試験の平均年齢は,「平均年齢(PDF)」としてまとめられています。
過去3年分を見る限り,それほど大きな変動はないようです。
それ以前の資料は,公式にはないのですが,大分昔,ということで,2001年に書かれた@ITの「情報処理技術者試験は受験すべきか?」の記事のデータをもとに,10年のスパンでの変化をみてみました。
平成12年と平成23年での平均年齢の違いを,表にまとめたのがこちらです。(画像データです)

やっぱり,ちょっとずつ上がってきてる感じですね。
若い世代の人数が少ない,ということや,私たち団塊ジュニア世代の人数が多い,ということも大きく影響しているのだとは思います。
基本情報技術者は,受験者は昔は20代前半,という感じでしたが,今は27歳ぐらいが平均のようです。
だから何?という感じではあるのですが,なんとなく最近,受験者の平均年齢が高くなってきた気がしていたのが納得です。

わく☆すたでは,本日より,平成24年春に合格された方の合格体験記を募集します。
詳しい募集要項は,わく☆すたホームページの「合格体験記の募集について」をご覧ください。
次の試験に向けて,受験される方に役立つ合格体験記を募集しています。
前回までに採用させていただいた合格体験記は,以下の各試験区分のページにまとめられていますので,よろしければご覧ください。
・応用情報技術者
・情報セキュリティスペシャリスト
・ネットワークスペシャリスト
・システムアーキテクト
・ITサービスマネージャ
・データベーススペシャリスト
そういえば,ITストラテジストのものがないので,近日中には私の合格体験記(平成23年秋合格)を載せます。
論述系区分は数が少ないので,合格体験記は去年のものも募集します。
あと,今回から,プレゼントするクーポン券の金額を,区分ごとに変えました。
合格された区分が高度区分(情報セキュリティスペシャリスト(SC)を除く)の場合は3,000円分,情報セキュリティスペシャリストの場合は2,500円,応用情報技術者(AP)の場合は2,000円です。
前回募集したときに,全部同じ金額にしたところ,SCとAPの数が多くなりすぎたので,今回は差をつけさせていただきました。
今日,ヨドバシAKIBAの有隣堂に行って,平成24年秋向けの願書をもらってきました。
試験の申し込み開始は7月23日(月),もうすぐです。
合格体験記を参考に,試験合格のイメージを明確にして,勉強を進めていきましょう。

前回,2012年春試験向けセミナー,おかげさまで大勢の方が合格されましたが,その中でも「わく☆すた直前勉強会」に参加された方の合格の声が,特に多かったです。
午前は午前問題バトル,午後は午後2の問題演習&採点し合い,という勉強会でしたが,アウトプットが多かったのが効いたようです。
特に,他の人の書いた午後2記述式や論述式の答案を採点することで,採点者の視点に気づいた方も多かったように思います。
今回は,試験前の祝日,10/8(月)に会場を確保できましたので,この日に開催する予定です。
詳細の発表は後日また行いますが,参加しようと思われている方は,日程を確保しておいてくださいね。
勉強会やセミナーだと,他の人の視点がわかる,という利点があります。
学習というのは,一人でやっているより,他の人と一緒の方が気づきが多いので,効率的に進みます。
何か学びたいことがあるときには,他の人がいる場所に行くというのはおすすめです。
ただ,直前勉強会のような,アウトプット中心の学習は,やる気さえあれば一人でもできます。
そして,試験に合格する,という目的がある場合には特に,アウトプットを意識した学習がおすすめです。
試験というのは,答案の上に,自分の考えたことをアウトプットする作業です。
いくら頭ではわかっていても,それを表現するのは,慣れていないと結構大変です。
日々の勉強の時に,アウトプットを意識して行っていると,本番でそれが活きてきます。
特に,午後2が論述式試験の区分は,手書きの文章でアウトプットすることに慣れておく必要があります。
以前,「手書きで字を書く練習をする」の記事でも書きましたが,手を動かす練習,というのも,意外と大切です。
手書きで正確に速く字が書けると,時間に余裕ができますし,午後試験では特に有利です。
アウトプットの練習は,やり始めてすぐに劇的な効果が出るわけではなく,継続して続けていくことが大切です。
試験の直前になって,「問題を解くのに,全然時間が足りない~」となっても,遅いのです。
今の時期からアウトプットを意識して,できるだけ書いて勉強を進めていきましょう。

本日,わく☆すた公開セミナー「高度午前1・応用情報午前対策 1日集中コース」が無事終了しました。
ご参加いただいた皆様,予定時間を大きくオーバーしてしまい,申し訳ありません。
長丁場におつきあいいただき,ありがとうございました。
今回のセミナーは,ボリュームが大きくなってしまったので,DVDだと3枚組~4枚組になる予定です。
YouTube動画配信も検討中です。
遠方の方,午前をしっかり繰り返し学習したい方はご活用ください。
次回からは,2日間に分割して開催する予定です。
午前分野って,一度通して学習すると,ITの全体像がなんとなくつかめます。
毛色の違ういろいろな分野を知ることによって,自分の業務以外のことも,いろいろ学ぶことができます。
ですので,個人的には,午前1試験は毎回受けて,知識をリニューアルし続けるのは楽しいです。
そろそろ秋試験の申込も始まります。
まずは午前問題などで基礎固めして,秋に向けて進んでいきましょう。