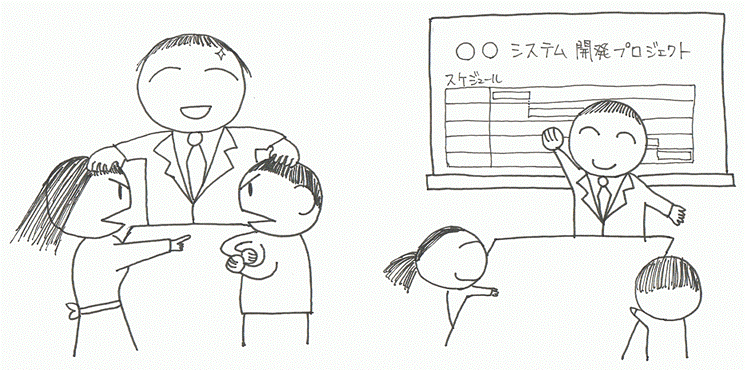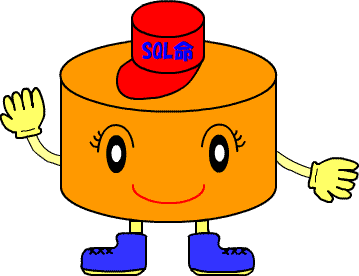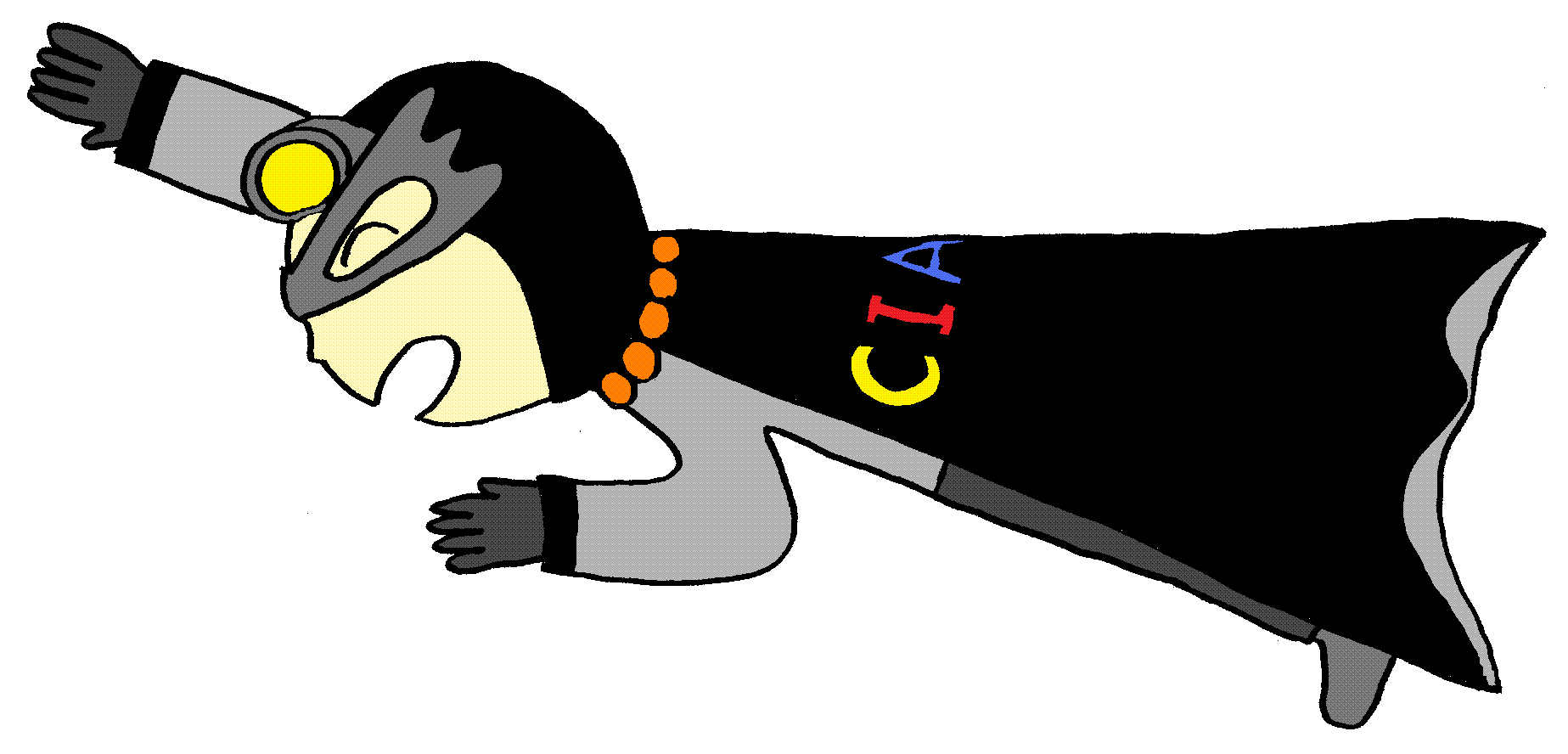以前,「情報処理技術者試験の難易度」という記事をかかせていただいたのですが,ブログのアクセスを見ると,この記事,なにげに人気なんですよね。
といっても,これを書いたのは2009年で,新試験制度が始まって間もない頃ですし,いろいろ曖昧な部分はありました。
新試験制度が始まって3年,そろそろ各試験の難易度や方向性も固まってきましたので,改めて情報処理技術者試験の全12区分の難易度を比較してみたいと思います。
まず,公式の情報,IPAのITスキル標準センターが発表している,「ITスキル標準 V3」の第1部概要編(PDF)では,情報処理技術者試験全12区分を,次の4つのレベルに分類しています。
<レベル1>
ITパスポート
<レベル2>
基本情報技術者
<レベル3>
応用情報技術者
<レベル4>
高度区分全部(ITストラテジスト,システム監査技術者,プロジェクトマネージャ,システムアーキテクト,ITサービスマネージャ,ネットワークスペシャリスト,データベーススペシャリスト,情報セキュリティスペシャリスト,エンベデッドシステムスペシャリストの9区分)
基本的には,レベル1,2,3は分野にかかわらず順にステップアップしていく資格で,レベル4は専門分野に応じて自分の仕事に関わるものを受ける,という形です。ですので,一応,レベル4はすべて同レベル,という形になっています。
ちなみに,ITスキル標準では,レベルは7までありますが,試験で判定できるレベルはだいたいレベル4まで,ということになっています。
その他のベンダ試験も合わせた,スキルレベルと資格の対応表は,スキル標準ユーザ協会が発表している「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ(Ver5 Rev1)(PDF)」にまとめられています。
この表によると,ベンダ試験系で,レベル4相当される現行のものとしては,
・ORACLE MASTER Platinum (Oracle Databaseの最上位資格,現在バージョンは11g,実技試験あり)
・CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert,CISCOの上位資格,ラボ試験あり)
・RHCA (Red Hat Certified Architect,Red Hat Linuxの最上位の認定資格)
・OCJ-EA (Oracle認定エンタープライズアーキテクトEE 5(Java認定の最上位資格,
プログラミング課題,小論文試験あり)
・ITIL V3 エキスパート(ITILの最上位の認定資格)
の5つのみです。
その他,旧試験のITIL V2 マネージャや,まだ未実施のUMTP L4 (UMLモデリング技能認定試験のレベル4(最高レベル))も,レベル4の対象ではあります。
こういった資格と比較すると,情報処理技術者試験の高度区分はレベル1,2,3とステップアップしてから受ける,最上位のIT関連の国家試験,という位置づけだと思います。
ちなみに,ITパスポートはレベル1ですが,だからといってめちゃくちゃやさしくて誰でも楽勝,というわけではないのです。
先ほどの「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ(Ver5 Rev1)(PDF)」にもあるとおり,ベンダ資格まで含めると,「レベル0」までありますし,レベル0のMCA(Microsoft Certified Associate)などよりは確かに難しいです。
ITパスポート試験はCBTなのでいつでも受けられる国家試験ではあるのですが,これに合格するためには,1からだとある程度しっかり学習する必要があるのです。
ですので,個人的には,情報処理技術者試験の受験順序としては,ITパスポート,基本情報技術者,応用情報技術者と順を追ってステップアップ,というのが,王道だとは考えています。
そして,高度区分の9区分,位置づけと難易度は,原則的には同じです。
ですので,専門分野に合わせていただいて,好きな区分を受ければいいのですが,会社などの一般的な評価,となると,結構区分によって差があります。取ったときの褒賞金でも,差がついている会社が多いです。
この分類は,私の経験からくる個人的な判断も入っていますので,言い切るわけではないですが,今の高度区分の評価は大体こんな感じだと思います。
<高度区分エントリー資格 最初に受けることが多い>
情報セキュリティスペシャリスト
<高度区分スペシャリスト系資格 取るとその分野に強いと評価される>
ネットワークスペシャリスト,データベーススペシャリスト,エンベデッドシステムスペシャリスト
<高度区分論文エントリー資格 論文系をとると一般に会社の評価は高い>
システムアーキテクト,ITサービスマネージャ
<高度区分論文上位資格 このあたりを取ると最高と評価されることが多い>
ITストラテジスト,システム監査,プロジェクトマネージャ
高度区分は1つとって終わり,ということではなく,いくつか取って幅を広げながら専門性を深めていく,という形になります。
段階的に,自分の進路を見据えながら,数を重ねていくのがおすすめです。
自分の現在地と欲しい資格とを比較して,確実にステップアップしていきましょう。