
Kindleで本を読む
昨日,いつも行ってる整体院の先生に,「体がかなり冷えてる。夏だからって冷たい飲み物ガブ飲みしちゃだめ」と言われてしまい,冷たい飲み物を控えるようにしました。
のどが渇いたら,熱いほうじ茶を入れて飲む。
ティーパックなので,意外と入れるのも楽です。
そうしたら,大分調子は良くなりました。
暑いからって,体を冷やしすぎてはダメですね。

昨日,いつも行ってる整体院の先生に,「体がかなり冷えてる。夏だからって冷たい飲み物ガブ飲みしちゃだめ」と言われてしまい,冷たい飲み物を控えるようにしました。
のどが渇いたら,熱いほうじ茶を入れて飲む。
ティーパックなので,意外と入れるのも楽です。
そうしたら,大分調子は良くなりました。
暑いからって,体を冷やしすぎてはダメですね。

うちには今日,情報処理技術者試験の合格証書が届きました。
今年は2枚,基本情報技術者と情報セキュリティスペシャリストです。
特別試験だから何か変わるかな,と思ったのですが,合格証書番号は第SC-2011-04-00143号って感じでいつもと同じです。
コメント欄で書いていただいた方もいらっしゃいましたが,合格証書の日付が8月なところから,いつもと違うことは識別できる,という感じです。
ちなみに,合格証書の日付は,基本情報技術者が8月5日,応用情報技術者・高度区分が8月15日のようです。
去年の応用情報技術者試験の合格証書は6月25日ですので,1ヶ月半ぐらい違いますね。
あと,経済産業大臣は,今話題の海江田万里氏です。
改めて署名を見て,情報処理技術者試験って国家試験なんだな,と感じました。
そんなこんなで前回の特別試験関連のイベントが,やっと全部終わりました。
あとは秋試験に向かっていくだけですね。
試験の申し込みがまだの方,忘れないように申し込みを行いましょう。
8月29日(月)が,インターネット個人申し込みの締切ですので,あと1週間です。
申し込みを忘れたら,どんなに頑張っても合格できません。
昔,申し込んだつもりで,実は申し込みを忘れていた,という人がいました。
受験料の支払いを,コンビニでの払込やペイジーでの払込にすると,申し込み後に別途,お金を払い込む必要が出てきます。
また,クレジットカードでの支払の場合にも,支払がうまくいかない場合には,申し込みは完了していません。
インターネット申し込みの方は全員,申し込みが完了していたら,「情報処理技術者試験受験申込み受付(完了)」のメールが届いているはずです。ちゃんと届いているか確認してみましょう。
今ならまだ申し込み直せば大丈夫ですが,申し込み締切後に気づくと悲しいです。
申し込みを完了させる,という行為自体が,秋への勉強のきっかけにもなります。
できるだけ早く申し込んで,「申し込まなきゃ」というストレスを手放していきましょう。
試験申込は,こちらです。

本日,わく☆すた公開セミナー「応用情報技術者対策 3回コース」「情報セキュリティスペシャリスト対策 3回コース」の2回目が無事終了しました。
ご参加いただいた皆様,ありがとうございました。
今回の講座の収録は無事終わりましたので,編集が終わり次第DVDを発売いたします。1週間後ぐらいの発売予定ですので,DVDで学習したい,という方は,もうしばらくお待ちください。
本日ははじめての会場で,浅草での開催でした。
浅草寺のすぐそばで,懇親会も「神谷バー」で開きました。
昭和の香り漂う,レトロな感じが楽しかったです。
今日,懇親会で質問されて,そういえば大事だな,と思ったことに,「計算問題を間違えない方法」があります。
応用情報技術者試験の午後問4は,毎回計算問題が多く,その出来が大きく点数を分けます。
しかも,1つ間違えると連動して間違える,ということもよく起こります。
私自身,もともとおっちょこちょいでミスが多い性格なので,小学校の頃から計算ミスには泣かされてきました。
「もっときちんと見直しをしましょう」と,よく注意されていたことを思い出します。
「忘れ物をなくしましょう」も同じぐらい言われていましたが。。。^^;
そこで,何十年にもわたる(^^;)奮闘の結果,忘れ物はともかく,計算ミスはだいぶん,減らすことに成功しました。
ここ数年は,情報処理技術者試験で計算ミスはしてないと思います。
ということで,私が気をつけている,「計算問題を間違えない方法」は,以下の通りです。
1.単位を書きながら計算する
2.問題用紙に計算式を全部残し,後で見直しをする。
3.過去の間違いを分析し,自分が間違いやすいパターンを知っておく
1,2は多分,定番だと思います。
単位を書いて,その単位が合っているかどうかを確認しながら,式を残して計算すると,間違いは少なくなります。
例えば,平成23年特別試験で,応用情報技術者午後問4設問1(1)に,次のような問題が出てきます。
(1)稼働率99.9%を満たすためには,1年間を365日とすると,1年間のサービス中断時間の累計は最大何時間か。
稼働率99.9%=0.999,1日が24時間ということを考慮すると,計算式は次のようになります。
365[日]×24[時間/日]×(1-0.999)=8.76[時間]
ここで,24[時間/日]を,面倒がらずに単位を書いておくと,単位の整合性が確認できます。日/日で日が消えて,時間だからちゃんと合ってるね,という感じです。
これを,紙に書いて残しておくと,検算するときに便利です。
そして,これに加えて,自分が間違えそうなパターン,というか,一度間違えたパターンはすべて記録しておく,ぐらいの勢いでチェックすると,自分のパターンが見えてきます。
今日,受講生の方も言われていましたが,私も結構,時間に関しては間違うほうです。
1年=365日(または366日),1日=24時間,1時間=60分,1分=60秒
当たり前なんだけど,意外とミスしがちです。
私はなぜか,1時間=3600秒とか,1日=86400秒とかの方が強烈に頭に残っていて,油断すると,分や時間を求める問題なのに,秒で計算してしまったりします。
あと,基本なんですが,かけ算と割り算を間違ってしまうとか,足し算よりかけ算を優先するのを忘れてしまうとかも,油断してるとやってしまいます。このへんは,最近は計算するときに気づいて,慎重にやってます。
計算ミスをしてしまったときには,「なぜそのミスをしたのか」「どんなミスをしたのか」を振り返ってみてください。
そうすると,自分のパターンも見えてきますし,そのミスを防ぐことができます。
特に,試験勉強中にミスをするのは,ダメなのではなく,本番で間違えないための経験値の上昇です。
パターンを知ることで,そのパターンから抜けることができるのです。
失敗は成功のもと。ミスも,経験として活かしていきましょう。

今年から,「ONE TOKYO」という,東京マラソン公式のクラブができました。
4月から,地味にスタートしていたのですが,ここのプレミアムメンバーになると,東京マラソンに出るチャンスが,格段に増えます。
一般に先駆けての先行エントリーがあったり,出場者に抽選で東京マラソン出場権が当たるマラソン大会に参加できたりします。
今日,先行エントリーの抽選結果の発表があって,おかげで当選することができました。
半年後の東京マラソン,今からしっかり準備して臨みます。
今回は,こういったクラブの情報を見逃さずに手に入れて,ちゃんと活用したことが良かったと感じてます。
プレミアムメンバーって言っても,年会費4,200円ですし。
ということで,情報を活用する,ということは結構重要です。
そして,情報は,ネットからの情報も大切ですが,人から,そして本からの情報も,とても大切だと感じています。
昨日,コメント欄で風太さんにご紹介いただいたので,早速今月号の「Software Design (ソフトウェア デザイン) 2011年 09月号 [雑誌]
」を買ってみました。
特集は,トップエンジニアのお薦め本55,ということで,エンジニアにおすすめの本がいっぱい出て来ます。
私が大好きな,技術の本質が学べる「新版暗号技術入門 秘密の国のアリス」や「珠玉のプログラミング―本質を見抜いたアルゴリズムとデータ構造」あたりの硬派な本もいっぱい紹介されています。
結構使える,面白い本や,まだ読んでないけど面白そうな本がいっぱい紹介されています。本が好きな方は,一度買って読んでみるのはおすすめです。
そして,個人的なお気に入りは,小飼弾さんの一押しの,「魔法少女まどか☆マギカ」です。
単純に今年一押しの,大好きなアニメではあるのですけど,それだけではありません。
IT関連の勉強会などで,この話をネタにプレゼンを行う,ということが,よく行われているので,知っておくと話についていきやすい,というメリットがあるそうです。
確かに,私のまわりの凄腕のセキュリティ管理者の人や,プログラマの人などには,まどか☆マギカが好きな人が多いですし,よくその話で盛り上がります。
もちろん,真面目な本でも,「共通の認識」として,読んでおくと話が通じやすい,ということもあります。
例えば,セキュリティ関連の人は,「アリス」といえば,秘密の国のアリスで,暗号化について詳しく書かれてる本,というのは通じると思います。K&Rと言えば,C言語の解説書,ラクダ本といえばオライリーのPerlの本,みたいな感じで,その分野で仕事するなら読んでおいた方がいい本,っていうのは,結構あります。
それと似たような感じで,「魔法少女まどか☆マギカ」を押さえておくのも,いいんじゃないかな,って感じてます。
Blue-RayやDVDで買わなくっても,ニコニコ動画で見られますし。
試験勉強をして知識を身に付けると,全体的に幅広く知識は得られるのですが,少し薄っぺらくなってしまいます。
自分の興味のある分野については,専門書などで深く掘り下げるのがおすすめです。
ITエンジニアが共通で持ってる趣味,というのも,会話からさらに深く多くのことを学ぶという意味で,ちょっとかじっておくのもおすすめです。
楽しみながら,いろんなことを学習していきましょう。

応用情報技術者の午後試験は,全部で12問あって,そのうち6問選択です。
12問の内訳は,
問1 経営戦略(か情報戦略か戦略立案・コンサルティングの技法,でも大体経営戦略)
問2 プログラミング(アルゴリズム)
問3 問1と同じ
問4 システムアーキテクチャ
問5 ネットワーク
問6 データベース
問7 組込みシステム開発
問8 情報システム開発
問9 情報セキュリティ
問10 プロジェクトマネジメント
問11 ITサービスマネジメント
問12 システム監査
です。このうち,問1と問2はどちらか1つ,問3から問12のうちから5つ選択します。
全部で11分野あるのですが,この分野を全部検討する人は意外と少なく,だいたいの人はなんとなく選ぶ問題を決めています。
基本情報技術者試験の延長線上だと,テクノロジ系の問2,4,5,6,8,9という形でとるのが,最も一般的な感じです。
アルゴリズムが苦手な人は経営戦略,という手もあります。
ですので,経営戦略を考える人は結構いるのですが,あまりマネジメント系を取ろうとする人は聞きません。
プロジェクトマネジメントはなじみがあるのか,選択する人は結構いますが,他の2つは検討もしてない感じです。
あと,組込みシステム開発も,あんまり眼中にない人が多いみたいです。
どの分野を選ぶか,というのは,別になんでもいいのですが,最初から思い込みで決めちゃうと,もったいないです。
一度全部解いてみて感触をつかむと,自分の向き不向きも見えてきますし,ひょっとしたら将来進みたい分野も見えてくるかもしれません。
そんな意図から,わく☆すた公開セミナーの応用情報技術者試験対策では,午後分野は全部ひととおり学習します。
全部やることで,午前対策も兼ねられますし,視野がとっても広がるのです。
どの年度でもいいので,一度,午後問題を問1から問12まで全部,解いてみてください。
解答解説の詳しい過去問集などを併用すると,解くこと自体が,結構勉強になると思います。
例えば,EVM(Earned Value Management)などは,午前で用語だけ覚えていると忘れやすいですが,一度平成22年春試験の午後問9を解いて,実際にEVMを体験してみると,イメージがつかめてよくわかります。
「非機能要件」という言葉も,ただ覚えるよりも平成23年特別試験の午後問4を解くと,具体的にどんなものが非機能要件かがわかって,頭に残ります。
システム監査などは特に,「やってみると向いてる」人も結構多いと思います。
アルゴリズムも,昔の一種やソフトウェア開発技術者に比べてだいぶん易しくなっていますので,苦手意識を持っている方も,一度解いてみるのをおすすめします。
午後問題の選択を固定化させる前に,一度全部解いて,感覚を確かめていきましょう。
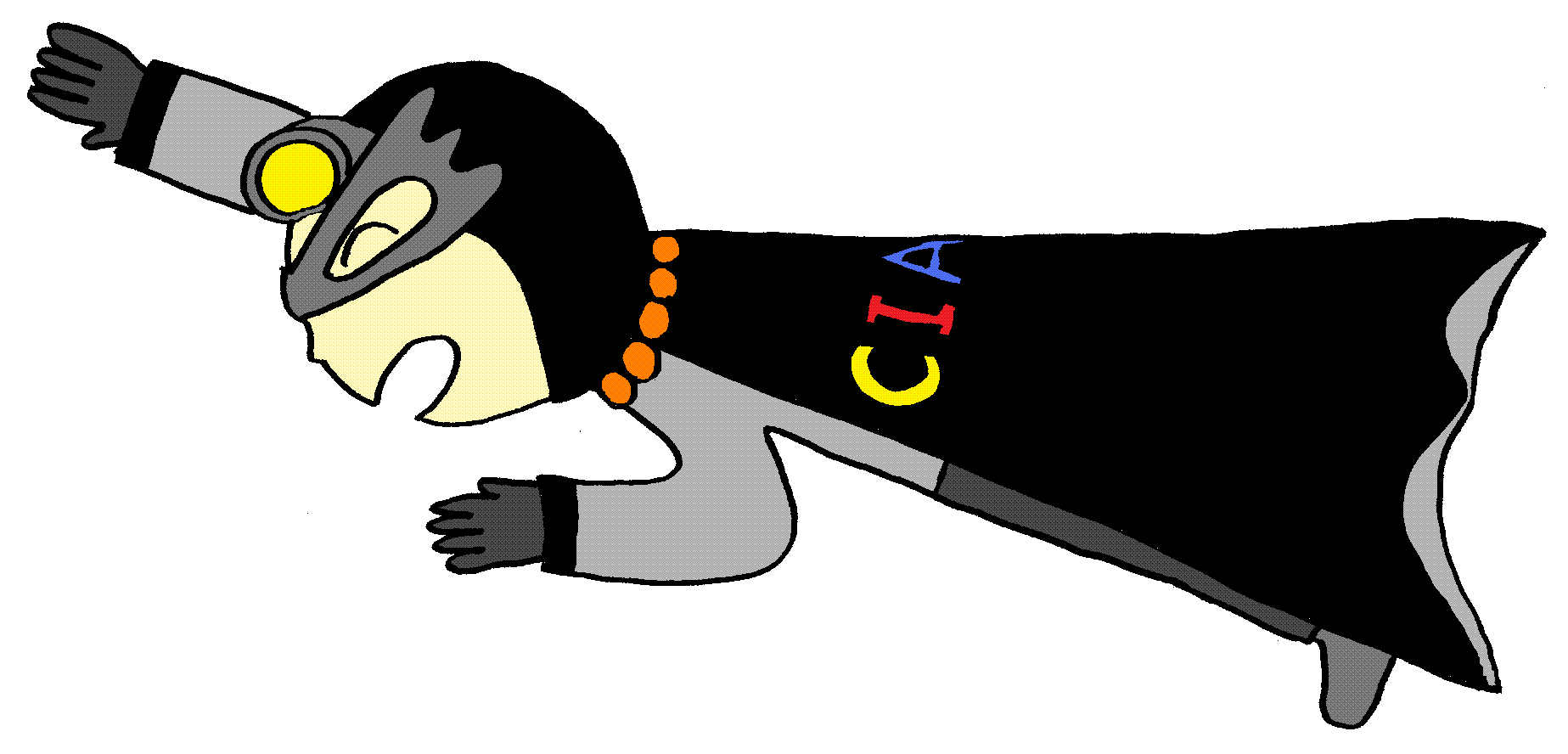
試験センターのページで,「高度試験の一部免除申請番号の照会について(平成23年度特別試験を受験された方へ)」ということで,「高度試験 一部免除申請番号照会」ができます。
ためしにやってみると,一部免除申請番号は「SC20110400143」でした。
これは合格証書番号と同じ形式に見えるので,多分これが合格証書番号でしょう。
ということは,SC-2011-04-00143という風に区切れますので,特別試験でも,受験月は4月の扱いのようですね。
となると,合格証書を見ても,特別試験だとはわからないかもしれません。
合格証書の発送は,すべての試験区分で8月21日(日)の発送予定です。
基本情報技術者試験,ITパスポート試験に合格された方も,まだ届いておりませんので,もうしばらく待ちましょう。
ちなみに,8月21日(日)には,わく☆すた公開セミナー「情報セキュリティスペシャリスト対策 3回コース」「応用情報技術者対策 3回コース」の2回目を開催いたします。
こちらは,実は2つとも,同じ内容で,実際にやることは応用情報技術者試験の午後対策(1)です。
応用情報技術者試験の午後対策は2回目,3回目の2回で行うのですが,午後対策(1)ではセキュリティに関連するットワーク,セキュリティ,情報システム開発,データベース,システムアーキテクチャ,システム監査の6分野について学習します。
応用情報技術者試験の午後対策に特化して学習したい方は,3回コースの2回目,3回目で午後のすべての分野をひととおり学習しますので,こちらにご参加していただければ,午後対策は網羅できます。
情報セキュリティスペシャリスト試験を受験される方で,ネットワークやシステム開発など,セキュリティ以外の分野で不安を感じる方,またはセキュリティについても基礎力に不安があるかたには,この2回目の受講をおすすめします。
情報セキュリティスペシャリストは,実はセキュリティ以外の比重が半分以上あります。システム開発の知識も必要ですし,ネットワークについてはそれなりに深く知っておく必要があります。セキュリティだけ勉強していても受からないのが現実です。
「応用情報技術者試験レベルはOK」という情報セキュリティスペシャリスト受験者向けには,3回目の「情報セキュリティスペシャリスト応用・過去問」で,1日集中で情報セキュリティスペシャリストレベルの学習を行います。
前回の,「2011春 情報セキュリティスペシャリスト対策 1日集中コース」のリニューアルになりますので,すでに応用情報技術者レベルの基礎力がある方は,こちらがおすすめです。
情報処理技術者試験は,専門分野だけ知ってる専門バカだと解けないような問題がたくさん出てきます。
情報技術は,単独で存在するものではなく,協調しているものですので,当たり前なのですが,スペシャリストと言っても,周辺分野の学習は,ひととおり行っておく必要があります。
必要な知識を身に付けて,秋の合格に向けて進んでいきましょう。
追伸
わく☆すた,中の人のけんけんです。
今回美月さんが紹介したセミナーは全て東京での開催になります。
なので,遠方で参加できない方,スケジュールが合わなくて参加できない方は,全てDVD化しますので,ちょっとお待ち下さい。今回の合格祝いで,PCをSSDキャッシュ化しようと目論んでおりますので,少しは早くDVD化できる“かも”しれません。
(自分のPCは巨大な動画データを扱うので,全SSD化は難しいのです。)

昨日が合格発表だったのに,気がつけばもう,試験まであと2ヶ月です。
2ヶ月,というと,高度区分の勉強をゼロから,というには少し厳しい時期だと思います。
ただ,再受験だったり,今までの蓄積がある場合には,十分間に合う可能性はあります。
特に今回,応用情報技術者や情報セキュリティスペシャリストでぎりぎり不合格だった方は,リベンジまで2ヶ月,と考えるとちょうどいい期間だと思います。
自分の答案と解答例をじっくり見比べて,なぜ合格点に達しなかったのか,その理由を感じてみてください。
それがつかめれば,次回の合格に向かって,着実に進むことができます。
今回,何度も受験されていて,やっと合格しました,というご報告を何件もいただきました。
苦労すればした分だけ,合格したときの喜びはひとしおだと思います。おめでとうございます。
中には,テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)の初回から受験されていて,やっと情報セキュリティスペシャリストに合格した,という方もいらっしゃうました。
トータルで8回目,あきらめずに受け続けた,ということだけでも素晴らしいと思います。
今回の特別試験は,秋試験までの間がありません。
不合格で傷ついた心を癒してそれから勉強。。。ということがやれればベストなのですが,その時間はあまりありません。逆にいうと,悔しさをバネに勉強するなら,時間も短いですし効率的に学習できると思います。
あと,高度午前1の対策は,なるべく急いで行いましょう。
今回合格された方は,高度午前1の免除はあと2年間継続されますが,残念ながら不合格だった場合には,秋試験は午前1からの受験になります。
試験センターの「統計情報 得点分布・評価ランク分布」から計算してみると,特別試験の午前1の突破率は,低い順に並べると,
情報セキュリティスペシャリスト 50.4%
応用情報技術者 51.0%
プロジェクトマネージャ 53.0%
エンベデッドシステムスペシャリスト 60.8%
データベーススペシャリスト 64.0%
システム監査 64.6%
でした。以前,「午前を侮らない」でも書きましたとおり,平成22年秋の応用情報技術者午前の突破率は37.4%,高度午前1の突破率は,SC 37.1%,NW 42.1%,SA 54.2%,ST 55.7%,SM 32.9%でした。
こちらに比べるとだいぶん高くはあるのですが,半分近くは午前1で足切りに合っている現状です。
毎回,秋の方が難易度が高い傾向があるので,しっかり準備しておきましょう。
ちょうど,わく☆すたの「2011秋 高度午前1・応用情報午前対策 1日集中コース」の収録DVDができあがりましたので,よろしければこちらもご活用ください。
秋試験の申し込みも,8月29日(月)までと,あと少しです。
試験に向けての状況も定まりましたし,秋に向けて,焦点を合わせていきましょう。

取り急ぎ速報です。
本日,8月15日(月)正午に,応用情報技術者及び高度各区分の合格発表が行われました。
「合格者受験番号一覧」で,合格者の受験番号一覧が見られます。
こちらは,正午きっかりに更新されたようで,番号を確認できました。
とりあえず,情報セキュリティスペシャリスト試験,自分の番号はあったので,ホッとしてます。
「成績照会」の方は,まだちょっとつながりにくいみたいです。
携帯サイトの方が,通常はつながりやすいので,こちらも試してみてください。
成績照会では,午前1が98.60点,午前2が100.00点,午後1が72点,午後2が92点でした。
午後1はマネジメント系の問3で,「移動中は肌身離さず持つ」を技術的問題と読み違えたところが痛かったです。
やっぱり,情報セキュリティスペシャリストは,問題文を正確に読むところが一番大切で,そして難しいですね。
ちなみに,応用情報技術者20.6%,プロジェクトマネージャ13.3%,データベーススペシャリスト18.2%,エンベデッドシステムスペシャリスト16.2%,情報セキュリティスペシャリスト13.9%,システム監査技術者14.5%でした。データベーススペシャリストが問題の難しさに比べて,予想外に高いですね。
合格された方,おめでとうございます。
また残念ながら不合格だった方も,次の試験はもうすぐです。
あと2ヶ月,秋の試験に向けてスパートしていきましょう。

今年は大事をとって帰省せず,お盆も秋葉原にいる美月です。
ここ数日の秋葉原は,コミケ開催中だからか,いつもにも増して賑わってます。
みんな楽しそうでわくわくしてて,とってもいい感じです。
というわけで,今年のわく☆すたはお盆休みはなく営業してます。
夏休み,勉強してみようかな,というかたは,いつでもどうぞ。
試験センターから,「合格証書の発送について」と,「平成23年度特別試験の午前Ⅰ通過者番号通知書の発送について」が発表されました。
合格証書や午前1通過者番号の発送は,8月21日(日)の予定のようです。
また,結果を見てから秋試験の申し込みをする場合には,合格証書などが到着する前に,照会画面で番号が確認できるようになる予定です。
ちなみに,午前1通過者番号は,高度区分の試験を受けるときには,どの試験区分でも使えます。
別に,情報セキュリティスペシャリストの午前1通過者番号で,ITストラテジストを受験しても午前1免除になります。一度受かれば2年間有効ですし,春秋,どちらの試験でも使えますので,自分が一番受けたい試験区分で使ってください。
私はいつも午前1から受けるのですが,午前1の試験には,この,「免除だけ狙ってる」と思われる人が,結構大勢いるように感じます。というのも,午前1の時だけいて,午前2の時にはもういない,という人が,結構いっぱいいるからです。
個人的には,午前1だけで5,100円って,もったいない気がするのですが,戦略としてはありだと思います。
合格発表を見てから免除申請をして申し込みする予定の方は,照会してからすぐ申し込みできます。後になると忘れがちなので,関心が向いてるうちに早めに申し込みをするのがおすすめです。
また,すでに秋試験の申し込みをしている人が,後から免除申請を追加することも可能です。
郵送の場合,何も問題がなければ1~3日で大体届きますので,8月24日(水)ぐらいには届いているとは思います。締切は8月29日(月)ですので,何も問題なければ郵送で届くのを待ってでもいいとは思います。
ただ,郵送は,思ったより時間がかかることもあります。
特に,「合格証書」は,簡易書留で届きますので,自分で受け取る必要があります。
昔,一人暮らしをしていて仕事が忙しいとき,合格証書を受け取りに行けなくって苦労したことがあります。
結局,保管期限ぎりぎりになって,不在通知を持って郵便局の夜間窓口に取りにいきました。
今回は,そんなことをやっていると,締切がすぎてしまいますので,注意が必要です。
ちなみに,午前1通過者番号の方はハガキなので,受け取るのは楽だと思います。
個人的には,大変でも合格証書の方がいいですが。^^;
あと,転居された方もご注意ください。
転居届を出しておかないと,うまく届きませんし,再送してもらう場合には,費用がかかります。
暑い日が続きますが,無理のないよう,勉強も仕事も楽しんでいきましょう。

お久しぶりの美月です。
目まいがして体調を崩して,先週末から寝込んでおりました。
やっと復活してきましたので,今日から仕事に復帰してます。
中小企業診断士の1次試験も,結局会場まで行けずじまいでした。
勉強不足だったので,行ったところで合格はできない,とわかっていた分,敵前逃亡になってしまって悔しいです。
今は,できない自分,ダメな自分を逃げずに味わいたいと思います。
今日,特別試験の応用情報技術者及び高度区分の解答例が発表されました。
もうそろそろ,自分の答案のことは忘れた頃だとは思いますが,今後に向けて復習しておくのもおすすめです。
改めて解答例を見て感じましたが,応用情報技術者やデータベーススペシャリストの午後は,解答が合ってるかどうかって一目瞭然で,あいまいなところはあんまりない気がします。それに対して,情報セキュリティスペシャリストの午後や,論文系の午後1などは,合ってるかどうかの判断が微妙なものも多いですね。
曖昧な問題ほど,「出題者の意図を見抜く」のは大変な感じです。
今年は,解答例発表も遅いですし,本試験を解説した問題集も,出るのが遅そうですね。
私自身も,応用情報技術者とデータベーススペシャリストの解答解説を書く仕事はあるのですが,いつもの年よりもだいぶん,後ろ倒しのスケジュールです。
お盆の暑い季節ですが,今年はいつもと違って,情報処理技術者試験関連でも,いろんなイベントが目白押しですね。
今回は,解答例発表から合格発表(8月15日正午)までは3日しかないので,あと少しだけ,結果を待ちましょう。

わく☆すた,けんけんです。美月さんが体調不良の為,飛び石で記事を書いております。
さて,今日のお題は「IT用語3分間スピーチ」についてです。
ここで,「IPsec」について3分間語って下さい。
と突然言われたら,3分間語り続けることができますか?
「IPsecとは,IPパケットを暗号化するプロトコルで,IPデータグラム部分を暗号化し通信を行う。・・・」
などと説明が始まると思うのですが,問題はその先です。
もし言葉に詰まったら,なにが詰まったのでしょうか。「喉まで出かかっているのに。」と出かかっている言葉はなんでしょう。その出てこない言葉が,自分の弱点になっていると思います。
もし本試験で「IPsecについて100字以内で説明せよ。」なんて問題が出たらアウトですよね。
なので,今のうちに練習しておくのです。
学習には,インプットの学習とアウトプットの学習があります。どっちが大事かと言えば,アウトプットの学習の方が大事です。(言い換えれば問題演習です。) なぜなら,試験で合格するためには,白紙の解答用紙に正解を書かなければ合格しないからです。
そこで今回お話するのが,「IT用語3分間スピーチ」です。スピーチと言っても人前でスピーチする必要はありません。1人,机に向かいながら,A4用紙に図を書きながら話しても良いでしょう。自分がしっかり身につけたいと思っている分野の用語について,3分間話し続けます。
もし,話に詰まったら,どの部分が話せなかったのか,振り返って確認します。つまった部分が弱点とすぐにわかります。やり始めの頃は,詰まりまくりでいやになってしまう事もあるでしょう。けれども,話せないって事は,その問題が出題されたら解けないって事と同じです。
今は沢山間違えてOKです。本試験で間違えなければいいだけです。
3分間話せるようになったら,マインドマップなどにまとめておきましょう。自分専用の参考書のできあがりです。
今日は,この辺で。
追伸
先日開催した,「2011ネットワークスペシャリスト対策 3回コース1回目」のDVDができあがりました。
最新のNWセミナーDVDは,こちらです。

わく☆すた,けんけんです。昨日に引き続き登場です。
最近思うことは,自分では普通にあたりまえだと思っていることが,他の人にとっては普通じゃないことがよくあるなぁってことです。
例えばプロジェクターの解像度。
実は,今日,事務所を貸し出す予定があるので,プロジェクターを購入したいと友人から相談を受けたのです。弊社のセミナーで使っているのがEPSONで使い勝手が良いので,同系統の機種を進めました。けれども返ってきた返事が,解像度がそんなにいらないかなぁとSVGA(800×600)の機種を聞いてきたのです。
自分が“普通に”思っていることは,最近のパソコンの解像度は上がっていて,XGA(1024×768)はあたりまえで,モバイル用のノートPCでも,WXGA (1280×800)以上の解像度を持っている機種も出てきています。上位機種では,フルHD(1920×1080)があたりまえです。
なので,SVGAの解像度のプロジェクターでは,画面の一部分しか投影できなくなってしまいます。
SVGAのプロジェクターは最下位の機種で価格も割安ですが,こんな落とし穴があることがわかるのです。
(なので,最低でもXGAの機種にしてねと,返事しました。)
さてさて,プロジェクターの話は置いといて,これから皆さんが受験しようとしている情報処理技術者試験の種目は,合格することが“普通”でしょうか?
たぶん,合格だと閾値が高いので,そう思える人は美月さんぐらいで,あまりいないと思うので,言い方を変えてみます。
各種目の出題分野の中で,どれだけ自分にとって“普通”に理解している分野があるでしょう?
“普通”に感じている分野が多いほど,合格に近づきますし,少ない,もしくはわからない人ほど,合格からほど遠いでしょう。
なので,わく☆すたでは,「合格への道しるべ」と名付け,合格に必要なことを網羅して理解できるようなDVD教材を作成しています。
情報処理技術者試験に合格するためには,出題分野の各分野をどれだけ自分が“普通レベル”と認識して理解しているかどうかだけです。
だから,問題演習で間違えた部分はチェックして,繰り返し正解するまで演習する必要がありますし,問題を解くレベルまで行っていないなら,その分野を学習する必要があるのです。
千里の道も一歩から。合格へは一つの理解からです。
今日は,このへんで。

わく☆すた、けんけんです。
美月さんが体調不良の為、ピンチヒッターで登場です。
8月5日に、基本情報とITパスポートの合格発表がありました。高度系は15日なので、あと一週間ですね。受験した一人は、ドキドキして発表を待っていると思います。
さて、あなたはどうして試験を受けるのでしょう。
高度系ともなると、かなり勉強する内容も増えますし、内容も名前に劣らず高度になってくるので、理解や覚えるにも時間がかかってきます。
貴重な人生の時間を使って、受験する理由はなんでしょうか。
自分の場合、受験しはじめの頃は、食品会社の情報システム部にいたので、年齢が30歳を過ぎ、将来に不安を感じたのが一番の理由でした。
今まで勉強して、試験に合格して思うことは、可能性の広がりです。また、ここまでこれたのは、コンピュータが好きだったことがとても大きいです。
受験対策をしていて、どうして試験を受けるのか不思議に思う人に出会うことがあります。
高度区分の試験対策は、それなりに高度な内容と分野の広さがあるので、結構大変です。
にもかかわらず、この道に進むのはなぜでしょう。
正直、試験勉強が楽しくないならば、自分が楽しいと思える分野に時間と労力を割いた方が幸せだと思います。
なぜなら、時間は有限だから。そして、自分が楽しいことをやっていると、その周りの人たちも幸せが伝搬してゆくからです。
わく☆すたは、高度情報処理技術者試験に合格したい人を応援します。
けれども、もし、あまり試験勉強に情熱を感じられない時は、自分の立ち位置を振り返ってみることをおすすめします。
もしかしたら、今、試験対策をすることが最優先でないこともありえます。
そんな時は、少し寄り道をすることが近道になることもあるでしょう。
合格発表の直前のこの時、ちょっと立ち止まって、自分の向かう方向を見るのもいいと思います。
今日はは、このへんで。

本日8/5(金)正午,ITパスポート試験と基本情報技術者試験の合格発表が行われました。
ついつい気になるので,正午には結果を確認しに行きました。
合格者受験番号一覧で,合否はすぐに確認できたのですが,成績照会はなかなかつながりません。
携帯サイトだとさくっとつながったので,点数はそちらで確認しました。
午前97.50点,午後90.30点,結構間違えてしまいましたが,とりあえず9割は確保できたので良かったです。
合格率は,「プレス発表 平成23年度特別情報処理技術者試験(ITパスポート試験、基本情報技術者試験)の合格発表について」によると,ITパスポートが44.8%,基本情報技術者が24.7%,去年(平成22年春)よりはどちらも若干高いです。
受けた感じ,いつもより易しかった気はしないので,私たちみたいなダブル受験組の影響かな,と感じています。
ただ,基本情報技術者は学生の方が合格率高いですし,あんまり影響はないかもしれないです。単純に,勉強する期間も延びましたし。
というところで,基本情報技術者試験にはじめて合格された方,おめでとうございます。
受かってホッとされてる方におすすめなのが,そのまま連続での応用情報技術者試験の受験です。
私が今まで研修で教えてきた感じでは,応用情報技術者試験に一番受かりやすいのは,「直前に基本情報技術者試験に合格」した人たちです。
覚えたことを忘れないうちに再復習するので,記憶も定着しやすいのだと思います。
逆に,ここで一息ついてしまって,2~3年以上放っておいたりすると,また1から勉強し直す感じになりますので,大変です。
基本情報技術者試験の勉強をちゃんとやっていれば,応用情報技術者試験の問題も,半分ぐらいは解けます。
アルゴリズムを解くのには,練習して慣れる必要があるのですが,基本情報技術者試験の勉強をしていれば,それも慣れているはずです。
最近は,応用情報技術者試験のアルゴリズムはかなり易しくなっていますので,基本情報技術者試験からのステップアップも,それほど敷居は高くないと思います。
特に,テクノロジ系を中心に午後問題を選択するなら,プログラミング言語がないぐらいで出題範囲はほとんど同じですので,今までの勉強が活かせます。
連続して取得すると,すごく「自分ができる」気になるので,その後の勉強も勢いがつきます。
高度区分に連続して合格するような人は,基本情報技術者試験の後にすぐ次を受験した人が多いです。
個人的には,合格発表を見た勢いでそのまま,応用情報技術者試験の参考書を買いに行っちゃう,ぐらいが,エネルギーロスがなくっておすすめです。
受かった時の勢いとかパワーは,そのまま次へ進むための原動力になります。
これは,普段は高度区分を受験している人たちにも言えると思います。
合格,というのは,やっぱり気持ちがいいですし,やる気もアップします。私も,「さすがに落ちないだろう」とは思いながらも,受かるとやっぱりうれしいです。
秋の試験の申し込みは,すでに始まっています。
せっかく合格した,その嬉しい気持ちを原動力に,次のステップに向けて進んでいきましょう。

今日,ひょんなことから,「自己採点した答案をチェックする」という仕事をやってました。
そして,自己採点って,人によってものすごくばらつきがあるなぁ,というのを,改めて感じました。
ある人は,解答例からちょっとでも違うと,×にしていました。
私から見れば同じことを言ってるように見えるのですが,「なりすましによって」の一言がないとか,そんな一言がないぐらいで,いきなり×と判断している感じです。
そんな風に採点しておいて,「点数は全然合格レベルじゃない」と思ってる人がいます。
普通に採点官が採点したら,十分合格レベル,という感じです。
こういう人は,自分に厳しい感じなので,意外と合格率は高いと思います。
逆に,「え?なぜこれで○」ぐらいの,疑問に感じるぐらいの答案で,○にしてる人がいました。
全然違うことを言っていても,「暗号化」が合ってれば○,ぐらいの勢いです。
何を暗号化するのかがポイントなのに,ただ暗号化していれば○,というのは,採点が甘すぎです。
こういう答案は,「結構できてたのに落ちた」と言う人に多いです。
「解答例と大体同じようなことを書いているのに」といっても,他の人が見たら全然同じに見えない答案,というのも結構存在します。
情報セキュリティスペシャリストは特に,この手の振れ幅が大きい気がします。
希望的な解釈によっては,明らかな誤答でも正解なんじゃないかと感じさせるようなあいまいさが,この試験にはあります。
といっても,何でも正解になるわけじゃなく,問題文の前提や,情報セキュリティの考え方によって,正解の幅は狭まってきます。
自分の答案と解答例を見比べて,「これで点数になるかどうか」を見極める練習をしてみましょう。
最初のうちは,「厳しすぎる採点」ぐらいがおすすめです。
実際,厳しすぎる採点をする人は,そのうち,「どう書けば正解か」ということを学んでいきますので,成長が速いです。迷ったら×,ぐらいの姿勢でもいいと思います。
今,勉強するうちから,「これくらいの答案でいいか」と妥協してしまうと,成長が止まります。
違った部分を直視する,というのは,正解を導き出す方法を知る上で,不可欠なのです。
人に採点してもらう,という手もあるとは思います。
ただ,自分で採点できる目を身に付けておくと,本番で正解に近い答案を書くのに,すごく役立ちます。
問題演習を行うとき,採点を厳密に,細かくやって,何が正解なのかを判断する練習をしてみましょう。
その判断自体が,とてもいい勉強になると思います。
補足
わく☆すた,けんけんです。(久しぶりに,ちょこっと登場です。)
自分は,勉強し始めの時,甘い採点で受験しては落ちまくってました。
あまり自分には厳しくない方なので(^^;),微妙な解答の場合には,「×」ではなくて「△」印を付けて,2回目に解く時にわかるようにしておきました。
すると,甘く採点した時はもう一度同じように間違えました。けれども,厳しく採点した時は正解を答えられることが多かったです。そうすると,合格率も上がってきました。
なので,「×」か「○」かだけではなくて,微妙に感じる時は「△」を付けて,もう一度演習することをおすすめしたいと思います。

試験問題の解答を書くとき,「正しい解答を書こう」と頑張ると,かえって書けなくなることがよくあります。
企業研修などでよくあるのが,記述式の解答を書くときに,固まってしまって何も書けなくなる人。
あと,論文を書き始めるときに,書いては消しを繰り返して,設問アで止まってしまう人。
そんなときには,「間違える練習^^」ぐらいに思って,とりあえず書いてみるのがおすすめです。
勉強するときの問題演習では,いくら間違えてもかまいません。
最悪,全部間違えていても,そこから間違えた原因を分析して,次から答えられるようになれれば全然OKです。
勉強のときには,いろいろ転んでみて,うまく間違いの経験を積みつつ,段々正解が書けるようになる,というのが王道です。
私が昔,ネットワークスペシャリストを受験してた頃のノートが今も残っていますが,こちらはもう,間違いだらけです。知識がなかったり,問題を読み間違えていたりして,ほとんど間違いだらけなものを,真っ赤になる感じで採点しています。
そこから,足りない知識を調べたりして追加して,ひととおり理解したら1回目が終わりです。
そして,時間をおいて2回目でもう一度解いてみます。1回目よりはだいぶんマシではあるのですが,やっぱり間違えます。そうして,繰り返し間違えるところは自分の弱点なので,そこを重点的に補強します。
3回ぐらい回せば,だいたい同じような間違いはしなくなってきます。
こうやっていっぱい間違えておくと,本番では,「自分の間違えそうなポイント」も見えてきます。
「あ,この計算問題は単位を間違えそうだから気をつけよう」とか,「なんか問題文にヒントが隠れてそうだから問題読み直そう」とか,よくわかるようになります。
そうすると,ミスも減りますし正答率が上がります。
最初からうまくできる人なんていません。
本番で真っ白になったり,適当な回答を埋めたりする前に,あらかじめ間違いを経験しておきましょう。
そうすれば,本番では間違えずに,うまく対処できるようになると思います。

平成21年度に試験制度が変わってから,論文の形態が変わりました。
論文試験には設問がア,イ,ウの3つありますが,昔は,設問イと設問ウがまとまっていて,設問ウは少し書くだけでもなんとかなりました。
それが,設問イと設問ウを別々に聞かれるようになって,設問ウもちゃんと600字以上で書くことが必須となりました。
例として,平成20年秋のシステムアナリスト試験午後2と,平成22年秋のITストラテジスト午後2を比較してみます。
昔のアナリスト時代の午後2は,設問ウはほとんど「評価と改善」で,定型文でもなんとかなるぐらいの付録的扱いでした。それが,ストラテジストになって,設問ウが「工夫した点」だったり「どのようなシステム化構想としたか」だったりと,バラエティに富んできています。
ですので,定型文(「評価としてはおおむね良かった」とか)を用意してテクニックで切り抜ける,ということは,やりにくくなってます。用意した論文がそのまま使える可能性も少なくなってます。
でも,それで,論文を書くのが大変になったわけではないと思います。
私が今まで試験会場で論文を書き,そして合格した体験から感じるのは,「論文が書きやすくなった」ことなのです。
昔は,問題の聞き方も曖昧でしたし,何を書けばいいのか迷うところも多く,字数を埋めるのに苦労もありました。
でも,今の問題だと,設問でバラエティに富んだ聞かれ方をされる分,その「設問で聞かれている内容」について答えていると,普通に字数が埋まります。
問題文を読んで,書いて欲しい内容の意図を読み取って,そこから自分の経験やネタのストックからあてはまるものを見つけていきます。
そしてそれを,設問で問われている形で,具体的に記述していくことで,だいたい字数が埋まるようにできている感じなのです。
設問イの最低字数が800字と少なくなったことも大きいと思います。
設問イ,設問ウでそれぞれ別のことを問われることによって,1つ1つの内容について,具体例をいっぱい記述する必要がなくなりました。
基本的に,1つの論文で具体例を2つぐらい考えて,それを設問ア,イ,ウでうまく話がつながるように前振りも含めて書く,というぐらいで,設問イの800字,設問ウの600字は埋まります。
つまり,聞かれている内容がはっきりしていて,書く分量もある程度想定されており,ちょうどいい字数で書き終われるように問題が設計されているようなのです。
ですので,「字数が埋まらない」という時には,書く内容が少なすぎるだけだと考えられます。ですので,問題文で聞かれている内容から具体例としてもう1つ加えるなどして,内容を追加する必要があります。
字数を埋めるために,よけいなことを書いたり,同じことを繰り返し言ったりしても,内容が足りないので不合格,ということになります。
準備論文を書くときには特に,「とにかく字数を埋める」ことよりも,「きっちり内容を満たす」ことを意識して論文を書いてみましょう。書くべきことを書ききる意識で時間制限なしに書くと,字数制限の上限に近い感じになると思います。本番ではそこまで書く必要はありませんが,最低の字数を埋めるぐらいの内容は必須です。
情報処理技術者試験は付け焼き刃が効かないように,そして本来の実力が測りやすいように曖昧さを排除する方向で進化しています。
論文を書くときには,しっかり問題文と設問を読んで,「字数を埋める」のではなく,字数を満たす内容を考えて,それを書ききるようにしましょう。

今日から8月ですね。
いつもの年なら,試験結果はとっくに出ていますし,申し込みも締切が近い頃です。
秋の試験に向けて,徐々にペースアップしていく頃だと思います。
ただ,今年は8月には,行事が目白押しです。
「平成23年度特別試験 合格発表スケジュール」によると,基本情報技術者・ITパスポートの合格発表は今週末8/5(金)の正午,応用情報技術者・高度区分の合格発表は8/15(月)の正午です。
そして,試験申し込みの締切が,インターネット個人申し込みでは8月29日(月)20時,インターネット団体申し込みは8月23日(火)20時,郵送の場合は8月19日(金)です。
試験日が10月16日(日)ですので,応用情報技術者・高度区分の合格発表8/15(月)からだと,2ヶ月(62日)しかありません。
手続きや合格発表が遅くても,試験自体は待ってくれないので,計画的に,なるべく前倒しに準備を進めていく必要があります。
特に,高度区分受験者で,今回で午前1免除が切れる人は,2ヶ月で午前1からの準備は厳しです。
午前1の勉強は,午後の勉強でも意外と役に立ちますので,今のうちにひととおり復習しておくのはおすすめです。
また,応用情報技術者試験に受かって,最初に高度区分を受験,という場合も,2ヶ月だと少し厳しいと思います。
今回に限っては,応用情報技術者試験に受かりそうな希望を持ってる方は,合格発表前に高度区分の勉強をスタートさせるのが得策です。
個人的には,今週末8月6,7日に中小企業診断士の一次試験があるのですが,他の試験と掛け持ちする場合には,時期的な調整も必要だと思います。
今年は節電や震災の関連で,夏休みの取り方が例年と違う方が多いと聞きます。
勉強するのに,暑くて勉強しづらい,ということもあると思います。
夏バテしやすい時期なので,無理に頑張る必要はないです。
ただ,昔,「夏を制するものは受験を制す!」とか,入試の頃には言ってたのですが,夏,特に8月の過ごし方というのは,合否にかなり影響します。
なんとなく過ごしてるとあっという間に過ぎてしまう8月,やる必要のあることをしっかり見つめて,見通しを立てていきましょう。

本日,わく☆すた公開セミナー「高度午前1・応用情報午前対策 1日集中コース」及び「応用情報技術者対策 3回コース」「情報セキュリティスペシャリスト対策 3回コース」の1回目が無事終了しました。
ご参加いただいた皆様,ありがとうございました。
今回の講座の収録は無事終わりましたので,編集が終わり次第DVDを発売いたします。1週間後ぐらいの発売予定ですので,DVDで学習したい,という方は,もうしばらくお待ちください。

私が長年,友人たちや受講生さんたちを見ていて感じるのは,知識や実力以外にも,性格的なところで,受かりやすさ・受かりにくさってあるな,ということです。
ポジティブで,明るくって誰からも好かれるタイプ,っていうのは,クラスに一人いると和んでいいのですが,そういう人はめったに受からなかったりします。
特に,教室でギャグをいって笑いをとるタイプは,頭の回転は速いんだとは思いますが,試験でもギャグに走りすぎて失敗したりすることが多いです。
逆に,「この人は確実に受かりそう」という人は,若干,暗めだったりして,ネガティブな人が多いです。
特に,ちょっと性格が悪そうな,論理的に人を追い詰める厳しい感じの人は,結構受かります。私もそんな,人のこと言えませんが。^^;
高度区分の試験に大量に合格している人に,ネガティブな感じの人が多いのは,偶然ではないと感じています。
勉強するときに,ポジティブに「さあやるぞーーー!」っていう感じの人は,意外と長続きしません。
無理に頑張ると,どこかで必ず,息切れするからです。
黙々と,淡々と,日々1つ1つ積み重ねていく方が,結果的に実力はアップします。
仕事,特にチームプレイ的なものでは,ポジティブな人も大切だと思います。
営業などでは,ポジティブな性格で,ぱっと見で人に好かれる方が,有利な場合も多いと思います。
場を盛り上げるというのも必要なこともあると思います。
でも,試験だと,それは通用しません。
解答用紙に,明るく「これから頑張ります!」「今度飲みにいきましょう。」と書いても,点数にはなりません。
聞かれたことに確実に答えることだけが,求められています。
そして多分,試験だけじゃなく,普段の仕事でも,実はそうだと感じています。
長期的な視点で見たら,多少ネガティブでも,相手の意図を汲んで確実に仕事をしてくれる人の方が信頼されるのではないかと思います。
もちろん,ネガティブになりすぎて,「どうせ自分はダメ」とか,「試験問題のここが気に入らない」とかいうところまでいくと,行き過ぎです。
その場合には,適度にポジティブな方向に向かった方がいいと思います。
ベストな状態は,ポジティブでもないけど,ネガティブでもない,中間ぐらいだと感じています。
試験勉強という観点から見たら,試験自体が若干ネガティブな感じで作られているので,多少ネガティブ寄り,ぐらいがいいのかな,とも感じています。
ポジティブな状態がいいとは限りません。
適度にポジティブとネガティブのバランスを取りながら,淡々と勉強を進めていきましょう。