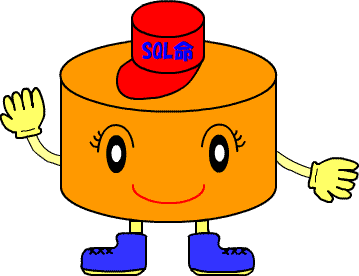「のび太」という生き方
今日は,久しぶりに,これは紹介したいな,という本に出会ったので,紹介したいと思います。
タイトルは,「「のび太」という生きかた―頑張らない。無理しない。」。
7年前の本なのですが,中学生が書いた「読書感想文」が話題を呼んで,再度注目されているらしいです。
最近,今の時代の,21世紀型のリーダーシップってどんな感じかな,っていうのをよく考えてました。
頑張ってみんなを引っ張って,パワフルに先頭を切って動くのは,なんか20世紀型の古い感じがして,あんまりそういうのはやりたくないな,って感じていました。
のび太は,一見,なにもかもうまくいっていない子,という印象なのですが,実は,想像以上に人生を上手に歩んでいる,というのが,この本の主旨です。
実際,のび太は結局,しずかちゃんと結婚して,幸せな将来を手に入れています。
そんな,「のび太が夢を叶えられる理由」を「のび太メソッド」として紹介しているのがこの本です。
例えば,夢の叶え方,のび太メソッドに,「心配なことは,考えない」というのがあります。
のび太は先を見越して考えないので,とりあえずやってよく失敗します。でも,失敗もするけれど,繰り返しやってるうちに成功することもあります。
のび太は,先のことをあまり考えないで,今やっていることに全力を尽くしています。ですので,結果的には,失敗を繰り返しながらも前に進むことができます。
これを「ああしたら,こうなるかも」と心配しすぎて行動できなくなる,というのが私たちにありがちな失敗なんじゃないかと思います。心配しすぎて,自分で自分の手足を縛ってしまうと,何の行動もできなくって,夢を実現することができない,ということになります。
時には,のび太みたいに,失敗してもいいから行動する,というのも大切なんだな,と改めて感じました。
自分がちゃんとできないとか,ダメなやつって思ってしまいがちな人には,この本は特におすすめです。
頑張るだけが道じゃないんだな,と肩の荷が下りると思います。
ぐうたら三昧を続けながら,幸せに生きる道もあります。
のび太はのび太らしく,あなたはあなたらしく,楽しく生きていきましょう。