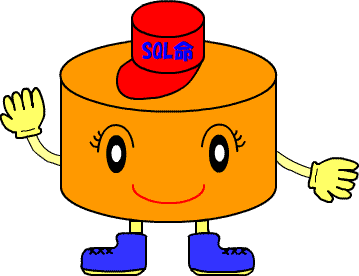エンベデッドシステムスペシャリスト試験
わく☆すた,美月です。
先日,友人から,電子工作マガジンを,いただきました。
「女の子のための電子工作教室」などもあって,結構面白かったです。また,久しぶりに電子工作をしてみたくなりました。
私は,父が電気工事の会社をやっていたこともあり,電子回路などは,結構身近に見て育ちました。
電子工作をしたり,ロボットを動かすプログラミング,などは時々やりますが,大好きです。
仕事では,医療機器製造の会社で,装置用のソフトウェアの開発をやったことがありますが,「ちょっとかじった」という程度だと思います。
というところで,今日は,エンベデッドシステムスペシャリスト試験のお話しです。
テクニカルエンジニア(エンベデッド)試験に関しては,私は,3回目でなんとか取得しましたが,実務の専門家というわけではありませんので,教えられるレベルにはありません。
ですので,一合格者の意見,ぐらいの感覚でお聞きください。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験では,ハードウェア系の問題と,ソフトウェア系の問題が出てきます。
ハードウェア系は,回路設計が出てきたりします。ソフトウェア系は,OSのタスク管理がメインです。
どちらも,他の試験とは全然毛色が違いますし,付け焼き刃の知識だけだと受かりません。
私は,2回受験したときには,参考書を読んで,過去問を3年分解いただけで臨みました。
結構いい線行った気もしたのですが,2回とも午後1で落ちました。
3回目は,対策講座に通いながら,自分で電子回路を作ったり,プログラミングしたりしました。
「チャタリングって,こういうことか!」とか,実体験で理解することができ,楽しく学習できました。
組込系のプログラミングは,目の前で機器が動くので,わかりやすく,とっても面白かったです。
それで,3回目は余裕で合格できました。
受かった後で考えると,テクニカルエンジニア(エンベデッド)試験は,他のテクニカルエンジニア試験に比べて,素直な問題が多かったです。
「素直」っていうのは,あまり奇をてらってない,というか,問題文に複雑なことが書いていないと言う意味での素直です。
ちゃんと読んで,知識を使って問題を解くと,それほど的外れな解答にはなりません。
ですので,できれば自分でやってみるという体験を交えながら,知識をきちんと得るというのが,この試験の合格のポイントになると思います。受験参考書よりは,「組込みシステム開発のためのエンベデッド技術」などで,技術の基礎をかためるのがおすすめです。
あと,この試験は,情報処理技術者試験の高度試験の一つなので,他区分と共通の午前知識が必要になります。
組込系の技術者は,そこで足下をすくわれる,という方が多かったので,ちゃんと共通の午前対策を行う必要はあると思います。
私は,この試験は,苦労もしたのですが,勉強していてすごく面白かったです。
モノを作るのが好きな人だと,かなり楽しめるんじゃないかと思います。
取ったから直接役立つ,というのは組込技術者以外だとあまりないですが,技術の幅を広げる,と言う意味では,おすすめの資格です。