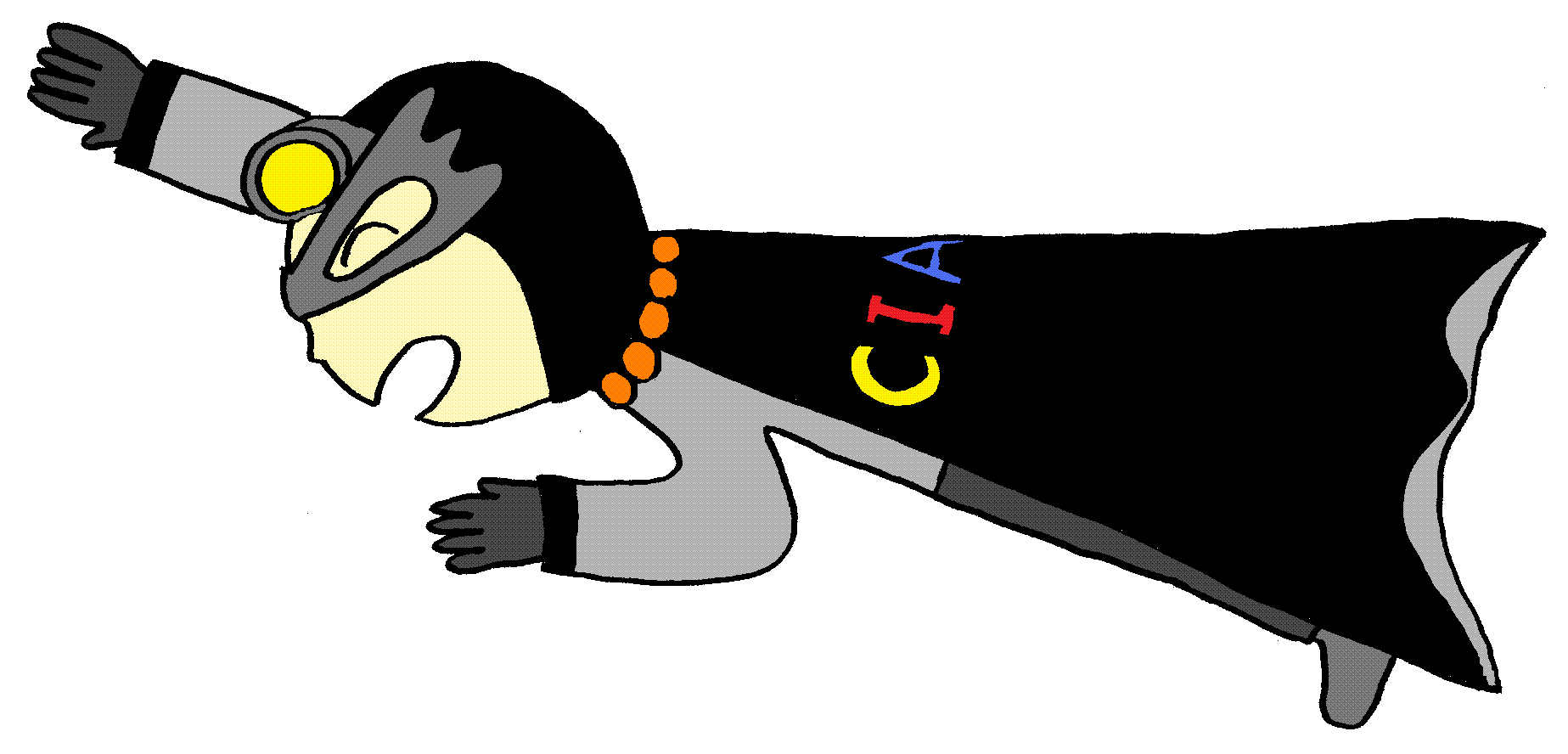昨日は,「スタートアップセミナー 合格への道しるべ」システムアーキテクトを開催いたしました。
ご参加いただきました皆様,ありがとうございました。
論述系の試験に関するスタートアップセミナーはこちら1つだけだったので,いろんな論述系区分を受ける方に集まっていただいて,盛況でした。今後は,余裕ができたらいろいろ手を広げていきたいと思います。
情報処理技術者試験は,ITパスポート以外は,午前と午後の試験があります。
そして,基本情報技術者以外は,午後は記述式です。
午前では,広く浅く,知識や基礎的な理解を聞いてきます。
高度区分では,午前1と午前2に分かれますが,午前1では,広く浅く,すべてのIT分野の知識が問われます。
午後では,専門分野に特化して,深く理解しているか,実務に応用する力があるかどうかを試します。
ですので,実際の技術の応用例や,会社の事例をもとに,詳しく記述することが求められます。
高度区分では,午後2でより深く,実務的な能力を問う問題が出てきます。
午前と午後では,聞かれている内容の質が違うのです。
ですので,基本的に,午前と午後,それぞれで別の勉強が必要になります。
もちろん,共通する内容も多いですし,午前の勉強は午後にもつながります。
でも,片一方の勉強だけしていると,思わぬところで足をすくわれますので,両方を見据えることが大切です。
わく☆すたでは,今回の応用情報技術者試験対策は,今週末に開催する「高度午前1・応用情報午前対策 1日集中コース」と,毎月行う「応用情報技術者午後対策 3回コース」の2つに分けてセミナーを行います。
午前に関しては,全員共通なので,一度全体的に勉強することで,幅広い視野を身につけられると思います。
高度区分を含めて,応用情報技術者以上の場合,「午前レベルの幅広い知識」は,午後の勉強を開始する前に持っておく方がいいです。
情報処理技術者試験の高度区分は,専門分野ごとに分かれていますが,「その分野だけ知ってればOK」という試験ではないからです。
IT分野はそれぞれ,完全に独立しているわけではなく,いろんな分野が絡み合っています。
もともとあった基礎技術が発展していって,応用技術ができているので,基礎技術についてはしっかり学習しておくと,いろんな方面で役に立ちます。
もちろん,すべての分野の専門家になる必要はないのですが,すべての分野について,それなりに知っておくことは,業務をやる上でも,試験問題を解く上でも,応用が利くようになります。
ですので,一度広く浅く,午前1レベルで学んでおくことが必要なのです。
特に,情報セキュリティスペシャリストは,他の分野の知識が合否を分ける,といっても過言ではないほど,セキュリティ以外の要因が大きいです。
また,システムアーキテクトも,アプリケーションエンジニア時代よりも要素技術の比重が高いので,技術的な勉強もひととおり行っておく必要があります。
特に,高度区分を受験する方で,午前1免除でない方は,この時期にはまず,午前1の勉強をして,基礎知識をつけておくのをおすすめします。
その知識が,午前2や午後の勉強をするときにも役立ってきます。
ちなみに,高度の各区分での,午前1免除者の割合を「統計情報 得点(評価ランク)分布」から計算してみると,次のようになりました。
SC 64.0%
DB 65.4%
ES 55.8%
PM 58.9%
AU 67.2%
基本的に,半分以上は午前1免除で,午前2から受ける方の方が多いのです。
午前1が免除でないときには,その午前1に対してしっかり対策を取ることが大切になります。
そして,そこで単なる暗記ではなく,ちゃんと理解しながら学習すると,その後の勉強にも役立つのです。
午前と午後では,求められているものが違うので,それぞれに対策を行う必要があります。
まずは午前から,合格を確実にしていきましょう。