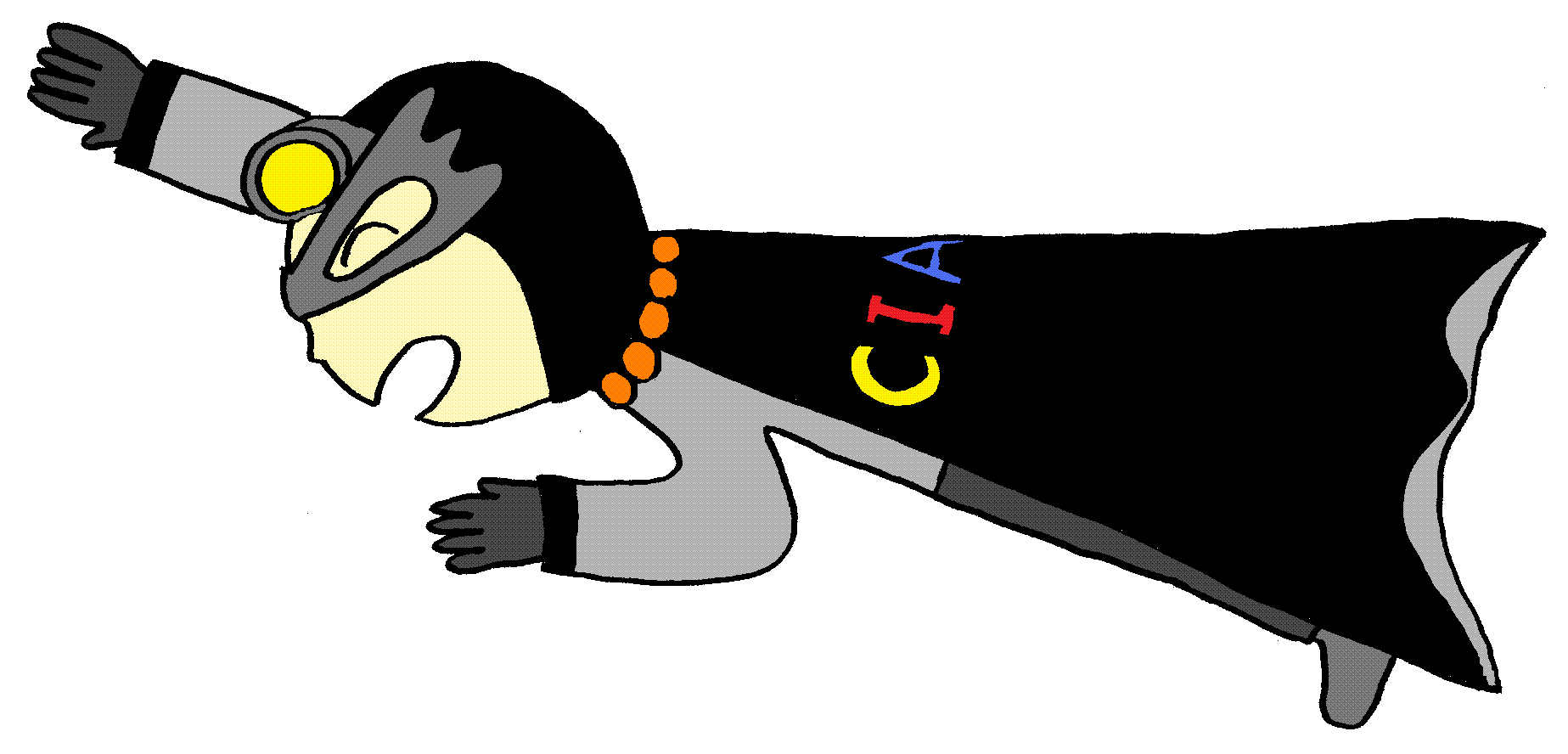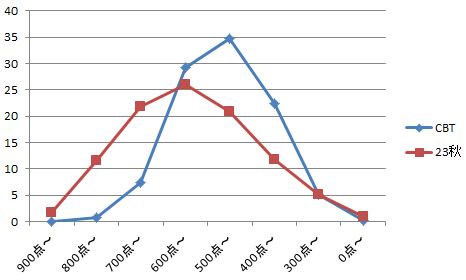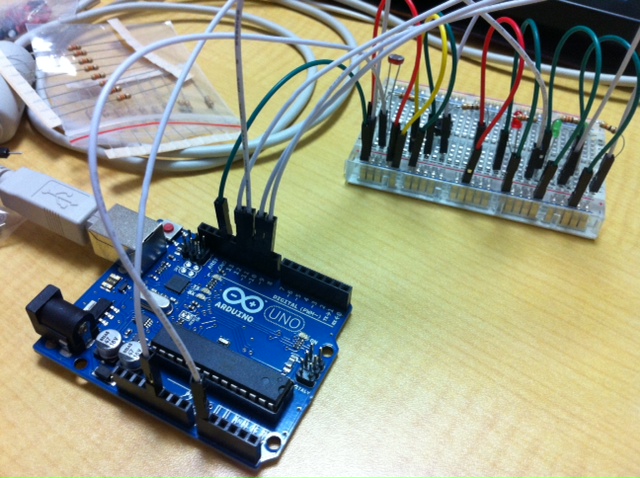2012年05月30日
昨日に引き続き,試験範囲変更ネタです。試験要綱Ver1.5(PDF) 」だと,午前の出題範囲がいろいろ変更されています。プレス発表 によると,見直しの観点は,次の通りです。
7.システム戦略
それ以外の分野でも細かく加筆・修正がなされています。
用語の修正レベルですが,プロジェクトマネジメントとシステム監査は,修正が多いです。
ちなみに,昨日とりあげた待ち行列理論は,ネットワークスペシャリストの午後からはなくなりましたが,午前では,1.1基礎理論の1.1.2応用数学に分類される内容で,特に変更はありません。基礎理論では,プログラム言語にECMAScriptが加わったのが,おもな変更点です。
応用情報技術者試験の午後の出題範囲は,それほど大きくは変わっていません。
経営戦略で事業継続計画(BCP)が,システムアーキテクチャで仮想化技術が,ITサービスマネジメントで仮想環境の運用管理が加わっていますが,これらはすでに,午後問題で一度,出題されています。
出題されていないところでの変更は,情報セキュリティでの「情報セキュリティマネジメント,PKI,個人情報保護」などの追加です。応用情報技術者試験になってから,情報セキュリティマネジメントについては午後で一度も出題されていませんので,このあたりが秋試験に出てくる可能性は高いかな,と思います。
私の書籍,「
徹底攻略 応用情報技術者教科書 平成24年度 」は,出題傾向を見て,なるべく新しい技術もちゃんと掲載するところに注力しています。ですので,ここに挙げた用語の,8割方は押さえていると思いますが,それでも足りない部分は少しはあります。
書籍は,すぐには変更できませんので,来年度の改訂で対応する予定です。
セミナーについては,すぐに対応できますので,「
スタートアップセミナー 合格への道しるべ 応用情報技術者」以降,新しい出題範囲に対応します。
出題範囲は,時代に合わせてどんどん変更されていきます。
今の時代に合った知識を身につけるためにも,新しいことにもどんどん興味を持っていきましょう。