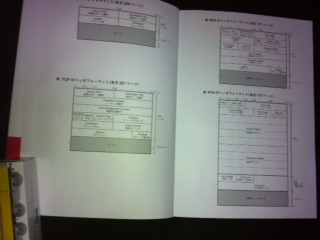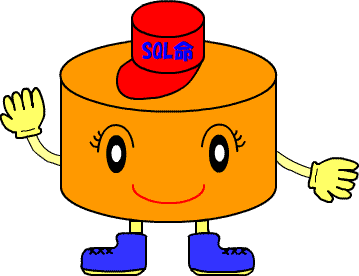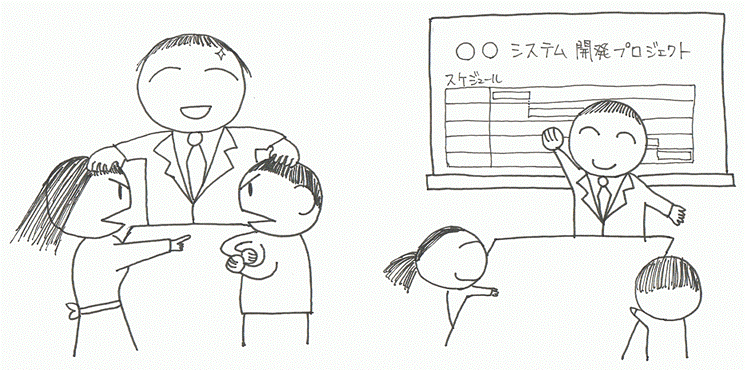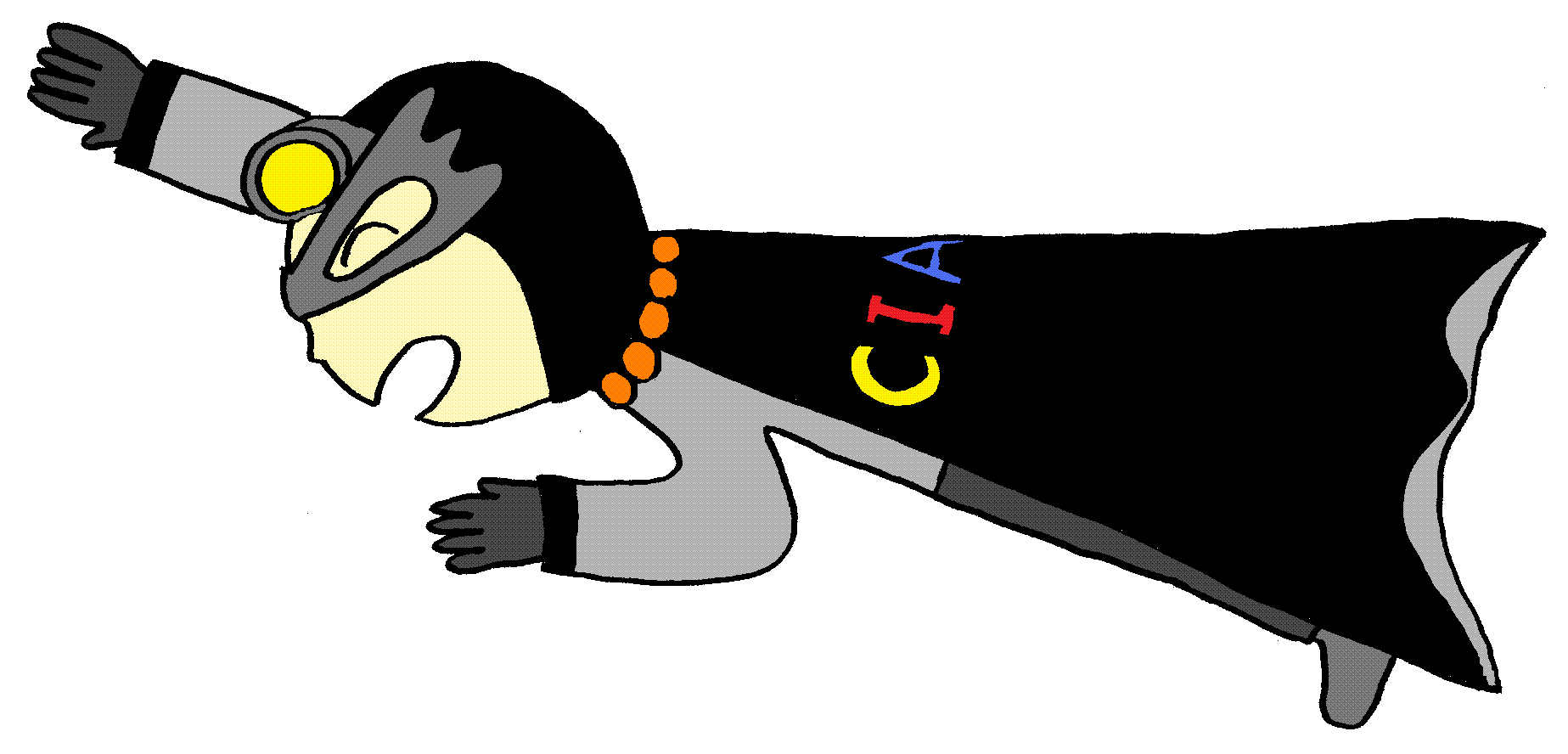
思い込みを外す
本日は,わく☆すた公開セミナー「情報セキュリティスペシャリスト対策」3回コースの3回目,最終回を開催しました。
雨の中,参加していただいた皆様,ありがとうございました。
今日は,午後2の演習を中心に行いました。
情報セキュリティスペシャリストの午後2は,他の試験区分に比べても独特で,「何を聞かれているか」をつかむことが大切です。
そして,午後2で聞かれているのは,「セキュリティの知識をいっぱい知っているか」ではありません。
試験問題で登場している会社で,「その会社に最適なセキュリティ対策は何か」を考えるところが大切なのです。
例えば,今日取り上げた,SC平成23年午後2問2では,A社情報システム部のY主任が基本設計を担当します。
でも,Y主任は,十分な経験と知識がないと判断され,SIベンダE社のT氏に助言を受けながら設計を行うのです。
そのY主任は,問題文の中で,T氏の案に反抗して,「ネットワークフォレンジックと呼ばれる案もあるのではないか」と主張します。
でも,その案は実は,A社の状況では使えないのです。。。
この問題では,なぜその案が使えないのか,というのが設問になっています。
単に新しい技術を入れればいい,というわけではなく,その技術を会社の状況に合わせて取捨選択することが大切なのです。
午後2で出てくる会社は,毎回変わります。
ですので,「こういう時はこういう技術」という固定概念を持っていると,それが解答を作る時の邪魔になります。
思い込みを外して,なるべく真っ白な状態で,問題文の状況を受け入れることが大切です。
それができれば,逆にそれほど知識がなくても,情報セキュリティスペシャリストの試験は突破できます。
知っていることよりも,考え方がわかっていて,臨機応変に対応できることの方が重要な試験です。
試験問題を解くとき,なるべく問題文に先入観を持たず,まっさらな状態から解いてみることを意識してみてください。
その,思い込みを外すコツがつかめれば,合格は近いです。
●わく☆すたWebページ更新情報
公開セミナー「応用情報技術者対策 3回コース」3回目DVDを発売いたしました。
公開セミナー「情報セキュリティスペシャリスト対策 3回コース」3回目DVDのご予約を開始いたしました。
「データベーススペシャリスト 平成23年春期・解答解説」DVDを発売いたしました。
現在発売中のセミナーDVDはこちらです。(AP,SC)