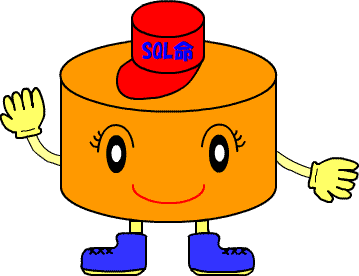「団体戦」の情報処理技術者試験
私は昔,高校生クイズ選手権に出たことがあります。(といっても,中国予選敗退ですが。^^;)
3人一組で,チームでクイズをやる,というのは,一人とは違った面白さがあります。
走るのも,マラソンだと自分の走りさえすればいいですが,駅伝だと,タスキを渡したり,みんなで一丸となって走る面白さがあります。私が好きで良く出ている大会に,「EKIDENカーニバル」というのがありますが,こういう勝負ではなく楽しみが中心の大会で,みんなで走るのはとても面白いです。
情報処理技術者試験も,「団体戦」みたいなのがあったら面白いなぁ,といつも感じています。
先日,セミナー懇親会の帰り道で出たアイデアに,「情報処理技術者試験 箱根駅伝」というのがありました。
春・秋の試験で1年かけて,10人で10区間(10区分)を担当して試験を受けて,勝敗を競う,駅伝みたいな競技です。
例えばこんな感じです。
往路(春試験)
1区 データベーススペシャリスト
2区 システム監査
3区 プロジェクトマネージャ
4区 情報セキュリティスペシャリスト
5区 エンベデッドシステムスペシャリスト
復路(秋試験)
6区 ネットワークスペシャリスト
7区 応用情報技術者
8区 システムアーキテクト
9区 ITサービスマネージャ
10区 ITストラテジスト
これで,10区間での午前1~午後2までの合計点数を,チームごとに競います。
もちろん,誰か1人でも不合格だったら,タスキが途切れたことになりますので失格です。
往路,復路の兼務は可能としても,最低5人が必要です。
人数揃えるのが大変だとしても,各企業対抗ぐらいだったら,集まるのかなぁ,とも思います。
もちろん狙うは,並み居る実業団(大企業)を相手にして,チームわく☆すたが優勝,という展開です。^^;
春試験の合格発表の時に中間順位を,秋試験の合格発表の時に最終結果を発表すると,かなり盛り上がるような気がします。
それ以外にも,「午前1から午後2を4人で受けて合格」する団体戦や,「チームみんなで協力して解くデータベース午後2」なんかも面白いかな,って思います。
情報処理技術者試験は個人競技なので,自分が頑張って勉強しさえすれば合格できる。。。
と思っている方も多いと思います。
多分,応用情報技術者試験ぐらいまでは,それでOKだと思います。
ただ,高度区分,特に論述式の試験になると,そうでもありません。
最近論文を読んでいてつくづく感じるのですが,午後2の論文って結構,その人の「人生経験」がにじみ出てるのです。
論述系5区分は,すべてチームで仕事をすることが前提の試験区分ですので,そこでの人のやりとりを,表現せざるを得なくなります。そこで,今までどのように人と関わってきたのかが,読んでいる側には結構はっきり伝わるのです。
仕事をする上では一番大切な能力は人とのコミュニケーション能力だとは思いますが,それは試験でも一緒です。
なるべく自分の殻を破って,人と関わっていくことは大切です。
せっかくなら試験も,そういったコミュニケーションの手段に使えればいいな,と感じています。
とりあえずは,同じ試験を受ける仲間を見つけて,「一緒に合格しよう!」と励まし合うところから始めると,やる気も出るのでおすすめです。
今日で1月も終わりです。
一緒に,試験合格という共通の目的に向けて進んでいきましょう。